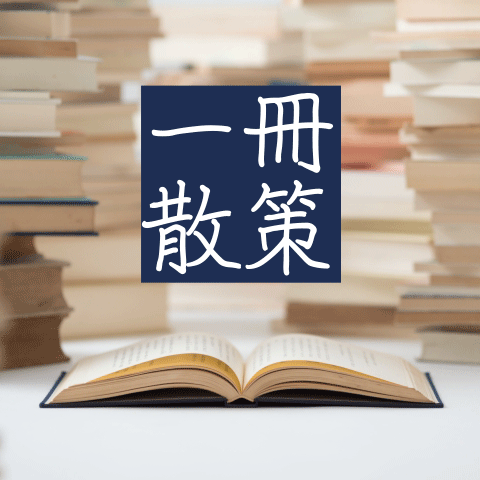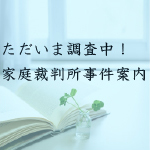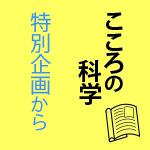#心理 タグ 記事一覧
プロ精神科医あるあるノート(兼本浩祐)| 2024.07.17
(第6回)死ぬ代わりに先延ばしを選ぶ
本当にこの先に希望はあるのか
突然ですが、この先、生きていていいことはありそうだと思われますか。
実習に来ている医学部の学生さんにそう尋ねると、「あると思います」と迷いなく明るく答える人が圧倒[……]
ただいま調査中! 家庭裁判所事件案内(高島聡子)| 2024.07.04
(第10回)ウェブはじめました――親権者変更
令和の家裁から
調停や調査の姿が、大きく変わりつつある。
令和3年度以降、全国の家裁で「ウェブ会議システムを用いた家事調停」、通称「ウェブ調停」が導入され始めており、遅くとも令和6年度中にはす[……]
プロ精神科医あるあるノート(兼本浩祐)| 2024.06.13
(第5回)機能は貝のようになったとしても
赤ん坊は人か動物かをめぐる議論
どうして赤ん坊を私たちは人と認めることができるのでしょうか。テレビなどで新生児の誕生を寿ぐ番組を見ていると、赤ん坊こそ一番純粋な人間らしい人間ではないかと即座に反論を[……]
ただいま調査中! 家庭裁判所事件案内(高島聡子)| 2024.06.04
(第9回)ロスト(喪失)――離婚等(人事訴訟・控訴審)
電話
「総括、調査室の借用依頼です。高裁から」
内線電話が転送されてくる。調査官の調査では、他庁の管轄区域に当事者が住んでいる場合、最寄りの裁判所の調査室を使わせてもらうことがあり、その窓口は[……]
プロ精神科医あるあるノート(兼本浩祐)| 2024.05.16
(第4回)ミスド、スタバ、コメダの距離感
蝶に好みの花があるように
蝶というのはかなり厳格に特定の花をターゲットにして蜜を吸うのだという話を聞いたことがあります。たとえばモンシロ蝶はタンポポが好きで、アゲハ蝶はヒガンバナ。ちょっと似合いすぎ[……]
ただいま調査中! 家庭裁判所事件案内(高島聡子)| 2024.05.02
(第8回)僕ver.2.0――児童ポルノ製造
手のひらの犯罪
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反保護事件」。家裁ではこれを「児ポ」と略す。
私はどちらかと言えば、家事事件の担当が長い調査官だ[……]
プロ精神科医あるあるノート(兼本浩祐)| 2024.04.16
(第3回)恋人転移から始まり、父親転移を通り、おじいさん転移に到る
若い精神科医の試練のひとつとしての恋人転移
きちんと臨床をしようとしている若い精神科医にとって、最初の試練はいくつかありますが、「恋人転移」もそのひとつでしょう。文字どおり、来訪者が年若い精神科医に[……]