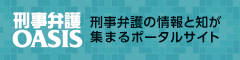「正解病」が検察を蝕む:なぜ小説『ナリ検』を執筆したのか(市川寛)
 市川寛『ナリ検 ある次席検事の挑戦』(2020年8月刊行)は、元検察官の著者が弁護士出身の検察官を主人公にその実態を赤裸々に描く、フィクション小説です。
市川寛『ナリ検 ある次席検事の挑戦』(2020年8月刊行)は、元検察官の著者が弁護士出身の検察官を主人公にその実態を赤裸々に描く、フィクション小説です。現在、弁護士として活躍しつつ、さまざまなメディアで発信をする市川寛さんに、本書執筆のきっかけ、また本書への思いについて、ひとこといただきました。
 私は1993年に検事任官し、2007年に弁護士登録しましたが、昨年末の時点で検事と弁護士の経験年数がどちらも13年弱と同じになりました。
私は1993年に検事任官し、2007年に弁護士登録しましたが、昨年末の時点で検事と弁護士の経験年数がどちらも13年弱と同じになりました。
だからというわけでもありませんが、検事時代に考えていたことを忘れ去ってしまう前に、何かしらの形で遺しておきたいという思いがあります。
もとより私は検察の何もかもを見聞きしてきたわけではありませんし、私の考えがそのまま検察という組織の思考だと断言するつもりもありません。
ですが、検事が行う外形的な行為や言動は知ることができても、「なぜそうするのか」という検事の思考方法についての情報は多くないので、多少なりとも社会の役に立つのではないかと考えて、これまで海外メディアによるものも含めて数々の取材に応じたり、自ら発信もしてきました。この小説もその一環になります。
つまりこの小説は、敢えて一口で言えば「検事の思考方法」を伝えようとするものです。
狭い検察の独善性
裁判官・弁護士・検事の法曹三者のうち、検事が一番少なく、今も全国で2000人に満たない人数です。検察はとても狭い世界なのです。ちなみに、裁判官は3000人弱、弁護士は約4万人です。
しかも、検事には司法修習を終えてすぐに任官しますから、昨日まで学生だった人が他の世界を知らないままに入って、検察の作法だけを叩き込まれてしまいます。
この「作法」が客観的に正しければ問題はありませんが、どう贔屓目に見てもそうではないものが含まれています。無罪判決に抵抗したり、弁護人に全証拠を開示しないといったことです。
こうした芳しくない「作法」にも検察なりの理由はありますが、その理由自体が狭い検察の中でしか通用しないこともあります。検事の思考方法がどこででも通用するはずがないのです。これは私が弁護士になって改めて痛感したことです。
ところが検察の中にいると、こうしたやり方や考え方の独善性に気づくことができません。少なくとも、「気づいても、それを改めることができない」と言えるでしょう。
私が検察で見てきた限りでは、私も含め、検事の多くは気づいているというよりは、外部からの批判こそが間違っているとうそぶいていたような気がします。孤高を気取っていると言ってもいいかもしれません。
検察も間違える
これまでにも、検察の問題点について多くの人々が指摘しています。そして、例えば無罪判決への徹底抗戦については、検察が「組織のメンツを守るため」だと指摘されることがあります。私もこれに反対はしません。
ですが、「組織のメンツ」と言われてもその中身が判然としませんし、それで考察を終えてしまっていいのだろうかとも思っていました。「なぜ検察は無罪判決を嫌うのか。なぜ抵抗するのか」について、前著『検事失格』(毎日新聞社、新潮文庫)を上梓した後も自分なりにずっと考えていました。
そして、この疑問に対する現時点での私なりの仮説を、この小説に書いたつもりです。
刺激的な表現をすれば、実は無罪判決を最も嫌っているのは検察ではなく、私たち市民なのではないか。これが私の現時点での仮説です。
多くの市民は検察を信頼していると思います。が、その信頼の根拠が「検察は間違えない」ことだとしたらどうでしょうか。
捜査活動も、起訴も、法廷での活動も、すべてが正しく、何一つ誤りはない。たしかにそうであるべきとは思います。が、「常にそうあり続けられるだろうか」と正面から問えば、誰もが「否」と答えるでしょう。検察が人間の集まりだからです。
それでは、検察が間違えたときの市民の反応はどうでしょうか。
これは報道が誘導するところにもよると思いますが、「無罪になる事件をなぜ起訴したのか。そもそも起訴前の捜査が間違っていたのではないのか」との批判が浴びせられるはずです。
もちろん、起訴とは強大な国家権力が無力な個人を刑事裁判に引きずり出すことですから、誤りがあってはならないことです。が、神ならぬ人間のやることに「絶対」はあり得ません。それなのに、市民は人間の集まりにしかすぎない検察に「絶対」を求めているのではないでしょうか。
「検察は絶対に間違えてはならない」が検事の矜持のよりどころになっているとは思いますが、同時に大きなプレッシャーになっているとも思います。なにしろ「絶対に」ミスが許されないのですから。
「司法試験に合格したのだから、そのくらいのプレッシャーに負けるな」との指摘もあろうかと思います。これにも反対はしません。
間違いという結果と、それに至る過程
検察の誤りにも様々な過程があります。
結果として無罪判決になったとして、起訴に至る捜査のすべてが否定されていいとは思いません。もちろん、初めから見当違いのひどい捜査もありますから、そのような捜査を正当化するつもりなどありません。あくまでケースバイケースです。
が、とくに殺人、強盗といった突発的に起きた事件で、被疑者が事件から間もなくのうちに逮捕されたような場合は、刑事訴訟法の定める時間制限の中で、後手に回った捜査が慌ただしく進められることもあります。
このような場合に、たまたま有罪と思わせる証拠があったばかりに、警察も検事も油断して捜査を続け、起訴してしまうことはゼロではないと思います。
もちろん、無実の人を誤って起訴したのですから、こうした事件で無罪判決が出るのは当然ですし、起訴した検察は厳しい批判を免れないでしょう。
が、無罪という結果に対しては批判できたとして、果たして捜査の全過程までが批判されなければならないのか、ということです。ここでとにかく強調したいのは、捜査の「全」過程が批判の対象になるのか、です。
ここまでの私の意見に対しては、「検察を不当にかばっている」との指摘があろうかと思います。が、もう少しお付き合いください。
では、無罪判決が出たからには、それに至るまでの検察の「全」活動が否定されるとしましょう。すると検事たちは、検察は、どう思うでしょうか。
悪い結果が出たとき、その結果だけならまだしも、その結果を招いた過程のすべてが否定されて気持ちのいい人間はいません。そして検事も人間です。
先ほども述べたように、人間には「絶対」などありませんから、その時その時に最善を尽くしてもなお、悪い結果に至ることはあり得ます。が、最善を尽くした過程までもが「全」否定されたら、果たしてその人間はまっとうな反省をするでしょうか。
これはむしろ、人が罪を犯した場合にこそ言えると思います。
すべての犯罪がそうだとまでは言えなくても、その人が置かれた状況を考えれば、やむにやまれず罪を犯してしまった場合もあります。そのとき、罪だけでなく、その人の人生や人格までもが全否定されていいのでしょうか。同じ人間をそこまで責めることが許されるのでしょうか。
人によっては、罪だけでなく人格までも否定されたことで自暴自棄になり、かえって再犯に陥ってしまうこともあり得るでしょう。まして、犯した罪とその後に浴びせられる非難とのバランスが取れていなければ、なおさらです。
このように、今の社会は、人に過度の完全性を求めているように思われてならないのです。人に「神であれ」と求めているように思われてならない、と言い換えてもいいと思います。
その反面、結論さえ正しければ、それに至る過程にどんな不正があっても大目に見てしまうようにも感じられます。
例えば「この被疑者は間違いなく犯人だから、逃げも隠れもしないだろうけど、逮捕・勾留して取調べで痛めつけてもいいんだ」となってしまうわけです。
あらゆる場面で、結論の正否には過剰に固執し、翻ってそれに至る過程をないがしろにし過ぎていると思います。
「正解病」の危うさ
「絶対に間違えるな」と常に正解を求める声が、あらゆる人に対して浴びせられ、あらゆる場面で唱えられているのではないか。
その延長で、ひとたび間違えると結果だけでなく過程のすべてまでもが厳しく非難され、じっくりと反省する気力を奪ってしまう。反省しないから原因究明がなく、再挑戦もできない。
こうした情け容赦のない非難が続くことによって、少なからぬ人が一度の過ちによって将来の活躍の機会や場所を失うだけでなく、非難した側も心の底では「明日は我が身か」とおびえて萎縮してしまい、ひいては社会全体が地盤沈下していくのではないか。いわば「正解病」が社会をダメにしているのではないか、と思うのです。
あるいは、「絶対に間違えてはならない」ばかりに、失敗を糧とする試行錯誤によって高みに達することができなくなり、これも社会の発展を妨げているのではないか、と思うのです。
「正解病」のために、無罪判決が出ると、私たちはすぐさま検察のすべてを非難してしまう。
すると検察は、反省どころか「無罪判決が出ると、それまでの全活動が否定される。それは困る」と考えるようになり、無罪を認めずに控訴するのではないか。
「検察は絶対に間違えてはならない」という市民の要求に応えるため、かえって最大の間違いである無罪判決を否定しようとするのではないか。しかも、無罪判決は検察が起訴を間違えたことが明らかになった結果ですから、本当は正解のはずなのに、です。
このような意味で、無罪判決を一番嫌っているのは市民なのではないか、と思うわけです。
私は検察を不当にかばっているのではなく、むしろ検察を真に正すためには、検察の何もかもを厳しく非難するのは得策ではないのではなかろうか、と考えているのです。
検察が間違えたとき、それに至る活動をいたずらに非難するのではなく、原因究明に力を注ぐべきではないのか、と考えているのです。
私たち市民には、一歩間違えると自分の首をも絞めかねない「正解病」の熱を冷ました上での対応が求められるのではないでしょうか。
このように考えていくと、検察を巡る問題は、取りも直さず人間を、社会を考える問題に直結しているような気がしてなりません。
これこそ独善の極みかもしれませんが、私はこれからも、検察を通して人間や社会について考えていきたいと思っています。
この「ナリ検」をお読みいただいた方々にも、検察を初め、人間や社会が抱える問題についてのより良い解決策を考えていただけたら、これに優る喜びはありません。
◆本書の詳細・購入はこちら
市川寛 著『ナリ検 ある次席検事の挑戦』
◆Webセミナーのお知らせ
「再審法改正をめざす市民の会」第4回WEBセミナー
「ナリ検」から読み解く検察官の本音と思考(お話:元検察官・市川寛さん)
9月19日(土)14時 ライブ配信開始
YouTubeによるライブ放送ですので、どなたでも開始時刻に以下のURLにアクセスするだけで無料でご視聴いただけます。
https://youtu.be/ukq_0F-HyP0
詳細は「再審法改正をめざす市民の会」
1965年神奈川県川崎市に生まれる。1993年検事任官。横浜地検、大阪地検、佐賀地検などに勤務し、2005年に辞職。2007年弁護士登録。
著書に『検事失格』(毎日新聞社、新潮文庫)がある。
趣味は写真撮影、ギター演奏など。Twitterアカウント @imarockcaster42