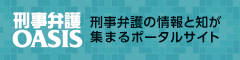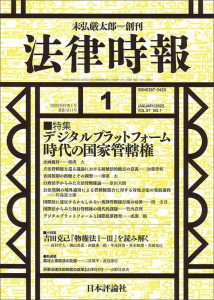(第83回)著作権等侵害罪の適切な成立範囲を探る試み(宮本聡)
 企業法務、ファイナンス、事業再生、知的財産、危機管理、税務、通商、労働、IT……。さまざまな分野の最前線で活躍する気鋭の弁護士たちが贈る、法律実務家のための研究論文紹介。気鋭の弁護士7名が交代で担当します。
企業法務、ファイナンス、事業再生、知的財産、危機管理、税務、通商、労働、IT……。さまざまな分野の最前線で活躍する気鋭の弁護士たちが贈る、法律実務家のための研究論文紹介。気鋭の弁護士7名が交代で担当します。(毎月中旬更新予定)
遠藤聡太「著作権等侵害罪と違法性の意識—民事訴訟係属中の侵害継続に対する責任評価のあり方」
法律時報97巻1号(2025年1月号)118頁より
著作権法においては、条文上、民事における著作権侵害と、刑事罰(著作権等侵害罪)の対象となる著作権侵害の客観面が区別されておらず同一とも考えられるため、処罰範囲が広くなるおそれがある。インターネットやSNSの普及によって、誰もが容易に著作物を生み出し、公表できる「一億総クリエイター時代」が到来し、著作権法は身近な法律となっていること、日本のコンテンツ産業の著しい成長が続いていることなどから、表現活動の過度な萎縮を避け、著作権等侵害罪の成立範囲を適切なものとすることは、法律実務上も非常に重要な課題である。
この課題に正面から取り組んだのが、法律時報の94巻11号(2022年10月号)から97巻3号(2025年3月号)までの間に、合計21回にわたり掲載された、「著作権法と刑法の語らい」と題する連載である。本連載では、著作権法、刑法の学者たちが、双方の学問の立場から、著作権法の諸論点について、新規かつ優れた議論を展開しており、読者の皆様には本連載の全てに目を通されることをお勧めするが、紙幅の関係で、今回は、表題の遠藤聡太教授による「著作権等侵害罪と違法性の意識」のみを取り上げる。
日本の刑事法においては、犯罪が成立するためには罪を犯す意思が必要であり(刑法38条1項)、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」(同条3項)とされている。そして、自身の行為が適法だと信じていた(違法性の意識を欠いていた)ときは、違法性の意識を欠くことについて「相当な理由」がある場合には故意ないし責任が認められない(つまり無罪)とする考え方が有力である1)。
本稿では、行為者にとって適法か違法か明確でない行為を継続しながら、その適法性を民事訴訟で争っていたが、最終的に民事訴訟で違法性(著作権等侵害)が認められた事案を想定して、著作権等侵害罪の成立範囲を「違法性の意識」の点から制限する議論を展開する。
本稿は、①違法の疑いがある行為を直ちに控えさせることは、著作権法の正当化根拠である「著作物を創作するインセンティブを確保し、表現物の創作を促す」という点にそぐわないこと、②「少なくとも一部の権利制限規定や類似性要件については、民事判例による事後的なルール形成が期待されて」おり、「民事訴訟による判断が確定するまでは、差止めがない限り、原則として行為の継続を容認するのが著作権法の態度であると理解する余地」があること、③著作権法の規律対象は、「企業や権利団体のほか個人利用者を広く含むところ、著作権法上のルールに係る知識・経験の具備を当然の前提とした制度運用は実際上困難であること」を挙げ、これらの理由から、「違法性の意識」の解釈において著作権等侵害罪の成立範囲が狭くなる余地を指摘する2)。また、著作権等侵害罪において、違法性の意識を欠くことに関する「相当な理由」の有無は、(上記①のとおりの)著作権法の態度から「国家による非難の適格性が一般的に大きく低下することを前提に」、「事案毎の規範遵守要求の過酷さ」を総合判断することによって決せられるものと整理する。
私見であるが、以上のように、著作権法の特殊性に着目し、違法性の意識の点から著作権等侵害罪の成立範囲を限定する本稿の試みは、違法性の意識に関する一般論を変更するよりずっと実務に受け入れられやすいと思われる。表現活動については、基本的に、国家による事前抑制は避けるべきであり(憲法21条2項等参照)、行為者側に表現行為の適法性に関する調査義務を課すことには慎重になるべきなのだとすれば、違法性の意識を欠くことの「相当な理由」が認められる範囲は、他の法分野より広くなる可能性があるだろう。
また、本稿の挙げる「相当な理由」の考慮要素である「国家による非難の適格性」、「事案毎の規範遵守要求の過酷さ」について、著作権等侵害罪の違反類型ごとに差異があるのか、(例えば株式会社では内部統制システムに従い多数人による業務分担が行われているが)行為者側における(あるいは行為者側が利用可能な)適法性のチェックシステムの合理性や、その利用態様等も考慮されるのかなど、興味が尽きないところである。
今後、本稿や本連載で示された、著作権等侵害罪の適切な成立範囲を探る試みが更に深まることを期待したい。
本論考を読むには
・法律時報97巻1号 購入ページへ
・TKCローライブラリー(PDFを提供しています。)
◆この記事に関するご意見・ご感想をぜひ、お問い合わせフォームよりお寄せください。
この連載をすべて見る
脚注
| 1. | ↑ | 最決昭和62年7月16日刑集41巻5号237頁、最判平成8年11月18日刑集50巻10号745頁(河合伸一裁判官の補足意見)参照。 |
| 2. | ↑ | より詳細には、条文上「知りながら」という要件のある犯罪については、確定的な違法性の意識がない限り、犯罪の成立は否定され、それ以外の著作権等侵害罪については、「確定的な違法性の意識を欠いたことにつき相当の理由があれば免責される」と論じている。 |
 宮本 聡(みやもと・さとし)
宮本 聡(みやもと・さとし)2007年慶應義塾大学法学部卒業。2009年東京大学法科大学院修了。2010年弁護士登録。西村あさひ法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)で企業の危機管理案件を数多く経験後、米国留学(Boston University School of Law (LL.M. )修了)を経て、2017年~2021年に東京地検検事として経済事犯、特殊過失事犯等の捜査に従事。2021年弁護士再登録、現在西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士。主な業務分野は、企業不祥事対応、刑事事件を含む取締当局対応等の危機管理、コンプライアンスや不正防止体制の構築等。主な著書・論稿として『法律実務家のためのコンプライアンスと危機管理の基礎知識』(共著、有斐閣、2025年)、『危機管理法大全』(共著、商事法務、2016年)、「不正競争防止法違反事件の刑事裁判における営業秘密秘匿決定制度の実務」(共著、NBL1049号(2015年5月1日号))等。また、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業が毎月発行している危機管理ニューズレターの編集委員も務める。