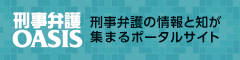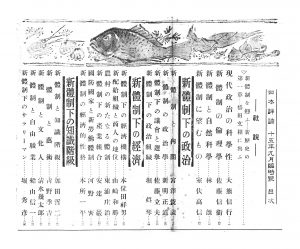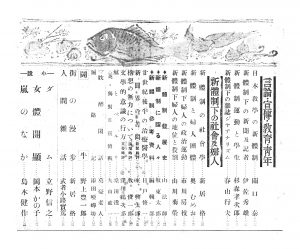挙国一致「新体制」への支持を明確化:1940(昭和15)年9月臨時号を読む
- #政治
- #歴史
- #特集_日本評論を読む
- #社会
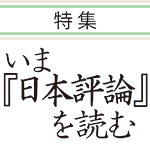
 特集:いま『日本評論』を読む
特集:いま『日本評論』を読む『日本評論』の発行は、「「経済往来」改題飛躍号」と題する1935年10月号をもって開始された。改題創刊号の表紙には、「高級大衆雑誌」と記されている。北河賢三「戦時下の世相・風俗と文化」によれば、『中央公論』『改造』『日本評論』『文芸春秋』の4誌に代表される綜合雑誌は、学生・インテリ層を主な読者にもち、アカデミックな学術論文をも取り入れて一種の民間アカデミーを形づくっていたという(『十五年戦争史2』青木書店、1988年)。そのうえで北河は、批判性を生命とする綜合雑誌にとって、日中戦争の開始から人民戦線事件にいたる時期の相次ぐ言論弾圧は致命的であったと指摘している。
では、『日本評論』は、知識人たちは、こうした時代のなかで、どのような軌跡を描いたのであろうか。以下、3つの『日本評論』特集号を素材としながら、これを読み解いてみることにしよう。(大日方純夫)
(1)「広田内閣打倒号」:1937(昭和12)年2月号を読む
(3)「大東亜戦争号」:1942(昭和17)年1月号を読む
「新体制下の日本」:1940(昭和15)年9月臨時号を読む
1937年7月の盧溝橋事件を契機に日中戦争は全面化した。政府は中国「膺懲」を声明し、国民精神総動員運動を展開していった。日中戦争の勃発は「挙国一致」状況をつくりだし、二・二六事件前後から高まっていた反軍感情や政治不信を吹きとばしてしまった(北河『戦争と知識人』)。新聞・ラジオは、政府・軍の発表どおり、中国の「暴戻」ぶりを報道して、敵愾心を煽っていった。12月には、コミンテルンの反ファッショ人民戦線運動を実践したとして、417人が検挙された(人民戦線事件)。そこには、『日本評論』「広田内閣打倒号」(【→本特集記事】)に登場した鈴木茂三郎・山川均らも含まれている。
翌1938年1月、政府は中国との和平交渉を打ち切って「国民政府を対手にせず」と声明した。2月には人民戦線事件(第2次)で労農派教授グループらが検挙された。そこには前年2月号に登場した有沢広巳も含まれている。一方、『日本評論』3月号の大場賢一「大内兵衛その他」は、「人民戦線派」検挙を批判的に論じたとして削除された(北河「戦時下の世相・風俗と文化」)。こうして、人民戦線事件以後、綜合雑誌の大勢は、戦争関係の報道、解説記事、国策への建言的論説を基調とするようになっていった(同前)。
1938年4月には国家総動員法が公布され、11月には近衛内閣が「東亜新秩序」の建設を声明した。一方、10月、河合栄治郎の『ファッシズム批判』(日本評論社)など4著が発禁となった。1940年2月には、斎藤隆夫が衆議院で政府の戦争政策を批判し、3月、この反軍演説により議員を除名された。同月、津田左右吉の古代史関係の著書も発禁処分となった。
1940年6月、近衛文麿は枢密院議長を辞任して新体制運動に乗り出すことを声明した。7月には新体制運動促進のために社会大衆党が解散。7月、第2次近衛内閣が成立し、その後、政友会も民政党も解党して、10月、大政翼賛会が誕生した。
こうしたなか、『日本評論』は1940年9月臨時号「新体制下の日本」を発行している。冒頭に掲げられた「社説」は、「新体制は必至である」と書いてこれを歓迎し、「近衛公の聡明」を讃えながら、新体制を推進すべきその人選に注文をつけている。そして、「新体制が生れようとして新しい歴史の第一章が書きはじめられようとする。(中略)明治以来の古き秩序が、総括的に原則的に、終りを告げて、新しい生活原則が打ち建てられ、新しい日本の第一歩がふみ出される」と書いている。
この号には27人が評論文を寄せている(掲載順と目次の構成は一致しない)。目次では、掲載した評論文を「新体制下の政治」、「新体制下の経済」、「新体制下の知識階級」、「言論・宣伝・教育・青年」、「新体制下の社会及婦人」の5つに振り分けて再編成している。そこに、新体制を可視化し、読者をリードしようとする編輯部の意図を読み取ることができる。したがって、本文の掲載順とは別に、編輯部の意図にそってこの号を目次順に見てみると(各筆者名の後に、必要に応じその専門を補った)、まず5区分に含まれない、いわば総論的な評論文として、大熊信行(経済学・評論家)「現代政治の科学性」、佐藤信衛(哲学)「新体制の倫理学」、林髞(生理学)「新体制と自然科学」、室伏高信「新体制に望むもの」が掲げられている。
 室伏は、「新体制に望む」ことの第一に、担い手の問題をあげる。「旧体制的な人物をそのまゝもつて来ても何んの意味もない」として、「青年」、「未経験者、青二才、危ぶなかしい人々」に期待を寄せる。これは、前述「社説」の基調と共通する。第二は、「イデオロギイ」をはっきりさせることである。室伏は、今日の世界は「全体主義の名」のもとに規定することができると述べ、日本の新体制はこのような「全体主義の嵐」の時代に生まれようとしていると位置づける。すなわち、「自由主義的諸体制が行きつまり、その機能を失ひ、廃物と化さうとして新体制が生れ出ようとする」というのである。こうして室伏は、新体制に際して、「全体的日本主義、もしくは日本的全体主義」を唱道する。「全体主義」は世界的だが、各国民の特性をもつとして、ドイツのナチズムとイタリアのファシズムが相違するように、日本の全体主義は「日本的性格」をもつというのである。ただし、室伏の議論は抽象的・一般的であって、「日本的全体主義」が如何なる点で「日本的」なのかには、何ら言及していない。いずれにしても、室伏は、新体制のもとで、政治だけでなく、経済も文化も全体主義に適合したものになるべきだとする。「全体主義は全体主義に適した文化をもたなければならぬ」、「全体主義下の経済には経済の独自性は最小限度にしか承認されない」というのである。
室伏は、「新体制に望む」ことの第一に、担い手の問題をあげる。「旧体制的な人物をそのまゝもつて来ても何んの意味もない」として、「青年」、「未経験者、青二才、危ぶなかしい人々」に期待を寄せる。これは、前述「社説」の基調と共通する。第二は、「イデオロギイ」をはっきりさせることである。室伏は、今日の世界は「全体主義の名」のもとに規定することができると述べ、日本の新体制はこのような「全体主義の嵐」の時代に生まれようとしていると位置づける。すなわち、「自由主義的諸体制が行きつまり、その機能を失ひ、廃物と化さうとして新体制が生れ出ようとする」というのである。こうして室伏は、新体制に際して、「全体的日本主義、もしくは日本的全体主義」を唱道する。「全体主義」は世界的だが、各国民の特性をもつとして、ドイツのナチズムとイタリアのファシズムが相違するように、日本の全体主義は「日本的性格」をもつというのである。ただし、室伏の議論は抽象的・一般的であって、「日本的全体主義」が如何なる点で「日本的」なのかには、何ら言及していない。いずれにしても、室伏は、新体制のもとで、政治だけでなく、経済も文化も全体主義に適合したものになるべきだとする。「全体主義は全体主義に適した文化をもたなければならぬ」、「全体主義下の経済には経済の独自性は最小限度にしか承認されない」というのである。
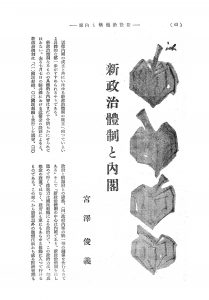
 つづいて、「新体制下の政治」について、宮沢俊義(憲法学)、新明正道(社会学)、堀真琴(政治学)が政治組織などをめぐって論じているが、それぞれの論調は室伏のトーンとはかなり異なっている。宮沢は新政治体制における内閣制度の改革について論じ、国務大臣と行政大臣の分離、内閣総理大臣の権限強化、国務大臣数の減少といった具体的な問題についての整理を試みている。新明は、新体制のあり方を唱道者である近衛に委ねるのではなく、新体制にふさわしい「新しい政治の観念」を提唱することが政治学の課題だとする。
つづいて、「新体制下の政治」について、宮沢俊義(憲法学)、新明正道(社会学)、堀真琴(政治学)が政治組織などをめぐって論じているが、それぞれの論調は室伏のトーンとはかなり異なっている。宮沢は新政治体制における内閣制度の改革について論じ、国務大臣と行政大臣の分離、内閣総理大臣の権限強化、国務大臣数の減少といった具体的な問題についての整理を試みている。新明は、新体制のあり方を唱道者である近衛に委ねるのではなく、新体制にふさわしい「新しい政治の観念」を提唱することが政治学の課題だとする。 そして、新体制が目ざすところは、「利益的分裂、国家と経済との分離をもたらした旧体制を打開して、国民的協同を端的に生かす強力な全体的な体制を樹立しようとする」ことにあるとする。それは、「国家と政府の統制的組織化の範囲を社会の全体に及ぼすもの」とされる。堀は、「自由主義的原理」を克服して、「東亜新秩序の建設、国防国家の完成を絶対的の要請」とする政治組織をつくることを提唱し、「全体主義的原理」にもとづいて、すべての「職務」を「執行府」に集中統合すべきだと主張する。「集中的執行府」である内閣の強化をはかり、議会を「執行府の協力機関」化してしまおうというのである。
そして、新体制が目ざすところは、「利益的分裂、国家と経済との分離をもたらした旧体制を打開して、国民的協同を端的に生かす強力な全体的な体制を樹立しようとする」ことにあるとする。それは、「国家と政府の統制的組織化の範囲を社会の全体に及ぼすもの」とされる。堀は、「自由主義的原理」を克服して、「東亜新秩序の建設、国防国家の完成を絶対的の要請」とする政治組織をつくることを提唱し、「全体主義的原理」にもとづいて、すべての「職務」を「執行府」に集中統合すべきだと主張する。「集中的執行府」である内閣の強化をはかり、議会を「執行府の協力機関」化してしまおうというのである。
「新体制下の経済」では、経済機構、新配給組織と商人、農村の新たな体制、産業組合、新労働体制などが扱われる。
 「新体制下の知識階級」では、加田哲二(社会学)が知識階級、青野季吉(文芸評論家)が芸術、清水幾太郎(社会学)が文化人、船山信一(哲学)が自由職業、堀秀彦(哲学)がサラリーマン、を取り上げている。加田の論は、「わが国最高の指導者」と近衛を讃えることから始まり、近衛が提唱する新体制に「知識階級」が参加・協力すべきことを説く内容となっている。すなわち、「明治・大正・昭和を通じての知識階級のイデオロギー」は「自由主義から社会主義への発展」であったが、「満洲事変を経て、支那事変に至り大きな変革を経験」しているとして、知識階級は再出発が必要だとする。そのためにも、「新体制問題」を利用して、知識階級は新体制に参加し、また、国民に対する新体制の「取次ぎ役」・「解説者」としての任務を担うべきだというのである。
「新体制下の知識階級」では、加田哲二(社会学)が知識階級、青野季吉(文芸評論家)が芸術、清水幾太郎(社会学)が文化人、船山信一(哲学)が自由職業、堀秀彦(哲学)がサラリーマン、を取り上げている。加田の論は、「わが国最高の指導者」と近衛を讃えることから始まり、近衛が提唱する新体制に「知識階級」が参加・協力すべきことを説く内容となっている。すなわち、「明治・大正・昭和を通じての知識階級のイデオロギー」は「自由主義から社会主義への発展」であったが、「満洲事変を経て、支那事変に至り大きな変革を経験」しているとして、知識階級は再出発が必要だとする。そのためにも、「新体制問題」を利用して、知識階級は新体制に参加し、また、国民に対する新体制の「取次ぎ役」・「解説者」としての任務を担うべきだというのである。
 清水の論は、短文であり、内容的にも新体制と文化人の関わりを“真面目”に論じたものではない。むしろ船山の方が、編輯部の要請を“真面目”にうけとめて、まず、「自由職業」とは何かを整理し、そのうえで、「文化人の問題を中心」に、新体制の問題を論じている。すなわち、新政治体制は新経済体制・新文化体制と両々相まっているが、経済に比べて、文化が政治と結びつくのはむずかしいと指摘する。営利を目的とする資本家にとって、自由は手段であるが、「文化人にとつては自由は手段ではなくて目的であり生活そのもの」だからである。しかし、そのうえで船山は、文化は自由を前提とするが、文化の「自由職業的性質」は永遠ではないとして、政治と文化の結びつきが必要だとする。それによって、文化が「非現実的、単に批評的」になり、政治が「文化的貧困」に陥っているという双方の欠陥を克服しようと呼びかけるのである。
清水の論は、短文であり、内容的にも新体制と文化人の関わりを“真面目”に論じたものではない。むしろ船山の方が、編輯部の要請を“真面目”にうけとめて、まず、「自由職業」とは何かを整理し、そのうえで、「文化人の問題を中心」に、新体制の問題を論じている。すなわち、新政治体制は新経済体制・新文化体制と両々相まっているが、経済に比べて、文化が政治と結びつくのはむずかしいと指摘する。営利を目的とする資本家にとって、自由は手段であるが、「文化人にとつては自由は手段ではなくて目的であり生活そのもの」だからである。しかし、そのうえで船山は、文化は自由を前提とするが、文化の「自由職業的性質」は永遠ではないとして、政治と文化の結びつきが必要だとする。それによって、文化が「非現実的、単に批評的」になり、政治が「文化的貧困」に陥っているという双方の欠陥を克服しようと呼びかけるのである。
「言論・宣伝・教育・青年」には、教学の新体制、新体制下の新聞と記者、新体制運動と学生、新体制下の雑誌ジャーナリズムを論じた各論を配している。
 伊佐は、「新体制運動がその目標すらも不明であるに拘らず、澎湃たる国民運動として展開され」ている状況に対し、新聞がその推進力として大きな役割を演じていると指摘する。「新聞は絶えず新体制運動を追廻し、新聞記者は近衛公の一挙手一投足に神経を尖らしてゐる」というのである。また、伊佐は、新体制運動の方向性について、「自由主義、民主主義の否定と資本主義の修正とを指してゐること」はいうまでもないと指摘している。「社説や夕刊短評などに現れてゐる論調に関する限り今日の新聞にはもはや自由主義的色彩など全く見られなくなり、全体主義の一色に統一されてゐる状態であるから、新体制が出来上るとしても慌てゝ転向しなければならない新聞などあり得ない」と、新聞の「鋭い時代感覚」を皮肉交じりに評する。そして、新体制運動は、「国民に深い浸透力をもつ」新聞と協力すべきであり、敵視したり「厄介物扱い」すべきではないとする。
伊佐は、「新体制運動がその目標すらも不明であるに拘らず、澎湃たる国民運動として展開され」ている状況に対し、新聞がその推進力として大きな役割を演じていると指摘する。「新聞は絶えず新体制運動を追廻し、新聞記者は近衛公の一挙手一投足に神経を尖らしてゐる」というのである。また、伊佐は、新体制運動の方向性について、「自由主義、民主主義の否定と資本主義の修正とを指してゐること」はいうまでもないと指摘している。「社説や夕刊短評などに現れてゐる論調に関する限り今日の新聞にはもはや自由主義的色彩など全く見られなくなり、全体主義の一色に統一されてゐる状態であるから、新体制が出来上るとしても慌てゝ転向しなければならない新聞などあり得ない」と、新聞の「鋭い時代感覚」を皮肉交じりに評する。そして、新体制運動は、「国民に深い浸透力をもつ」新聞と協力すべきであり、敵視したり「厄介物扱い」すべきではないとする。
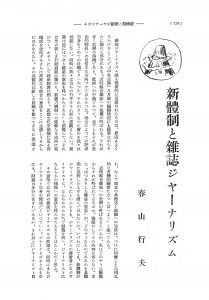 春山は、雑誌ジャーナリズムの問題は、ジャーナリスト自身の問題だとして、雑誌機構との関係や、時代の動きとの関係に、「多くの困難や矛盾が含まれてゐる」とする。従来の旧体制(民主主義国家)の「エキスパート」が、新体制(統制主義国家)の出現によって「アマチユア化、スロオ・モオシヨン化」し、これに代わって、むしろ「アマチユア」が新体制の推進者として登場してきているというのである。
春山は、雑誌ジャーナリズムの問題は、ジャーナリスト自身の問題だとして、雑誌機構との関係や、時代の動きとの関係に、「多くの困難や矛盾が含まれてゐる」とする。従来の旧体制(民主主義国家)の「エキスパート」が、新体制(統制主義国家)の出現によって「アマチユア化、スロオ・モオシヨン化」し、これに代わって、むしろ「アマチユア」が新体制の推進者として登場してきているというのである。
「新体制下の社会及婦人」には、奥むめお・市川房枝・山川菊栄が登場して、新体制下における女性の団体・政治運動や地位と役割について論じている。

 市川は、「婦人」が分担している「国家的に重要なる任務」として、「家庭を主宰」する主婦としての任務と、「男子と共に生産に参加」する任務の二つをあげる。そして、「議会翼賛体制」に対し、「主婦を職能とみ、職能代表としてその代表を参加」させることを求め、「国民半数だけの新体制確立」に終わらないようにと要請する。
市川は、「婦人」が分担している「国家的に重要なる任務」として、「家庭を主宰」する主婦としての任務と、「男子と共に生産に参加」する任務の二つをあげる。そして、「議会翼賛体制」に対し、「主婦を職能とみ、職能代表としてその代表を参加」させることを求め、「国民半数だけの新体制確立」に終わらないようにと要請する。
山川も、「新体制が婦人の協力を求める」なら、「参政権を拒む理由はあるまい」と主張する。また、農業、鉱・工業、商・交通業、その他すべて女性の力に負うところは大きくなっていくにもかかわらず、差別待遇が著しいとして、「各種職能代表」に「或割合で女性の代表」を参加させることなどを提起する。「女性の政治上、経済上、教育上の切実な要求を反映した政策」を示すことを、「指導者の義務」として求めるのである。
以上概観したように、この臨時号では、編輯部そのものが「社説」(おそらく編輯長の室伏が執筆)を掲げ、室伏自身も前述のように「新体制に望むもの」を書き、各論者が新体制と関わって、それぞれの立場・論点から議論を展開している。さらに編輯部自身も「新体制参考資料」を掲載し、「山法師」名の「新体制発展史」で一連の経緯を概観するなどしている。
巻末の編集後記(「編輯者から」)で、『日本評論』は「あくまで新体制を支持する」と宣言している。臨時号はそうした立場から、「政治、経済、文化、社会、青年と、あらゆる部面にわたつて、新体制がどのやうなものであるか、またあるべきか」について、各方面の論者に執筆を依頼し、その「指導的な論策を一巻のうちにおさめた」ものであった。ただし、編集後記は「よき筆者の乏しいこと」を嘆いてもいる。
1933年末、近衛のブレーン・トラストとして昭和研究会が発足し、蠟山正道を幹事役として活動を開始していた。そして、1937年6月の第一次近衛内閣成立後、政策立案のための研究を推進して、対中国政策、国民組織化、第二次近衛内閣成立前後の新体制運動に影響を及ぼしていったといわれる(北河『戦争と知識人』)。『日本評論』臨時号「新体制下の日本」に執筆した加田・清水・船山らも、これに参加していた。
本号のPDFを購入する 【→日評アーカイブズへ】
本号の復刻本を購入する 【→日本評論社へ】
 大日方純夫(おびなた・すみお)
大日方純夫(おびなた・すみお)
早稲田大学教授、専門は日本近現代史。
1999年より現職。
主著に、『警察の社会史』(岩波新書、1993年)、『未来をひらく歴史:東アジア3国の近現代史』(共著、高文研、2005年、日本ジャーナリスト会議特別賞受賞)、『新しい東アジアの近現代史:未来をひらく歴史(上)(下)』(共著、日本評論社、2012年)、『維新政府の密偵たち:御庭番と警察のあいだ』(吉川弘文館、2013年)、『「主権国家」成立の内と外』(吉川弘文館、2016年)、『日本近現代史を読む 増補改訂版』(共著、新日本出版社、2019年)など。
- #政治
- #歴史
- #特集_日本評論を読む
- #社会