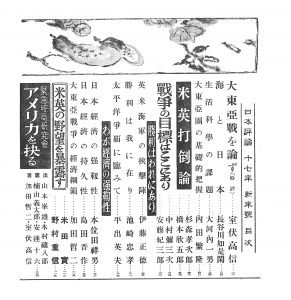“無謀”極まる大戦争推進の旗振り役へ:1942(昭和17)年1月号を読む
- #政治
- #歴史
- #特集_日本評論を読む
- #社会
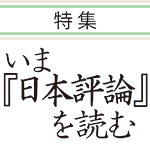 特集:いま『日本評論』を読む
特集:いま『日本評論』を読む『日本評論』の発行は、「「経済往来」改題飛躍号」と題する1935年10月号をもって開始された。改題創刊号の表紙には、「高級大衆雑誌」と記されている。北河賢三「戦時下の世相・風俗と文化」によれば、『中央公論』『改造』『日本評論』『文芸春秋』の4誌に代表される綜合雑誌は、学生・インテリ層を主な読者にもち、アカデミックな学術論文をも取り入れて一種の民間アカデミーを形づくっていたという(『十五年戦争史2』青木書店、1988年)。そのうえで北河は、批判性を生命とする綜合雑誌にとって、日中戦争の開始から人民戦線事件にいたる時期の相次ぐ言論弾圧は致命的であったと指摘している。
では、『日本評論』は、知識人たちは、こうした時代のなかで、どのような軌跡を描いたのであろうか。以下、3つの『日本評論』特集号を素材としながら、これを読み解いてみることにしよう。(大日方純夫)
(1)「広田内閣打倒号」:1937(昭和12)年2月号を読む
(2)「新体制下の日本」:1940(昭和15)年9月臨時号を読む
「大東亜戦争号」:1942(昭和17)年1月号を読む
1941年1月、大本営政府連絡会議は「大東亜長期戦争指導要綱」・「対支長期作戦指導要綱」を決定し、3月には国防保安法が公布された。4月、日米交渉が正式に開始されたが、7月、御前会議は対米英戦も辞せずと決定した。7月、米政府は在米日本資産凍結令を公布し、8月には発動機燃料・航空機用潤滑油の対日輸出を禁止した。10月、東条内閣が成立し、11月、御前会議で対米交渉不成立の場合、12月初旬に武力発動することを決定し、ついに12月、米・英・蘭に対する開戦を決定するに至った。
『日本評論』1942年1月号は「大東亜戦争号」である。「編輯後記」は、「対米英開戦を報ずるラジオの歴史的な一声に全国民の血は沸き立つた」と書いている。編輯部は、1941年12月8日の「宣戦の大詔」をうけて、1月号の「全プラン」を「更新」し、「電撃的編輯」によって特集号を発行した。印刷納本(12月20日)が奥付どおりとすれば、10日強で完成したことになる。
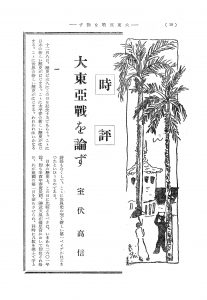 巻頭には、室伏高信「大東亜戦を論ず(時評)」が掲げられ、つづいて特集外の3論稿、長谷川如是閑「海と日本」、大河内一男「生活科学の課題」、内田繁隆「大東亜圏の基礎的把握」が掲載されている。
巻頭には、室伏高信「大東亜戦を論ず(時評)」が掲げられ、つづいて特集外の3論稿、長谷川如是閑「海と日本」、大河内一男「生活科学の課題」、内田繁隆「大東亜圏の基礎的把握」が掲載されている。
その後に、【特輯 英米打倒論】[杉森孝次郎「大東亜戦争の必然」12月15日筆、橋本欣五郎「アジアの黎明、英米の黄昏」](以下、編輯部がつけた各区分を【 】で示し、その後の[ ]内に各論稿の筆者と題名を記し、執筆月日の記載がある場合は付記)、【戦争の目標はここに在り」[安藤紀三郎「国民に望む」、中村弥三次「戦争の目標こゝに在り」]、【勝利は我れに在り】[伊藤正徳「英米海軍の挟撃陣」、池崎忠孝「勝利は我れに在り」12月13日、平出英夫「太平洋争覇に臨みて」]、【わが経済の強靭性】[本位田祥男「日本経済の強靭性」、島田晋作「日本経済の持久性」12月13日、加田哲二「大東亜戦争の経済綱領」12月13日]、【米英の野望を暴露す】[米田実「米英の横暴から大東亜戦争へ」、野村重臣「大東亜戦争原因論」]がつづいている。いずれも、特集号のために依頼をうけて、慌ただしく執筆されたものであろう。
 杉森(社会学者・政治学者)は、米英に対する「大東亜戦争」は、日本の「自衛」のため、「大東亜」を「救済」する「義侠」のため、日独伊三国同盟にもとづく世界史的な「正義」と「進歩」のための「必然」的な戦争だと主張する。中村(法学者)は、「聖戦目標として掲げた根本理念」は、現在の「世界的正義と道義とに適合」すると主張する。この戦争は、英米諸国による「世界的略奪の罪悪」、「シヤイロツク民族」による「貪婪な搾取の政界秩序」を打破するための戦いだというのである。池崎(評論家)は、「大英帝国の落日がはじまり、アメリカの顛落が開始された」、「世界はさらにその新しい歴史の第一歩を踏み出さうとしてゐる」と書く。こうした学者・評論家とあわせて、橋本・安藤・平出といった軍人たちが、執筆陣に登場していることが目を引く。
杉森(社会学者・政治学者)は、米英に対する「大東亜戦争」は、日本の「自衛」のため、「大東亜」を「救済」する「義侠」のため、日独伊三国同盟にもとづく世界史的な「正義」と「進歩」のための「必然」的な戦争だと主張する。中村(法学者)は、「聖戦目標として掲げた根本理念」は、現在の「世界的正義と道義とに適合」すると主張する。この戦争は、英米諸国による「世界的略奪の罪悪」、「シヤイロツク民族」による「貪婪な搾取の政界秩序」を打破するための戦いだというのである。池崎(評論家)は、「大英帝国の落日がはじまり、アメリカの顛落が開始された」、「世界はさらにその新しい歴史の第一歩を踏み出さうとしてゐる」と書く。こうした学者・評論家とあわせて、橋本・安藤・平出といった軍人たちが、執筆陣に登場していることが目を引く。


 この後に、特集号は、関係の各論稿をはさみながら、3つの座談会を掲載している。岩淵辰雄(ジャーナリスト)・三木清(哲学者)・菅太郎(官僚)らによる「第五回日本評論時局研究会 決戦政治の確立」、陸軍中将石原莞爾を囲んでの、石原の「世界最終戦論」をめぐる6人(京都大学の理学・工学の研究者ら)の「戦争の形態」、そして、木村禧八郎(ジャーナリスト)・楠山義太郎(同)・安達十六(陸軍軍人)・加田哲二(前出)・室伏高信(同)らによる「日本評論緊急時局研究会 アメリカを抉る」である。座談会「決戦政治の確立」では、「翼賛会を現在の情勢に応じてどう改革したらよいか」という司会者の問いかけをうけて、まず、三木が提起した「政治の能率化」をめぐって論議し、さらに、「政治意思の問題」、「政治の国民的反省」、「政治の科学的認識」へと議論をすすめて、「翼賛壮年団の新課題」や「選挙の問題」を話し合ったのち、最後に「決戦政治の確立」について意見交換している。また、座談会「アメリカを抉る」は、「米英をどう打倒し、又今後世界をどう新しく建直すべきか」をめぐって議論を展開し、最後に室伏の提案により、参加者全員で「大日本帝国陸海軍万歳」をして終わっている。
この後に、特集号は、関係の各論稿をはさみながら、3つの座談会を掲載している。岩淵辰雄(ジャーナリスト)・三木清(哲学者)・菅太郎(官僚)らによる「第五回日本評論時局研究会 決戦政治の確立」、陸軍中将石原莞爾を囲んでの、石原の「世界最終戦論」をめぐる6人(京都大学の理学・工学の研究者ら)の「戦争の形態」、そして、木村禧八郎(ジャーナリスト)・楠山義太郎(同)・安達十六(陸軍軍人)・加田哲二(前出)・室伏高信(同)らによる「日本評論緊急時局研究会 アメリカを抉る」である。座談会「決戦政治の確立」では、「翼賛会を現在の情勢に応じてどう改革したらよいか」という司会者の問いかけをうけて、まず、三木が提起した「政治の能率化」をめぐって論議し、さらに、「政治意思の問題」、「政治の国民的反省」、「政治の科学的認識」へと議論をすすめて、「翼賛壮年団の新課題」や「選挙の問題」を話し合ったのち、最後に「決戦政治の確立」について意見交換している。また、座談会「アメリカを抉る」は、「米英をどう打倒し、又今後世界をどう新しく建直すべきか」をめぐって議論を展開し、最後に室伏の提案により、参加者全員で「大日本帝国陸海軍万歳」をして終わっている。
この号は、この他、【特輯 進め南へ】、政界時評「大東亜戦争の意義」、田中直吉「日米外交史」、黒川修三「英国大東亜侵略史」などを収録し、さらに「大東亜戦争」を賛美する山口誓子の句、釈迢空・斎藤茂吉・北原白秋の歌などを掲載している。
以上のように、この「大東亜戦争号」は、「大東亜戦争への出発を記念」(編輯後記)するものであった。巻頭の室伏の「時評」がそれをよく示している。前述の新体制に関する「社説」と同様、歯が浮くような文の羅列と煽情的な表現が目立つ。今日からみれば、まさに“噴飯もの”だが、その“昂揚ぶり”を確認するため、少し抜粋してみる。
十二月八日、歴史は永久にこの日を紀念するであらう。こゝに日本の新しい歴史がはじまる。こゝに太平洋の新しい歴史がはじまる。こゝに世界の新しい歴史がはじまる。
国民はわが軍の報道に絶対の信頼をおかなくてはならぬ。この信頼が勝利への絶対条件である。われわれはわが陸海空軍に絶対信頼するとともに、その報道に絶対の信頼を払はねばならぬ。
偉大な目的のために結束しよう。われわれの目的は偉大でもあり、正義でもあり、霊感すべき崇高さをもつてゐる。全太平洋の支配へ、大東亜民族の解放へ、英米の打倒へ。「英米打倒せざるべからず。」
12月8日の開戦と緒戦の勝利は、国民を興奮させ、熱狂させた。欧米列強による支配からアジアを解放し、アジアの「共栄」を実現するという“理念”は、大義なき日中戦争と、その泥沼化に鬱屈していた気分・感情を“一掃”した。今日から見れば、巨大な幻影と虚偽でしかない“理念”が人々をとらえ、“無謀”極まる大戦争へと駆り立てていった。戦争を展開する政府・軍部のもと、メディア・知識人・文化人は、戦争推進の旗振り役となった。室伏は「わが国の勝利を疑ふものはもはや一人もないであらう」と書いている。しかし、その3年8ヵ月後、日本は敗戦の日を迎えた。そして、敗戦によってこそ、本当に新しい日本の歴史が始まった。室伏とは全く逆の意味で、「十二月八日」は「永久」に「紀念」される日となったのである。
言論人・知識人の“変説”の転機となった80年前、その前後の時期の『日本評論』を読みながら、今、あらためて時代のなかで、メディアは、知識人は、文化人は、いかにあるべきかを考えてみたい。「暴支膺懲」の排外主義を煽った日中全面戦争、議会を骨抜きにするファッショ的な政治体制の再編成を煽った「新体制」運動、そして、「アジア解放」の「聖戦」を煽った「大東亜戦争」。その敗戦から約75年、排外主義が高まり、議会政治が形骸化し、対外的な“危機”が煽られ、“戦前”的な状況が際立つ今、その思いを特に強くする。
『日本評論』1937年2月号【→本特集記事】で斎藤隆夫は、広田内閣の膨大な軍事費支出、増税、赤字国債増発の無責任さを糾弾し、国際情勢を調整するための外交上の努力は「徹頭徹尾何物も無い」と批判した。浜田国松も広田内閣の「外交失敗」を「近時稀有の大失敗」と糾弾した。「日支の親善とその経済提携を熱望」し、「両国国交の基調を此処に置かなければならぬ」と我々が主張してきたにもかかわらず、これをことごとく裏切ったというのである。80余年後、東アジアの〝危機〟を政治的な資源とし、外交的な努力を放棄しつづける現政権のあり方が二重写しになって見える。
他方で、権力を忖度するメディアの状況を、今中次麿「準戦時体制と議会政治」(『日本評論』1937年2月号【→本特集記事】)は、「日本の今日のジャーナリズムは、単にジャーナリズムの機能を喪失しつつあるのみでなく、積極的に誤つた判断を国民へ植えつけるための政府の御用機関に化しつゝある」と批判していた。80余年前のこととは思えない。
そのうえで、堀真琴「新体制下の政治組織」(『日本評論』1940年9月臨時号【→本特集記事】)が書いていたことを、現政権による議会軽視・無視のさまと重ねあわせてみる。議会は「執行府の協力機関」であり、「事更にこれを遅延したり、或は徒らな原則論の引延し策を講ずるが如きことの起らないやう」にしなければならない。まさに、それは「全体主義的原理」の貫徹である。
また、加田哲二「新体制と知識階級」は、「国民の認識を形成する」ためには、「巧妙な信念を持つ解説者がゐなければならぬ」、と書いていた(『日本評論』1940年9月臨時号)。国民を納得させるのが「知識階級の役割」であり、「新体制」は「巧妙なものでなければならぬ」、というのである。
そして、1942年1月の『日本評論』「大東亜戦争号」。知識人たちはいっせいに「大東亜戦争の必然」と「戦争の目標」を解説し、「米英打倒」を国民に呼びかけた。
今、東アジアの軍事的な緊張が最大限に〝活用〟され、政治的な目論見に「国益」が従属させられる事態が進行している。目に余るウソと不正がまかり通り、事実の軽視・無視によって、政治の劣化、知性と理性の劣化が一段とその度を増している。今こそ、歴史を振り返って現在を見つめ直し、私たち自身の身の処し方を律する手がかりにしたいものである。
本号のPDFを購入する 【→日評アーカイブズへ】
本号の復刻本を購入する 【→日本評論社へ】
 大日方純夫(おびなた・すみお)
大日方純夫(おびなた・すみお)
早稲田大学教授、専門は日本近現代史。
1999年より現職。
主著に、『警察の社会史』(岩波新書、1993年)、『未来をひらく歴史:東アジア3国の近現代史』(共著、高文研、2005年、日本ジャーナリスト会議特別賞受賞)、『新しい東アジアの近現代史:未来をひらく歴史(上)(下)』(共著、日本評論社、2012年)、『維新政府の密偵たち:御庭番と警察のあいだ』(吉川弘文館、2013年)、『「主権国家」成立の内と外』(吉川弘文館、2016年)、『日本近現代史を読む 増補改訂版』(共著、新日本出版社、2019年)など。
- #政治
- #歴史
- #特集_日本評論を読む
- #社会