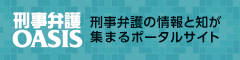(第93回)弁護士の説明義務違反を肯定した初の最高裁判例(加藤新太郎)
 より速く、より深く、より広く…生きた法である“判例”を届ける法律情報誌「判例時報」。過去に掲載された裁判例の中から、各分野の法律専門家が綴る“心に残る判決”についてのエッセイを連載。
より速く、より深く、より広く…生きた法である“判例”を届ける法律情報誌「判例時報」。過去に掲載された裁判例の中から、各分野の法律専門家が綴る“心に残る判決”についてのエッセイを連載。【判例時報社提供】
(毎月1回掲載予定)
奄美ひまわり基金法律事務所弁護過誤事件判決
債務整理に係る法律事務を受任した弁護士が、特定の債権者の債権につき消滅時効の完成を待つ方針を採る場合において、上記方針に伴う不利益等や他の選択肢を説明すべき委任契約上の義務を負うとされた事例
(最高裁判所平成25年4月16日第三小法廷判決)
【判例時報2199号17頁掲載】
東京地裁刑事部で初任判事補として、ユーザーユニオン事件に関与したことを契機として、「弁護士の執務のあり方」の研究が筆者のライフワークになった。『弁護士役割論』は思い入れある学位論文で、『コモン・ベーシック弁護士倫理』も刊行した。弁護過誤は、弁護士が執務の過程で、依頼者または第三者に対して失望と損失を与えるシクジリであり、「執務のあり方」について反省を迫る。したがって、弁護過誤事例は、対象となった関係者・場面・状況に適合したルールを形成する格好の機会であり、汎用性のある規範形成が待望されていた。ただ、筆者が裁判所在職中に、最高裁判例が出現するかは分からなかった。
本件最判は、その意味で待ちに待った、弁護士の委任契約上の説明義務について、最高裁が初めて具体的な判断を示した事例判例である(谷村武則判事の調査官解説『最高裁判例解説民事篇(平成25年度)』211頁は、これだけ読めば学説・下級審裁判例の動向と本件最判の意義が立ちどころに分かるという優れもので、一読の価値がある)。旧知の大橋正春裁判官・田原睦夫裁判官が構成員であり、いずれも補足意見を述べて判旨に深みを加えていることも嬉しい。
論点は、「債務整理を委任された弁護士が、時効待ち方針をとる場合において、依頼者にどのように説明すべきか」である。「時効待ち方針」とは、債権者が依頼者に対して何らの措置も採らないことを一方的に期待して残債権の消滅時効の完成を待つというものだ。
弁護士甲は、Aからクレサラ業者5社の債務整理を受任し、3社から過払金を回収し、1社とは残債務の一部減額和解をしたが、残ったBについては時効待ち方針をとることにした。そこで、甲は、回収した過払金から報酬を控除した残額をAに交付したが、その際の説明の内容の適否が問題となったのである(その後、Aは甲を解任した)。
Aから改めて債務整理の委任を受けた弁護士乙は、B社との和解を成立させたが、甲の仕事ぶりが極めて不誠実であるとの違和感を感じた。そうしたことから、乙は、Aの相続人Xが甲に対して提起した本件損害賠償請求訴訟の原告訴訟代理人を務めている。
原審は、Aが時効待ち方針に異議を述べず黙示に承諾したとして、甲の説明義務違反を認めず、請求を棄却した。しかし、最高裁は、次のとおりの理由付けをして、原判決を破棄し、本件を原審に差し戻す逆転判決を下したのである。
債務整理に係る法律事務を受任した弁護士が、当該債務整理について、特定の債権者に対する残元本債務をそのまま放置して当該債務に係る債権の消滅時効の完成を待つ方針を採る場合において、当該方針は、債務整理の最終的な解決が遅延するという不利益があるほか、当該債権者から提訴される可能性を残し、いったん提訴されると法定利率を超える高い利率による遅延損害金をも含めた敗訴判決を受ける公算が高いというリスクを伴うものであるうえ、回収した過払金を用いて当該債権者に対する残債務を弁済する方法によって最終的な解決を図ることも現実的な選択肢として十分に考えられたなど判示の事情の下では、弁護士は、委任契約に基づく善管注意義務の一環として、委任者に対し、当該方針に伴う不利益やリスクを説明するとともに、当該選択肢があることも説明する義務を負う。
弁護士と依頼者との法的知識・情報の非対称性を克服し、依頼者の実効的な意思決定を保障するためには、弁護士による必要にして十分な情報が付与されることが不可欠である。この原理的規範を前提として、本件最判は、依頼者が債務整理の方針につき意思決定するためには、弁護士の「時効待ち方針の不利益、法的リスク、代替選択肢の存在」の説明が必要不可欠であると判断した。必要十分な説明がされていない以上、依頼者の形ばかりの承諾には法的に意味がないのである。その論旨は明快で、画期的な判例であると思う。
本件最判は、田原補足意見において、甲が「時効待ち方針」を選択したこと自体が専門家としての裁量の範囲を超えているとの指摘がされているし、奄美ひまわり基金法律事務所という公設法律事務所の弁護士が、なぜこうした執務をするに至ったのか(乙の感じた違和感の内実は何か)という弁護士倫理に関わる問題も包含する。さらに、一審判決と原判決とが結論を異にした要因はどこに求められるかという事実認定論上の問題を考えてみるのにも好個の素材でもある。マルチのアプローチができる(しなければならない)という意味でも、筆者にとって心に残る判例なのである。
◆この記事に関するご意見・ご感想をぜひ、お問い合わせフォームよりお寄せください。
「私の心に残る裁判例」をすべて見る
 加藤新太郎(かとう・しんたろう 弁護士・中央大学法科大学院フェロー)
加藤新太郎(かとう・しんたろう 弁護士・中央大学法科大学院フェロー)1950年生まれ。裁判官、中央大学法科大学院教授を経て現職。著書に、『弁護士役割論〔新版〕』(弘文堂、2000年)、『コモン・ベーシック弁護士倫理』(有斐閣、2006年)、『民事事実認定論』(弘文堂、2014年)、『民事事実認定の技法』(弘文堂、2022年)、『四日目の裁判官』(岩波書店、2024年)など。