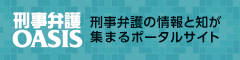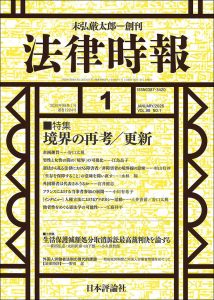外国人労働者法制の現代的課題—育成就労制度と外国人労働者問題をめぐって(野川忍)
 世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。
世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。ぜひ法の世界のダイナミズムを感じてください。
月刊「法律時報」より、毎月掲載。
(毎月下旬更新予定)
◆この記事は「法律時報」98巻1号(2026年1月号)に掲載されているものです。◆
1 90年代以降の政策
(1) 1990年入管法制
日本では第二次大戦後の長期間にわたって、外国人の就労資格を教員やエンターテイナー、コックや通信社の記者などごく限定された分野にのみ認めていたが、1990年に入国管理法(以下、「入管法」)が改正され、いわゆる「外国人労働者」の一定の受け入れに対応するささやかな政策転換が行われた。最も大きな理由の一つは、80年代後半に訪れたバブル時代に、建設業界等の人手不足を背景に中東などからの外国人労働者が多数就労するという事態が発生し、しかもその多くが違法滞在・違法就労であったということから、日本の外国人労働者政策があらためて問い直されることとなったことである。
当時の外国人労働者をめぐる議論は、未熟練労働による作業部門に外国人を受け入れるべきかどうか、というテーマに集約されて、かなりエキセントリックな内容を呈していた。しかし、90年の入管法改正による在留資格の整備やその後のバブル崩壊により、「鎖国か開国か」といった大上段の議論は下火となり、日本政府の公式見解は、「高度な資格・能力を要する職種の労働者は積極的に受け入れるが、いわゆる単純作業への受け入れは慎重に対応する」という内容を維持し続けることとなった1)。他方で、「定住者」という資格による日系人労働者の受け入れが一挙に拡大し、また国際研修協力機構(JITCO)の設立と外国人研修・実習制度の発足による研修生の流入、そして増大する留学生・就学生のアルバイト就労の拡大がみられたことに加え、滞在期限徒過を主たる理由とする一定数の不法就労者の定着という実態により、日本における外国人就労の実態は、「圧倒的多数の単純作業労働者」と、ほとんど拡大しない高度資格・能力労働者という、基本政策とは全く逆の図式が固定化するようになった2)。
(2) さまざまな模索
入管法は、日本の外国人労働力に対する需要の状況に応じていくつかの特例を設け、一定の範囲での就労活動の拡大をはかった。
まず、平成14年に成立した構造改革特別区域法にもとづき認定された特区の一つとして、外国人研究者について入管法の特例措置が認められている。これは、特区と認められた区域内の研究施設で研究活動を行い、かつその成果を利用して事業を経営する活動を行おうとする者にあらかじめ「特定活動」の在留資格を付与し、以後は在留資格の変更や資格外活動の許可を得る必要なく、研究活動と経営活動に専念することができるというものである。最長在留期間も3年から5年に延長された。
さらに、あらかじめ3年を超えて日本で就労することが予定されているIT技術者については、入管法の規制に関わらず、5年の在留期間を認めることとされた。さらに、特定地域において一定の産業の中小企業がまとまって研修生を受け入れる場合に、外国人研修生の受け入れについて人数枠を拡大する措置が取られているし、夜間大学院に通学しつつ週28時間までの資格外就労に従事しようとする留学生にも、「留学」の滞在資格を付与する道も開かれた。
脚注
| 1. | ↑ | 80年代末から90年代初頭にかけての日本の外国人労働者政策については、拙著『外国人労働者法—ドイツの成果と日本の展望』(信山社、1993年)1頁以下を参照。 |
| 2. | ↑ | 当時の法務省入国管理局の統計によれば、平成14年段階で就労ビザによる外国人労働者(すなわち高度な資格・能力に該当する合法就労者)が18万人弱であるのに対し、日系人労働者は23万人強、アルバイトが8万3千人、特定活動(技能実習)が4万6千人、不法残留者は22万人となっている。 |