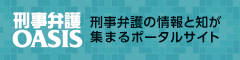(第92回)判例のルールは絶対か?(齋藤由起)
 より速く、より深く、より広く…生きた法である“判例”を届ける法律情報誌「判例時報」。過去に掲載された裁判例の中から、各分野の法律専門家が綴る“心に残る判決”についてのエッセイを連載。
より速く、より深く、より広く…生きた法である“判例”を届ける法律情報誌「判例時報」。過去に掲載された裁判例の中から、各分野の法律専門家が綴る“心に残る判決”についてのエッセイを連載。【判例時報社提供】
(毎月1回掲載予定)
時効援用権喪失・最高裁大法廷判決
一 消滅時効完成後における債務の承認はその時効の完成を知ってしたものと推定することの可否
二 消滅時効完成後における債務の承認と時効援用の許否(最高裁判所昭和41年4月20日大法廷判決)
【判例時報442号12頁掲載】
債務者が、消滅時効が完成した後に「借金を元本だけにしてくれたら、分割で支払います」と申し入れた場合、その後に時効を援用できるのか。本判決は、たとえ債務者が時効完成を知らなかったとしても、完成後に債務を承認した以上、信義則上もう時効を援用できないとした。いわゆる援用権喪失の法理を、最高裁大法廷として定立したものである。
本判決は、援用権喪失の理由を、時効完成後の債務承認と、その後に時効消滅を主張する行為との矛盾に求めている。この場合には、「もう時効は援用されない」と考えた相手方の信頼を保護すべきだというわけである。その結果、時効完成後に債務を承認すれば、完成を知っていれば時効利益の放棄となり、知らなかったとしても信義則により援用権を失う。つまり、いずれにせよ時効は援用できない。
このルールは、時効完成の知・不知で結論が揺れない点で法的安定性が高く、学生時代の私は素直に明快な仕組みだと感じていた。しかし、やがて私は、事態がそれほど単純ではないことを痛感することになる。
研究者として駆け出しのころに、幸運にも「時効研究会」に参加する機会を得た。この研究会では、債権法改正に先立って時効法の改正草案が検討されていた(その成果は、金山直樹編『別冊NBL122号 消滅時効法の現状と改正提言』〔商事法務、2008年〕)。
そこでは、本判決が「時効完成後に債務を承認する債務者は、完成を知らないのが通常である」とする経験則を認めた点をふまえ、そもそも「債権者の時効を援用されないとの信頼は保護に値せず、別の理由があるのではないか」という根本的な問い直しもあった。
債権者の信頼保護を前提とするにしても、どのような行為が債権者の信頼を惹起し、援用権喪失に足るかも簡単ではない。時効完成を知らずに弁済が行われた場合に返還請求を否定することには異論がないとしても、承認だけで援用権を失わせるのは行き過ぎだという意見も強かった。議論を聞きながら、私もその考えに自然と納得させられたものである。
そんなわけで、援用権喪失ルールの明文化をめぐる意見はまとまらず、立法提案も、本案(承認を援用権喪失事由としない案)と代替案(承認を援用権喪失事由とする案)に分かれた。いずれを本案とするかは研究会内の投票で決められたが、その難しさは、その後の法制審議会でも議論の末に条文化が見送られた事実に象徴されている。
振り返ってみると、こうした対立の背後には、時効制度の《不道徳さ》に対する評価や時効観のちがい、さらには債務の存在を承認するという行為の扱いを時効完成の前と後でどこまで近づけるべきかといった点に関する考え方のちがいなどが潜んでいたように思われる。加えて、判例が示した援用権喪失ルールが、ときにルールをよく知る債権者によって悪用されて債務者に思わぬ不利益を及ぼしうるという副作用を、どの程度考慮すべきかという問題も見過ごせない。不当な不利益を惹起する債権者との関係では、援用権喪失を認めることがかえって信義則に反することもあるのではないか(拙稿「判批」『民法判例百選Ⅰ[第9版]』80頁で検討している)。
こうした深度も観点も多様な議論が広がるなかで、これらを止揚することの難しさを学べたことは、私にとって大きな財産である。
このような経験を伝えることこそ、法曹をめざす学生には大切であると感じている。しかし、民法総則の講義で本判決を扱う頃には、時効の援用をめぐる難解な論点が続くため、学生の表情にはすでに疲れがにじむ。ここで本判決の「ルール」をそのまま示せば、授業としてはすっきりまとまるし、講義時間にも限りがある。
こうやって、本判決は、いつも私に考えさせ続けるのである。
◆この記事に関するご意見・ご感想をぜひ、お問い合わせフォームよりお寄せください。
「私の心に残る裁判例」をすべて見る
 齋藤由起(さいとう・ゆき 北海道大学大学院法学研究科教授)
齋藤由起(さいとう・ゆき 北海道大学大学院法学研究科教授)1978年生まれ。小樽商科大学商学部准教授、大阪大学大学院高等司法研究科准教授、法学研究科准教授を経て現職。著書に、『債権総論 第2版』(共著、日本評論社、2023年)、『民法理論の対話と創造』(共著、日本評論社、2018年)など。