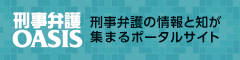(第90回)沖縄から見える法と統治の矛盾—1996年代理署名判決を起点として(徳田博人)
 より速く、より深く、より広く…生きた法である“判例”を届ける法律情報誌「判例時報」。過去に掲載された裁判例の中から、各分野の法律専門家が綴る“心に残る判決”についてのエッセイを連載。
より速く、より深く、より広く…生きた法である“判例”を届ける法律情報誌「判例時報」。過去に掲載された裁判例の中から、各分野の法律専門家が綴る“心に残る判決”についてのエッセイを連載。【判例時報社提供】
(毎月1回掲載予定)
沖縄県知事署名等代行職務執行命令訴訟大法廷判決
沖縄県内の土地を駐留軍の用に供するためにされた使用認定にこれを当然に無効とするような瑕疵があるとはいえないとされた事例ほか
最高裁判所平成8年8月28日大法廷判決
【判例時報1577号26頁】
1996年8月28日、最高裁判所は沖縄県知事に対し、駐留軍用地特措法に基づく署名等代行事務の履行を命じる判決を下した。いわゆる「代理署名裁判」である。この判決は、沖縄の歴史的背景や社会的矛盾を踏まえ、統治と法の関係を地方自治の観点から問い直す視点(問題意識)を提供するものとなり、私の研究の出発点となった。
私はこの訴訟に、市民大学人の会の一員として関わり、沖縄の基地問題に対する司法のあり方や法的課題を考えてきた。地方自治の立場から統治と法の関係を問い直すこの裁判は、私にとって単なる法的判断を超えた意味を持つ。また、近年の辺野古新基地建設をめぐる訴訟にも、辺野古訴訟支援研究会の一員として関与しており、両訴訟の共通性を検討することの重要性を強く感じている。
代理署名最高裁判決の最大の問題点は、裁判所が沖縄の基地の過重負担を肯定し、国の安全保障政策を理由に地方自治体の判断や憲法上の人権保障を後景に追いやった点にある。判決文では「基地負担軽減策が講じられている」「返還交渉が行われている」といった事実が挙げられているが、1951年から1972年の米軍施政下で憲法が沖縄に適用されない期間に、沖縄では基地面積が2倍以上に拡大する一方、本土では6分の1以下にまで縮小され、沖縄に憲法が適用された1972年から1994年にかけても、本土では約59%の減少が進んだのに対し、沖縄県では約15%の減少にとどまった。こうした構造的な基地集中の実態に裁判所は踏み込まず、沖縄の現実を見ようとしなかった。
私は当時、1996年7月10日の最高裁での弁論を傍聴し、大田昌秀知事の意見陳述を直接聞いた。知事は、米軍基地の存在が住民の人権・生活権を侵害する最大の原因であり、行政負担・住民負担を招いている根本的な要因であると述べた。その言葉は、残念ながら現在も沖縄のおかれた現実の重みを語るものであり、基地の存在が日常生活に影を落とし、騒音、事故、土地利用の制限など、あらゆる面で住民の権利を圧迫しているという状況は、今も変わっていない。大田知事の陳述は、今なお沖縄の声を代弁するものであり、司法がその声にどう向き合うかが問われ続けている。
さらに判決は、土地所有者の確認を怠った行政の事実認定(土地・物件調書)の誤りについても違法性を認めなかった。代理署名とは、駐留軍用地特措法および土地収用法に基づき、土地所有者が署名押印を拒否した場合に市町村長が代行し、それを拒否した場合に都道府県知事が代行するという収用裁決手続きの一環である。裁判では、署名対象者の中に実際の所有者であるか確認できない者が含まれていると認定されていたにもかかわらず、知事には代行署名の義務があると判断された。
この判断は、署名等代行事務が「機関委任事務」であるとの前提に立ち、形式的要件が整っていれば記載事項に明白な事実誤認があっても無効とはならないという立場に基づくものである。しかし、土地収用認定およびその後の裁決は、土地の使用権を国に与える行政処分であり、その適法性は処分要件事実の正確な認定に依拠する。すなわち、対象土地の所有者の明確化や使用根拠の厳密な確認は不可欠であり、これを誤れば処分は違法となるべきである。にもかかわらず、最高裁は行政調査に明白な事実誤認があっても、代行署名の執行命令は適法と判断し、形式的手続の履行を優先した。この判断は、憲法29条の財産権保障への配慮を欠き、行政の事実認定の誤りを容認する危うさを含んでいる。同時に、司法の役割—すなわち法治主義の実効性確保—の放棄でもある。
このような司法の姿勢は、辺野古訴訟にも受け継がれている。沖縄県が軟弱地盤に関するB27地点のボーリング調査を求めたにもかかわらず、沖縄防衛局はこれを拒否し、裁判所もその調査不足を問題視しなかった。安全保障政策を理由に、地方自治体の判断や住民の生活権・生存権を覆す構造は、代理署名判決と辺野古判決に共通するものである。司法が政策判断に対して自制的であるべきだという立場もあるが、事実認定や憲法上の権利保障に関しては積極的に関与すべき領域である。
代理署名判決は、司法がその責務を果たさなかった例として、今なお批判的に検討されるべき対象である。私にとってこの判決は、法や地方自治が誰のために、何を守るために存在するのか、そして現状をどう克服するのかを考える出発点であり、今後も問い続けるべき課題である。
◆この記事に関するご意見・ご感想をぜひ、お問い合わせフォームよりお寄せください。
「私の心に残る裁判例」をすべて見る
 徳田博人(とくだ・ひろと 琉球大学教授)
徳田博人(とくだ・ひろと 琉球大学教授)1962年生まれ。琉球大学法文学部助教授を経て現職。
著書に、『辺野古裁判と沖縄の誇りある自治』(共著、自治体研究社、2023年)、『地方自治法と住民 : 判例と政策』(共著、法律文化社、2020年)、『辺野古訴訟と法治主義 : 行政法学からの検証』(共著、日本評論社、2016年)など。