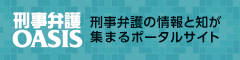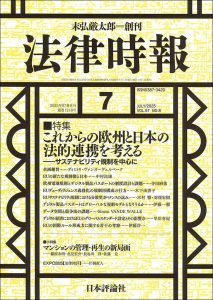(第84回)EUにおける人権・環境DDの義務化と日本企業への影響(野澤大和)
 企業法務、ファイナンス、事業再生、知的財産、危機管理、税務、通商、労働、IT……。さまざまな分野の最前線で活躍する気鋭の弁護士たちが贈る、法律実務家のための研究論文紹介。気鋭の弁護士7名が交代で担当します。
企業法務、ファイナンス、事業再生、知的財産、危機管理、税務、通商、労働、IT……。さまざまな分野の最前線で活躍する気鋭の弁護士たちが贈る、法律実務家のための研究論文紹介。気鋭の弁護士7名が交代で担当します。(毎月中旬更新予定)
木下由香子「EUデューディリジェンス義務化の規制再構成の行方—日本企業への波及と課題と機会」
法律時報97巻8号(2025年7月号)18頁より
近年、EUは脱炭素と経済成長の両立を図るグリーンディールの方針のもと、人権・環境分野における企業責任を強化する新たな規制を相次いで導入している。特に、EU企業サステナビリティ情報開示指令(Corporate Sustainability Reporting Directive)(以下「CSRD」という)やEU企業サステナビリティ・デューディリジェンス指令(Corporate Sustainability Due Diligence Directive)(以下「CSDDD」という)等は企業行動の変容と企業価値向上を通じて、持続可能性を巡る国際的な議論において主導的な立場を確立し、最終的にはグローバル市場における優位性を確保することを意図している。企業に対して人権・環境に関するデューディリジェンス(以下「DD」という)の実施を法的に義務付ける初の包括的立法であるCSDDDは、EU企業以外にも適用される「域外適用」の性質を有しており、連結ベースで閾値を満たす日本企業の親会社も対象となる。
このようなEUの規制動向を受けて、本稿は、EUにおける人権・環境DDの義務化の潮流が日本企業にもたらす影響を明らかにするとともに、企業の視点から具体的な課題と対応の方向性を検討することを目的とするものである。
通常、EU法には見直し条項が設けられており、法令施行後に一定期間を経た後、その実施状況を把握し、ステークホルダーからの意見も取り入れつつ内容の精緻化や制度設計の見直しが進められるのが通例である。しかし、CSDDDは、正式な適用開始を迎える前の段階において、既に包括的な見直し(オムニバスI(Omnibus I)と呼ばれる簡素化パッケージ法案)が進められるという例外的な展開となっている。その背景には、ウクライナ侵攻を契機とするエネルギー価格の高騰をはじめとした欧州の地政学的変更及び欧州主要加盟国の戦略的方向転換とそれに呼応した欧州産業団体からの規制負担に対する懸念と競争力強化を求める声の高まりがあり、それが政策全体の再編圧力として作用し、政治的トップダウンの意思決定の結果としてオムニバスIによる法案簡素化の動きに繋がった。このようにCSDDDは正式適用開始以前において既に制度的再構成を迫られているが、本稿は、それはEU内部におけるガバナンス転換の力学、即ち、規範的志向性と産業競争力の間の緊張関係を如実に示すものであることを指摘する。
次に、本稿は、CSDDDの人権・環境DD義務化に関して最も重要且つ議論の中心となると見られる、①対象企業、②DDの範囲、③民事責任についての修正内容の分析を試みる。①について、CSDDDはその適用対象を「EU企業」と「第三国企業」に分けて定義しているが、域外企業を対象から除外する、あるいは削減するような見直しは現時点で一切されていないため、日本企業を含む域外事業者にとって引き続き注視すべき重要な論点となっている。②について、国際スタンダードに準拠したリスクベースの柔軟なDDアプローチに近づいていたにもかかわらず、オムニバスI法案では、「直接のビジネスパートナー」というEU独自の概念を導入することで再び法文上の範囲の限定を試みていることから、DDの実効性と実務上の実装可能性、更に国際スタンダードとの整合性が再び問われることになる。③について、要件は簡略化され、企業が損害に対して責任を負わない場合を規定する表現や加盟国が特定の条項を国内法に移行する際に、それが他国よりも優先的・強制的に適用されることを確保する義務が削除されている。さらに、民事責任の統一的なEUルールを定めず、各加盟国の判断に委ねるという変更が提案されており、それによってCSDDDの運用と執行における加盟国間の差異が生まれ、法的確実性が失われるという懸念が示されている。
本稿は、以上のようなCSDDDによって企業の行動は大きく変わる一方で、人権・環境DDの法制化によって生じる課題があることを指摘する。第1の課題は、ソフトローの下で「対応の継続的な向上」を目指すプロアクティブなDDが、ハードローによる法制化によってミニマム達成を目指すDDへと変化することである。ソフトローであったDDの実施は、義務化ではなく、本来の目的を共有し、各企業が自らの状況に応じた手法で前向きに取り組むことで、常に基準は高く保たれ、「継続的な改善」へと繋がるプロアクティブなものであったが、DDが法制化されることで企業の取組みは一気に加速したものの、その取組みは「やらねばならぬこと」として形式的な義務履行やリスク回避を優先する「ミニマム・DD」へと変質する傾向が強まることになる。第2の課題は、第三国を含めたサプライチェーン現場の理解・準備状況と、法が求める要件との乖離である。人権や環境へのリスクは、ソフトローの下での取組みを進めてきた先進的企業のオペレーションよりむしろ上流の第三国に存在することが多く、かかるサプライチェーンの現場ではそもそも人権・環境DDの概念自体が浸透しておらず、主体性のない単なるアンケート対応に留まり、企業内の「作業」が増えるだけで人権や環境への潜在的侵害を見つけ出し対処するというDDの本来の目的に結びつかないおそれがある。真の法的義務実装のためにはこのような国々においてもキャパシティビルディングが必要であり、CSDDDの対象企業が存在するEUや日本の政府には調達先の国との政府間対話を通じてそれらの地域においてもDDの理解を深め実施しやすくする環境づくりへの投資が求められる。第3の課題は、DD手法の整合性である。CSDDDは、OECDのDDガイダンスによるリスクベースアプローチに対してオムニバスIによって「直接取引先」等の新たな概念を追加することで一定の制限を加えており、また、欧州紛争鉱物規則等の他のEU法に基づくコモディティ単位でのトレーサビリティの確保が求められるDDと必ずしも内容が一致しているわけではない。そもそも、現実には、世界共通で機密性を担保しつつ互換性を有するサプライチェーン・データ管理システムが存在しない限り、最下流の企業が最上流までの情報を把握することは極めて困難であるとともに、サプライチェーンに内在する構造的な複雑性や情報の非対称性により、リスクを完全に排除することは不可能である。このような限界を踏まえると、人権や環境に対する潜在的あるいは顕在化した負の影響に対処するというDDの本来の目的を達成するためには、情報の信憑性やトレーサビリティの確保に依存するアプローチよりも、企業が有するリスクマネジメント体制が実際に人権や環境リスクに対応しているかを評価する手法の方がより効果的且つ持続可能であり、そのような仕組みを整備することで制度運用の形骸化や国際スタンダードとの乖離を回避することが可能となる。
最後に、本稿は、人権・環境DDを義務化するCSDDDは日本企業を含めて世界の企業行動に影響を及ぼすので、CSDDDの再構築を含意するオムニバスIの議論に、日本からもステークホルダーの一員として積極的に関与し、実務の観点から制度形成に貢献することが求められると指摘する。さらに、国際スタンダードに準拠した共通の目標に向かって、日本と欧州が連携し、CSDDDの適用対象外となる東南アジアなどの国々におけるキャパシティを高め、企業がより実効的なDDを遂行できるような環境の醸成を支援することを通じて、グローバルなサステナビリティの実現に向けた実質的な前進が可能となると提言する。
本稿は、CSDDDによる人権・環境DDの義務化及びその揺り戻しのオムニバスIの議論を通じて、サステナビリティの規制志向と産業競争力の緊張関係を明らかにするとともに、ソフトローによる規制からハードローによる規制に移行した場合に、高い基準の下でのプロアクティブな「継続的な改善」から、コンプライアンスとしてのミニマムな対応に変化してしまう等の課題も鋭く指摘するものであり、日本における人権・環境DDのあり方1)を議論する際にも大いに参考になろう。また、本稿が提言する、EUにおけるCSDDDの再構築を含意するオムニバスIの議論に日本から参加することによる制度形成への貢献や人権・環境DDの国際的なスタンダードの普及に向けた欧州と日本の連携は、人権・環境DDの国際的なルールメイキングにおいて日本政府及び日本企業が果たすべき役割にとって非常に示唆に富む内容である。
本論考を読むには
・法律時報97巻8号 購入ページへ
・TKCローライブラリー(PDFを提供しています。)
◆この記事に関するご意見・ご感想をぜひ、お問い合わせフォームよりお寄せください。
この連載をすべて見る
脚注
| 1. | ↑ | ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月)【PDF】 |
 野澤大和(のざわ・やまと)
野澤大和(のざわ・やまと)2004年東京大学法学部卒業。06年東京大学法科大学院修了。07年弁護士登録。08年西村あさひ法律事務所入所。14年Northwestern University School of Law卒業(LL.M.)。14年~15年Sidley Austin LLP(シカゴオフィス)で研修。15年ニューヨーク州弁護士登録。15年〜17年法務省民事局に出向(会社法担当)。19年西村あさひ法律事務所パートナー。主な書籍・論文として、「『内部統制』の法的位置づけ」ビジネス法務25巻5号(2025年)、『企業法務のリーガル・リサーチ』(共著、有斐閣、2025年)、「定款規定がない場合における買収への対応方針の廃止を求める株主提案の可否」旬刊商事法務2381号(2025年)、「指名委員会等設置会社制度の改善に向けて-」旬刊商事法務2381号(共著、2025年)、『新株発行・自己株処分ハンドブック』(共著、商事法務、2024年)、「自己株式の取得・処分の事例分析-2023年6月~2024年5月」資料版商事法務485号(共著、2024年)、『デジタル株主総会の法的論点と実務』(共著、商事法務、2023年)、『実務問答会社法』(共著、商事法務、2022年)、『令和元年会社法改正と実務対応』(共著、商事法務、2021年)、『M&A法大全〔上〕〔下〕』(共著、商事法務、2019年)ほか多数。