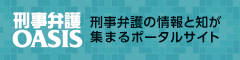(第88回)死刑適用のあり方と対峙した最高裁判所(本庄武)
 より速く、より深く、より広く…生きた法である“判例”を届ける法律情報誌「判例時報」。過去に掲載された裁判例の中から、各分野の法律専門家が綴る“心に残る判決”についてのエッセイを連載。
より速く、より深く、より広く…生きた法である“判例”を届ける法律情報誌「判例時報」。過去に掲載された裁判例の中から、各分野の法律専門家が綴る“心に残る判決”についてのエッセイを連載。【判例時報社提供】
(毎月1回掲載予定)
永山事件最高裁判決
1 死刑選択の許される基準
2 無期懲役を言い渡した控訴審判決が検察官の上告により量刑不当として破棄された事例—連続ピストル射殺魔事件上告審判決最高裁判所昭和58年7月8日第二小法廷判決
【判例時報1099号148頁掲載】
永山事件を巡っては、既に木谷明元判事が、死刑を回避した第1次控訴審判決を本シリーズ第60回で取り上げておられる。ここでは、敢えて、同判決を破棄し、死刑適用基準を定立したことで著名な第1次上告審判決を取り上げてみたい。というのも、この判決が、私が最も繰り返し読んで意味を検討したものだからである。
死刑適用の基準といっても、本判決は9つの情状を考慮して、罪刑均衡・一般予防という2つの観点から「極刑がやむをえない」場合に「死刑選択も許される」とするものである。9つの情状は基準ではなく、考慮事情であるし、「等」とされ網羅的でもない。死刑適用に関係ないはずがない特別予防への言及もない。このようなものは基準足りえないのではないか。私は当初そのように考えていた。
ところが、繰り返し判決を読む中で、本判決は、罪刑均衡・一般予防以外の観点から死刑を適用することは許されず、極刑がやむをえない場合でも、罪刑均衡・一般予防以外の観点から死刑を選択しないことも許される、としていることを理解するに至った。死刑回避の観点に敢えて言及しなかったことも、特別予防以外、例えば、慈悲の観点を入れる余地をも残すためであったと理解することができる。
また本判決は、「ほとんど異論の余地がない程度に極めて情状が悪い」場合にのみ死刑が適用できるとして、死刑適用を抑制することに意を払っている。それにより、下級審裁判所での死刑適用は、2000年前後に一時期積極化したものの、長い目で見ると謙抑化した。また裁判員裁判を念頭に、死刑選択の真のやむをえなさを慎重適用と公平性確保の観点から判断しなければならないとした判例(最二小決平27・2・3判時2256号106頁、最二小決平27・2・3判時2256号111頁)を生み出すに至っている。本判決は確かに規範性を有している。
他方、本判決には、原判決を追認してしまうと、運用上の死刑廃止論になってしまうことを懸念して出された側面がある。それにより、ごく限られた事件に対して概ね年間一桁、近年では年数件の死刑判決が出続ける、という死刑存置の意味を問い直さざるをえない状況が現在まで続いている。
本判決は、当てはめにおいても、被告人の不遇な生育歴と国家、社会の福祉政策の貧困の関係、犯行時18歳以上の少年への死刑適用と少年法51条の関係、獄中結婚を経て被害弁償を行うに至った被告人の変化といった諸点の評価に関して、重要な問題提起を行っている。その含意はまだ検討され尽くされていない、というのが私の見方である。これからも、本判決と向き合っていきたい。
「私の心に残る裁判例」をすべて見る
 本庄武(ほんじょう・たけし 一橋大学教授)
本庄武(ほんじょう・たけし 一橋大学教授)1972年生まれ。一橋大学専任講師、同准教授を経て現職。著書に、『少年に対する刑事処分』(現代人文社、2014年)、『刑事政策学』(共著、日本評論社、2019年)、『ベイシス刑法総論』(編著、八千代出版、2022年)、『ベイシス刑法各論』(編著、八千代出版、2022年)など。