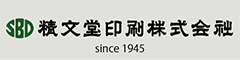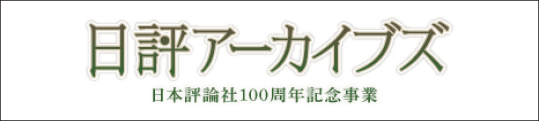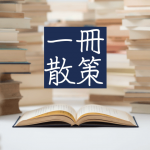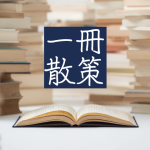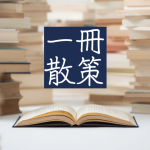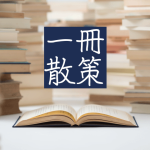『(新版)社会的選択理論への招待—投票と多数決の科学』(著:坂井豊貴)
はじめに
多数決という言葉の響きには,多数派の意見を重視しようという方針が強く認められる.しかし目的と手段が異なる概念であるのと同様に,方針と実現の間にも大きな隔たりは存在する.果たして多数決の結果は多数意見を反映しているのだろうか.この問題はおそらく多くの人々が暮らしの中で感じたことがあり,またどのように考えればよいか適切な思考方法を持たない類のものだ.多数決,およびより広く意思集約というものについて考えるための言語を与えること.それを通じて優れた意思集約の方法を探索し,どのような意思集約がどこまで可能か論理の境界を見極めること.本書が目指すのはそのようなことだ.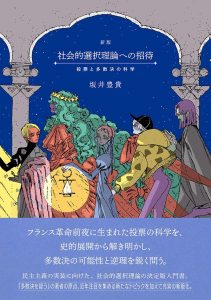
単純に多数決を行うことへの疑義を促す,ひとつの例を挙げてみよう.よく知られている通り,アメリカは二大政党制の国で,4 年に一度行われる大統領選挙では民主党と共和党の候補が接戦を繰り広げる.2000 年の選挙においては,民主党はアル・ゴアを,共和党はジョージ・ W ・ブッシュを候補としており,世論調査を見る限りはゴアが勝利を収めるはずであった.ところが物語はそう単純ではない.ラルフ・ネーダーが第三の候補として参戦を決め,それに伴いゴアに行くはずの票のいくらかがネーダーに流れることになったからだ.結果としてブッシュは史上稀に見る激戦を制し,大統領の座に就くことになった.ブッシュとゴアは多くの政策や政治姿勢において対極的な候補であった.2001 年に同時多発テロ事件が起こったことを考えれば,泡沫候補ネーダーの存在はその後の世界情勢に少なからぬ影響を与えたと言えるだろう.
多数決がこうした「票の割れ」に対して脆弱であること,すなわち本来選ばれるべき選択肢を上手く選び取れないことは,少なくとも 200 年以上前に,パリ王立科学アカデミーの学者ボルダとコンドルセにより鋭く指摘されていた.ボルダとコンドルセは多数決に代わる方法を考案し,それはまた「本来選ばれるべき選択肢」が何であるかについての考察を伴うものであった.歴史的には彼らの研究は,数理分析を用いる社会科学の黎明期の一端を担っている.そしてその「担われた箇所」は現在,社会的選択理論と呼ばれる学問領域を形成している.本書はボルダとコンドルセの議論から地続き的に社会的選択理論を解説する.
ボルダとコンドルセから「地続き的」であることは,単に学問の出発点から現在の研究動向までを紹介する,ということを意味しない.彼らの議論は,今なお社会的選択理論とその関連分野に重大な論点を与えており,それらの理解無しに現在の学問のあり方を適切に把握することはできない.本書は彼らの議論を整理して検討し,現在への学問的影響を意識したうえで,当該分野の重要成果とものの考え方について説明する.社会的選択理論は難解なイメージを持たれることが多いが,学問の黎明期から眺めると,随分と鮮明に現代の学問像を見渡すことができる.こうした学び方は人間の思考の流れに最も自然に沿うものであり,本書を読むのに特段の予備知識は一部を除いて必要ない.それゆえ読者を初学者に想定したうえでタイトルに「招待」と付けた次第である.
新版の刊行にあたって
本書の旧版は 2013 年に刊行され,幸いにも当該分野の標準テキストとしての地位を得た.その後こうして新版を刊行するに至った理由は主に二つある.
一つ目は,旧版刊行時にはまだ注目されていなかったマジョリティ・ジャッジメント (MJ) を加筆したいと考えたことだ.MJ は社会的選択理論家のバリンスキとララキが考案し,2010 年代に分析が進んだ画期的な意志集約の方法である.私は 2019 年に,ALIS というブロックチェーンのコミュニティで MJ を活用するプロジェクトに関わり,その秀逸さを実感した.しかし学びやすい教材が日本語にも英語にもなく,自分で用意しようという気になった.
二つ目は,社会的選択理論の実用先にオンライン店舗で商品を評価するレーティングが加わったことだ.旧版執筆時には,私はそのような実用を漠然と想像するだけで,実行できてはいなかった.しかしその後,私は仲間と共同創業した (株) エコノミクスデザインでレーティング方式の設計を事業化し,実用の経験を重ねてきた.選挙制度の設計を主な考察の対象としてきた社会的選択理論は,いまやオンライン市場に新たな居場所を見付けている.
旧版は時事的なテーマをいくつか扱っていたが,時が経つにつれ古びて見えるものも現れたので,それらの記述は削除した.細かな変化は他にも色々あるが,比較的大きな加筆として,二択の多数決を公理化するメイの定理がある.
おわりに
ある時期の社会的選択理論には「できない」ことを示して誇る文化があった.二項独立性という要求の強烈さを脇に置き,アローの不可能性定理を持ち出しては賢しらに民主主義の困難を語る学者の風潮もあった.若い時分の私はそうした文化や風潮に随分と不満があり,自分はこの学問分野にある「できる」を広めたいと願っていた.そもそも民主主義の困難などは,大層な定理など持ち出さずとも社会や世間を見れば容易に分かりそうなものだ.
それゆえ 2013 年に本書の旧版を書いたときは,不可能性の幻想を振り払い,適切に「できる」を書くよう心掛けた.ボルダとコンドルセの古典から当該分野を見渡す構成をとることが,その作業を可能にしてくれた.彼らは現代よりもはるかに困難な時代に,ひたすらに望ましい集約ルールの構築を追求していた.せめてその叡智と姿勢を引き継ぐ義務が,現代の理論家にはあるように思われた.
新版での最も大きな変化はマジョリティ・ジャッジメントとレーティングの加筆である.マジョリティ・ジャッジメントは中位選択肢に関する「できる」学知を巧みに発展させ作られている.レーティングは自分が事業化を手掛けたが,それも「できる」を示す多くの学知に頼っている.不可能性定理にも意義はあろうが,それ以上に,できる可能性を示す学知の価値は高い.可能性の科学としての社会的選択理論を,読者に伝えられていれば幸いである.
新版の作成においては,旧版と同じく,日本評論社の小西ふき子氏と飯野玲氏の手を煩わせた.新たに加筆した箇所については,慶應義塾大学の大学院生である土井涼雅君から詳しいコメントをいただいた.マジョリティ・ジャッジメントへの私の理解はリダ・ララキ氏と郡山幸雄氏との交流に学恩を負う.記して感謝する.
次の謝辞は,旧版での謝辞を引き継ぐものである.日本評論社の小西ふき子氏,飯野玲氏,吉田桃子氏からは,証明の細部を含む原稿全編に渡り,何百もの有益な指摘をいただいた.小島武仁氏,佐藤伸氏,高宮浩司氏,濱田弘潤氏,東陽一郎氏からは多くの鋭いコメントをいただいた.本書の草稿は慶應義塾大学の研究会で教材として用いたが,そこでは井口蔵人,池邉暢平,稲葉祐太郎,大関一輝,大谷秀平,岡本実哲,大塚美里,岡野真一郎,坂本亮,佐々木政紀,清水優香子,白塚弘眞,内藤豊男らの各君から本稿の改善に直接つながる指摘を頂いた.なかでも河田陽向君からは全編に渡る詳細なコメントを受けた.新版においても,以上の方々にあらためて謝意を表する.
2025 年 1 月
目次
- 序章 本書の案内
- 1 構成
- 2 特徴
- 3 補足
- 第1章 問題の出発点
- 1.1 ボルダルールを巡って
- 1.2 コンドルセの考察を巡って
- 第2章 正しい選択への確率的接近
- 2.1 陪審定理
- 2.2 開票後に多数派の判断が正しい確率
- 2.3 最尤法による「真の順序付け」の探求
- 第3章 ボルダルールの優越性
- 3.1 ボルダルールと他のルール
- 3.2 全員一致までの近さ
- 3.3 ペア比較における平均得票率の最大化
- 3.4 ペア全敗者を選ばない唯一のスコアリングルール
- 第4章 政治と選択
- 4.1 単峰的順序とペア全勝者の存在
- 4.2 実証政治理論と中位投票者定理
- 4.3 中位ルールと戦略的操作
- 4.4 ボルダルールについての補足
- 4.5 オストロゴルスキーとアンスコムのパラドックス
- 4.6 64 パーセント多数決と改憲
- 4.7 ギバード サタスウェイト定理
- 第5章 ペア比較の追求
- 5.1 アローの博士論文
- 5.2 設定
- 5.3 アローの不可能性定理
- 5.4 アローの不可能性定理の証明
- 5.5 満場一致性を用いない不可能性定理
- 5.6 単峰性のもとでの可能性定理
- 5.7 二択の多数決の公理化
- 第6章 社会厚生
- 6.1 社会厚生基準
- 6.2 レーティングへの応用
- 6.3 アローの不可能性定理ふたたび
- 6.4 自由主義のパラドックス
- 第7章 マジョリティ・ジャッジメント
- 7.1 絶対評価の集約
- 7.2 是認投票
- 7.3 マジョリティ・ジャッジメント
書誌情報など
-
-
- 『(新版)社会的選択理論への招待—投票と多数決の科学』
- 著:坂井豊貴
- 紙の書籍
-
定価:税込 2530 円(本体価格 2300 円)
- 発刊年月:2025 年 4 月
- ISBN:978-4-535-55926-4
- 判型:A5 判
- ページ数:176ページ
-
- Amazonで紙の書籍を購入
- 楽天ブックスで購入
- セブンネットショッピングで購入
- hontoで購入
-