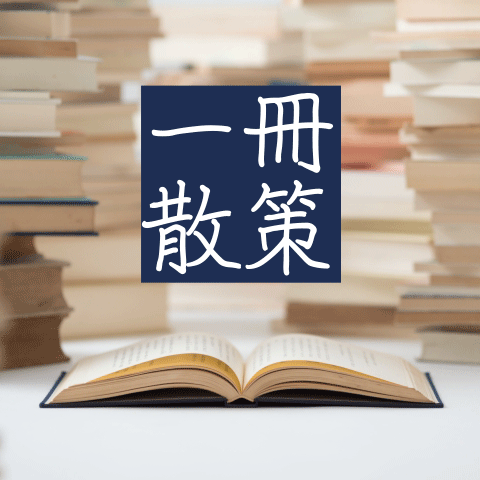『家庭裁判所物語』(著:清永聡)
日本初の女性弁護士、初の女性裁判所長であり、家庭裁判所創設にもかかわった三淵嘉子さん。
彼女の足跡を辿った、清永聡『三淵嘉子と家庭裁判所』の刊行に際して、「はしがき」、「第1章 荒廃からの出発 」の一部を公開します。
はしがき
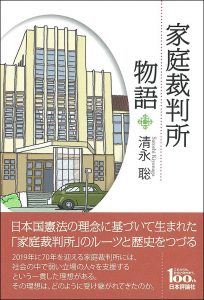 皇居に近い北の丸公園に「国立公文書館」があって、誰でもここで古い歴史文書を見ることができる。
皇居に近い北の丸公園に「国立公文書館」があって、誰でもここで古い歴史文書を見ることができる。
私は以前、取材で3年あまりここに通い、戦争裁判の記録と政府の公文書を閲覧していた。歴史文書を読むと、自分の思い込みや誤った先入観に気づかされることが少なくない。
例えば、敗戦直後の政府は、戦争に負けた衝撃からすっかり虚脱し、しばらく機能停止に陥ったと思っていた。ところが中央官庁の役人たちは、昭和20(1945)年8月15日がすぎると、すぐに戦後の課題処理に向けて動き出している。
「次官会議事項綴」というタイトルの文書がある。敗戦直後の8月22日から9月末までの1か月あまりで、実に27に上る議題を検討し、処理していることが記録されている。
8月24日には「臨時復員対策委員会規程」、8月30日には「外地(樺太含む)及び外国在留邦人引揚者応急援護措置要綱」を決定している。敗戦時、国外にいた日本人は、軍人・軍属と民間人合わせて600万人を超す。これだけの人が、荒廃した日本へ引き揚げてくるのである。準備を急がねばならなかったのだろう。
その後も罹災都市に簡易住宅を造ることや、食糧の輸入を連合国と交渉することなどを、矢継ぎ早に検討している。8月30日には「戦災者越冬対策要綱」もまとまった。まだ8月なのに、もう冬のことを考えている。
残された文書からは、統制や抑圧から解放された官僚たちが、在外邦人の保護や、国内立て直しのため、むしろ生き生きと活動していたことが分かる。
その次官会議。9月20日の議題は、「戦災孤児等対策要綱」だった。
空襲などで両親を亡くした孤児は、12万人と言われる。政府は対策の必要性を、早い時期から認識していたのだろう。要綱には保護の方法として「個人家庭への保護委託」「養子縁組の斡旋」「集団保護」の3つが書かれていた。
では、示された方針は、どの程度実行されたのか。
国立公文書館でさらに文書を探してみた。見つかったのは、「国内処理(引揚児童・戦災孤児)」という、広辞苑ほどの分厚い束だった。
そこには全国の自治体で、孤児を収容する施設を造る計画が書かれていた。当時「集団合宿教育所」と呼ばれている。空襲による被害が大きかった東京や大阪、そして原爆で多くの命が奪われた広島などが対象である。しかし食糧も予算も乏しく、1つの施設で受け入れる孤児の数は、数十人程度だった。文書に書かれた計画段階では、全国の収容予定数は1万5,000人。これでは、孤児全体の1割あまりしかない。
文書には、自治体が別の対応に追われている様子も記されていた。
学童疎開をしていた児童が、敗戦後も農村地帯に数多く取り残されていた。こうした児童を、都市部へと送り帰さなければならなかったのだ。だが、両親の安否が不明な子も多い。実際に自宅が焼失し、両親が死亡していたケースが少なくなかった。本来は疎開先でしばらく保護を続けるべきだろう。
ところが子どもたちは、親の安否が確認されないまま、都市部へと強制的に戻されている。文書からは自治体がただ送還を急ぐ印象を受ける。戻されても、親も家も失った子どもたちには、自立することができない。おそらく多くは、そのまま浮浪児となったのだろう。
その後、昭和23(1948)年9月には「浮浪児根絶緊急対策要綱」が閣議決定された。その文書も残っている。
――浮浪児を根絶できない大なる理由が、人々が浮浪児に対して安価な同情により又は自己の一時的便宜によって、彼らの浮浪生活を可能ならしめていることにあることを、一般社会人に深く認識せしめ「浮浪児に物をやるな」「浮浪児から物を買うな」の運動を強く展開して浮浪児生活存続の温床を絶つこと。
どうしてこのような、冷たい言葉になるのだろう。戦災孤児をまるで野良犬のようなやっかい者とみなしている。3年前に示した保護の方針とは正反対である。
そもそも浮浪児が増え続けたのは、前に作った「戦災孤児対策要綱」が成果を上げないためではないのか。そして、疎開先から無理に都市へと送還したことも、原因の1つであるはずだ。
文書には「浮浪児に対する保護取り締まりを連続反復して徹底的に行うこと」とも書かれている。犯罪者のような扱いだ。また、取り締まっても、子どもたちを保護する場所が足りない。児童福祉法は作られたが、まだ施設の不足は深刻だった。結局、送り先のない孤児たちは、多くが再び路上に戻るしかなかったのである。
だが、翌年の昭和24(1949年)年になると、戦災孤児関連の資料に「家庭裁判所」という言葉がたびたび出てくるようになる。
各省庁の文書には、まるで相談窓口のように「家庭裁判所に連絡」「家裁と協議」と書かれている。そして家裁もまた、戦災孤児、とりわけ浮浪児となった子どもたちの救済へ、積極的に乗り出していく。
家庭裁判所は、新憲法の理念に基づいて生まれた。
昭和24年1月1日にスタートした、新しい裁判所である。その仕事は幅広い。戦災孤児の「保護」や「養子縁組」。さらに、外地から引き揚げ、戸籍をなくした人たちの「就籍」も、戦地で不明になった人の「失踪宣告」も、家庭裁判所の担当だった。日本国憲法が法の下の平等を保障しても、戦争の被害によって、特に女性や子ども、高齢者の権利は損なわれがちだった。家裁は、戦争で傷つけられた弱い人々を救う役割を、担っていたのである。
その家庭裁判所は、2019年で設立から70年を迎える。
社会は大きく変わったが、家庭裁判所には、社会の中で弱い立場の人々を支援するという一貫した理想がある。それは、戦前の伝統的な司法からは、「異端」とも言われた。この「異端」の裁判所は、果たして誰が作り、どのように整備されていったのだろう。そして、設立当時の理想は、時代に沿ってどのように受け継がれ、あるいは変化していったのか。
取材を始めると、そこには「家庭裁判所の父」というべき裁判官がいることが分かった。
強い個性とリーダーシップを持つこの人物は、家庭裁判所と同様に異端の存在であったがため、没後も顕彰されることなく、半ば忘れ去られた存在だった。今回、長く消息が判明しなかった遺族がようやく見つかり、今まで知られていない多くの話を聞くことができた。
それだけではない。彼のまわりには、開戦前年にアメリカの家庭裁判所を視察した“殿様”裁判官や、戦後初めて最高裁に採用された女性裁判官など、司法の理想を託し、あるいは少年や女性の権利を守りたいと願う人々が続々と集まって、家庭裁判所を作り上げていたのである。
第1章 荒廃からの出発
1~8(略)
9 女性法律家第一号
三淵嘉子(当時の姓は和田)は、昭和20年の敗戦を、疎開先の福島県坂下町(現会津坂下町)で迎えている。
もんぺ服にぼさぼさの髪で、慣れない畑仕事をしていた。すぐそばには、まだ2歳の一人息子、芳武が無邪気に遊んでいた。
三淵の弟の武藤泰夫は終戦前、疎開先に姉を訪ねた時の痛々しい思いを、今も覚えている。
――あの、さっそうとしていた姉が、むごいことだ……。
泰夫が「むごい」と感じたのは、三淵が日本で最初に司法科試験に合格した女性弁護士であったからだ。虎ノ門の事務所に所属し、さっそうとしたスーツ姿で働いていた姉の姿とは、あまりに違う。
三淵が暮らしていたのは農家の納屋だった。電気もなく、明かりはランプだったという。兄の妻とその子の4人で、床にむしろを敷いて寝起きしていた。ノミやシラミに悩まされながら、荒れ地を掘り起こしていた。また、農家の手伝いをして、食べ物を分けてもらうこともあった。彼女は、芳武を守ろうと、懸命に生きていた。
泰夫によると、三淵は畑仕事をしながら、よく「戦友」の歌を口ずさんでいたという。「ここは御国を何百里、離れて遠き満州の」という歌詞である。
三淵の夫である芳夫は、この歌のように昭和20年1月に召集され、中国の上海にいた。
三淵の父、武藤貞雄は台湾銀行に勤め、アメリカやシンガポールにも赴任していた。大正3(1914)年に生まれた嘉子の名は、当時暮らしていたシンガポールの漢字に由来する。
東京では両親と麻布の広い邸宅に住み、5人兄弟の長女として活発な女性に育った。丸顔で、左の口もとにできる大きなえくぼがチャームポイントであった。きれいな声で、朗らかに笑う。頭も抜群に良く、明治大学の専門部女子部から法学部へ進んだ。この頃、女性で法学部に入ることができる大学は、明治大学などごくわずかしかなかったのである。
当時、女性が法律を学ぶということは、結婚をあきらめるということを意味していたという。うそのようだが、三淵本人がそう記している。
三淵は、進学のため女学校に卒業証明書をもらいに行った。そこで、女性教師は彼女の進学先を聞いて卒倒せんばかりに驚き、こう言って懸命に止めたという。「法律を勉強なさるのですか。それはおやめになった方がよろしいですよ。お嫁のもらい手がありませんよ」
それでも卒業証明書をもらって家に帰ると、今度は三淵の母がこう言って泣いていた。「これで娘は嫁に行けなくなった」
弟の泰夫も、家の外を歩いていた男子学生たちが、「ここの家、女だてらに法律を勉強してるんだって」と噂しているのを聞いている。三淵本人も、久しぶりに会った知人に近況を報告すると、変わり者という表情で、こわいなあと言われることが多かった。「まるで自分が、日陰者になったかのようだった」と回想している。女性が法学部に進学するというだけでも、大変な時代である。
本人は、それほど思い詰めた動機があったわけではない。泰夫によると、実家は江戸時代から続く丸亀藩の御殿医であったという。父親は娘に医師になってほしいという希望があった。しかし彼女は血を見るのが怖く、医者は無理だと考えて、法律を選んだのだという。
三淵は、感情が豊かな性格だった。喜怒哀楽が明瞭でものごとをはっきりさせる。自然、女性の中では目立ち、リーダーシップを発揮することになった。
彼女自身は、「もし自分が男だったら、黒部ダムでも造ってみたかった」と話している。また、後輩の弁護士には「私は精いっぱい働きたい。死ぬ時は、『ああ、私は精いっぱい生きた』と思って死にたいの」と話している。
いずれも彼女の性格をよく表す言葉である。
昭和13年、三淵嘉子は高等文官試験司法科に中田正子、久米愛とともに合格した。昭和8(1933)年に女性に弁護士の門戸が開かれてから、女性の合格者は初めてであった。
新聞は「初の女弁護士誕生」と、3人を写真付きで大きく取り上げている。全員が明治大学の出身である。総長の鵜沢総明や、女子部委員の穂積重遠、それに女子学生たちが参加して、盛大な祝賀会も開かれている。3人のうち久米が初めて法廷に立った時には、新聞に初弁論ぶりを紹介する、長大な法廷雑感記事が書かれたほどであった。
弁護士試補(修習生)の間は、3人とも丸の内の弁護士事務所に勤め、昼には待ち合わせをして一緒に昼食を楽しむこともあった。
三淵は虎ノ門の弁護士事務所に入り、婦人向け相談会を開く活動もしていた。
また、母校では講師として民法を教えていた。女性弁護士第一号としてマスコミからたびたび取り上げられた三淵は、同じく法律を学ぶ女子学生の人気を集めた。彼女のまわりには、いつも人だかりができている。
しかし、戦争が始まると、国が戦っている中で私的な争いをするのはもってのほか、という声が高まり、特に民事訴訟は減少した。
三淵は昭和16年に、以前自宅で書生をしていた和田芳夫と結婚する。決して「嫁に行けない」ことはなかったのである。芳夫は優しい性格で、三淵とは仲むつまじかった。もっとも、彼女は後に同僚に「男の人っていざというときには意気地がないのね。なかなか結婚しようって言ってくれなかったわ」と話している。
2人は東京・池袋のアパートで生活を始めるが、芳武が産まれると、弁護士は休業状態となった。
三淵の父は台湾銀行から紡績会社の重役を経て、自ら発煙筒や焼夷弾を造る工場を、川崎市の登戸に設立した。麻布の自宅は、空襲による延焼を防ぐため、軍の命令で引き倒された。4人の弟たちは、それぞれ応召したり、大学や旧制高校で下宿したりしていて、両親だけが登戸の工場近くに移り住んだ。
昭和19(1944)年6月に、三淵のすぐ下の弟で長男だった武藤一郎が戦死した。輸送船で沖縄に向かう途中、奄美諸島の南で船が沈没したためだった。泰夫によると、しっかりした性格の一郎は、一家の代表として家族全員が頼りにしていた存在だったという。
続いて昭和20年1月に、夫の芳夫に赤紙が届く。2度目の召集であった。もともと身体の弱かった芳夫は、前回も肋膜炎で召集解除になっていた。戦争はすでに末期で、芳夫は病気が完治していないことを告げることもできないまま、中国へ渡った。芳夫は戦地で発病する。敗戦後、病院船で帰国するが、乗船の時には重病の同僚に付き添うほど元気だったのに、船内で衰弱し、重症になった。自宅に帰ることもできず、港に着いた後、長崎の陸軍病院に移され入院していた。福島の疎開先にいた三淵には何の連絡も届かなかった。
年が明けて、三淵の実家に届いた電報は「芳夫が長崎で危篤」であった。三淵は、夫の復員を知らせる電報だと思い込んでいたため、ひどく驚いたという。芳夫は昭和21年5月に亡くなり、三淵は夫との死に目に会うこともできなかった。
その翌年、今度は母と父が相次ぎ病気で他界する。三淵は1年あまりの間に、すぐ下の弟と夫、そして両親の合計4人を相次いで亡くしたのである。
三淵はしばらく、泣き続けるばかりだったという。
だが彼女は、家族を養わなければならなくなった。
疎開先の福島から帰ったが、実家の工場は、軍需産業だったため操業できなくなった。残されたのは3人の弟と、一人息子の芳武であった。「姉は、今で言う〝とと姉ちゃん〟でしたよ」
泰夫はNHK朝ドラのタイトルをあげた。「私がまだ岡山の六高の学生で、大学に入る前でした。上の兄貴は北大。その上の兄貴は大学を出ていましたが金を稼ぐのが下手でした。まだ幼い芳武君を含めた、全員の生活の面倒を、姉が見なければならなくなったのです。私の学費も、出してくれました。本当に、父親であり母親でもある姉だったのです」三淵はこの頃、明治大学に戻って、民法の講師をしていた。ただ、大学の講師は給料が安かったという。しかも激しいインフレで、三人の弟と一人息子を養うことができない。
これから、どうするか。そう思った時、三淵はある光景を思い出した。
彼女自身の回想によると、それは昭和13年、司法科試験の筆記に合格した後のことであった。おそらく口述試験の控え室で、彼女は司法官試補(裁判官と検察官の修習生にあたる)採用告示の張り紙を見たのだ。
そこには対象者として「日本帝国男児に限る」と明記されていた。女性は弁護士にはなることができても、裁判官や検察官になる資格がなかった。
その紙を見た時の気持ちを、三淵はこう記している。―その告示を読んで、同じ試験に合格しながらなぜ女性が除外されるのかという怒りが猛然と湧き上がってきた。
長い戦争を経て、すでに新憲法が公布されていた。男女平等は明記されている。三淵は息子や弟をどうやって食べさせるかを考えた時、10年近く前に張り紙を見た当時の怒りを思い出したのである。
そして、彼女は裁判官になろうと決意する。
弁護士の試験に合格した時、三淵は自らが法律の力で弱い人の力になり、差別をなくそうと考えていた。だが、司法官試補の告示を見た時、自身もまた、差別された存在だったことに気づいたのである。
それでも戦争は、彼女の不満も否応なく抑え込んだ。三淵は一人息子を育てるため、スーツからもんぺ姿となって福島で荒れ地を耕したのだ。
国に堪え忍ぶことを強制されたにもかかわらず、戦争には敗れ、夫は戦病死し、弟は戦死して、両親も他界した。しかし、国からは一言の詫びもない。それは戦争で家族を失った女性に共通する憤りだが、三淵は自身のキャリアを投げうって耐えてきただけに、怒りが強かったのだろう。
昭和22年3月、彼女は一人で司法省に出向いた。
―男女平等が宣言された以上、女性を裁判官に採用しないはずはない。
三淵はいきなり、裁判官採用願いを書いて、人事課に提出したのである。受け取ったのは当時の司法省人事課長で、後に最高裁長官となる石田和かず外とであった。
司法省も最初は彼女の扱いに苦慮しただろう。新憲法が施行されれば、男性に限定された裁判官の採用規則が憲法に違反することは明白である。ただ、石田も新憲法の施行直前に、女性から就職を直談判されるとは、思っていなかったはずだ。
三淵は昭和22年6月に、司法省民事部に嘱託として採用された。彼女に与えられた仕事は、民法の改正作業の手伝いであった。
彼女は、現場の裁判官になれなかったことに、多少釈然としない思いがあった。それでも、民法の改正作業には、やりがいを感じたという。すでに記したとおり、家制度や家督相続の制度は、法の下の平等や男女平等を定めた新しい憲法に違反する。こうした差別的な制度を、取り除くことが必要だったのである。
民法は憲法の施行までに改正が間に合わず、急きょ、昭和22年5月に10条足らずの応急措置法を制定した。その後翌年に改めて改正を行っている。すでにできていた民法の改正案を読んだ三淵は、「女性が家の鎖から解き放され、自由な人間として、スックと立ち上がったような思いがして、息をのんだものです」と語っている。
民法改正の作業を終えると、三淵は昭和23年1月に、最高裁民事局へ配属された。今度は家事審判法の制定作業に加わっている。
三淵が後に語ったところによると、この頃、最高裁民事局内部の会合で、家庭裁判所の話が出たという。時期ははっきりしないが、おそらくGHQから、少年審判所と家事審判所の統合の話が出た直後、5月のことだと思われる。
GHQの提案を内藤頼博らが最高裁に持ち帰り、最高裁の各部署で意見を交わしたのだろう。ここでは、アメリカに家庭裁判所と呼ばれる裁判所があること、家事部と少年部に分かれて運営されていることなどが説明された。説明を聞いた三淵は、「結構なことだ」と思っている。打ち合わせの場でも、反対する者はおらず、民事局の中では、すんなりと家裁の設立は、賛成する意思でまとまった。
三淵自身は、裁判所に「家庭」の名が付くことが気に入った。
家庭のためにということは、女性のために、子どものために、つまり弱い立場の人たちに役立つ組織が作れるのではないか。自分が最初、女性弁護士としてめざしていた姿が、実現できるのではないかと思ったのである。明治大学で教え子だった一人は、家庭裁判所という新しい組織ができることを、三淵から直接教わっている。彼女は、明るい笑顔でこう言ったという。「家庭裁判所ができたら、きっと、素晴らしい時代が始まるのよ」
目次
はしがき
目次
第1章 荒廃からの出発
1 「家裁の父」帰国する
2 みじめな最高裁
3 家庭裁判所の前身
4 「愉快そうなオジさん」
5 BBSの生みの親
6 アイデアマン
7 殿様判事ニューヨークを観る
8 新少年法と「ファミリー・コート」
9 女性法律家第一号
10 「少年」と「家事」の対立
11 進まない設立準備
12 元旦の家裁発足
第2章 家庭裁判所の船出
1 屋根裏の最高裁家庭局
2 家裁の五性格
3 家裁職員第一期生
4 「高級官吏」調査官
5 二つの雑誌
6 村岡花子と対談
7 戦争被害者のために
8 戦災孤児を救う
9 民間の施設に託す
10 孤児の養子縁組
11 ヒロポン中毒
12 少年審判の心得
第3章 理想の裁判所を求めて
1 日本婦人法律家協会
2 夜に裁判所を開く
3 履行確保
4 建物の苦労
5 GHQとの交渉
6 滝に打たれる
7 日本一の所長さん
8 司法の戦争責任
9 理想の学校
第4章 少年法改正議論
1 多忙な第三課長
2 少年事件の「凶悪化」
3 示された試案
4 「原爆裁判」
5 女性裁判官の代表として
6 少年友の会発足
7 真っ向からの反論
8 長官を怒らせる
9 「首を絞められてじっとはしない」
10 ゴールト判決
11 もう一つの東大裁判
12 宇田川の遺言
第5章 闘う家裁
1 再結集した人々
2 波乱の幕開け
3 長官のバックアップ
4 烈しい応酬
5 場外戦へ
6 「誤算と誤解」
7 水面下の妥協案
8 日弁連の猛反発
9 管理と統制へ
10 「整備点検の時代」
第6章 震災と家裁
1 烈しい揺れ
2 家裁は弱者のために
3 被災者に寄り添う
4 少年事件
5 震災孤児を救う
6 家裁は死なず
あとがき
主要参考文献一覧
書誌情報など
- 清永 聡:著
- 紙の書籍
- 定価:税込 1,944円(本体価格 1,800円)
- 発刊年月:2018年9月
- ISBN:978-4-535-52374-6
- 判型:四六判
- ページ数:284ページ
- 日本評論社で購入
- Amazonで紙の書籍を購入
- 楽天ブックスで購入
- セブンネットショッピングで購入
- hontoで購入
関連書籍
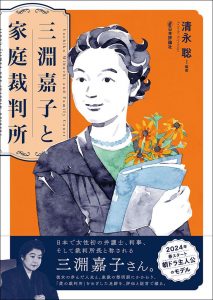 清永 聡 著『三淵嘉子と家庭裁判所』(日本評論社、2023年)
清永 聡 著『三淵嘉子と家庭裁判所』(日本評論社、2023年)
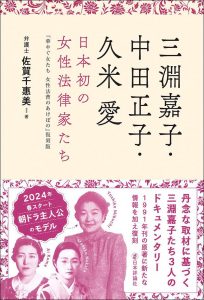 【同時刊行!】
【同時刊行!】
佐賀千惠美 著『三淵嘉子・中田正子・久米愛 日本初の女性法律家たち』(日本評論社、2023年)