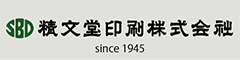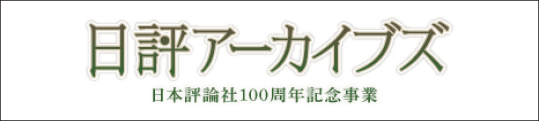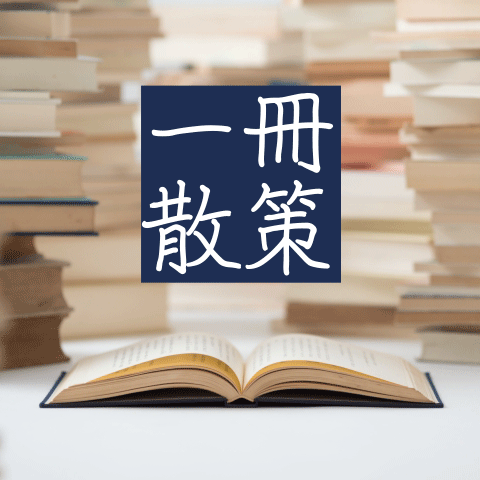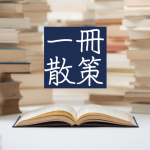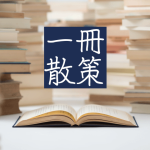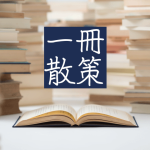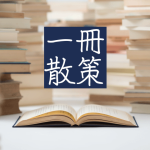『発達障害も愛着障害もこじらせない:もつれをほどくアプローチ』(著:村上伸治)
はしがき
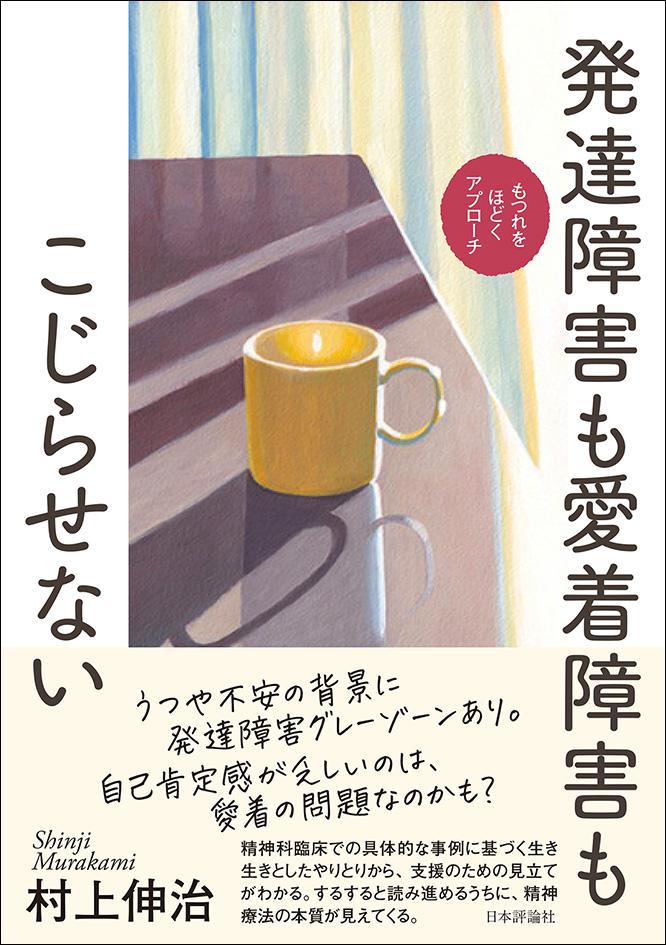 精神科外来で子どもを診ていると、子ども自身の苦しさがわかる一方、親御さんの必死な思いも伝わってくる。みんな子どものために必死である。「不登校を治してほしい」「手首を切るのをやめさせたい」「勉強を頑張ってほしい」「ストレスに負けない強い子になってほしい」など、親は子どもの幸せをいつも願っている。そして親が考える「幸せ」に向かって、子どもを進ませようとする。
精神科外来で子どもを診ていると、子ども自身の苦しさがわかる一方、親御さんの必死な思いも伝わってくる。みんな子どものために必死である。「不登校を治してほしい」「手首を切るのをやめさせたい」「勉強を頑張ってほしい」「ストレスに負けない強い子になってほしい」など、親は子どもの幸せをいつも願っている。そして親が考える「幸せ」に向かって、子どもを進ませようとする。
ただ、子どもには子ども側の事情といきさつがある。例えば、親の期待に応えようとして頑張りすぎ、その結果の疲労として不登校になったのならば、失ったエネルギーが充電されるまで休むだけでなく、親の期待に添うのを拒否したり、大人たちが敷いた高速道路から降りて裏路地で休む必要があるのかもしれない。そのような事情には親は気づかないし、子ども自身も気づいていなかったりする。不登校の状態は、その子が親など周囲が望むような道ではなく、その子らしさを取り戻しながら元気になる過程として、必要なまわり道である可能性がある。だがそれにも、親も本人も気づいていないことが多い。
筆者を含め、大人は子どもの表面的な行動を見て、何とか矯正しようと躍起になる。だが、それがしばしば事態を悪化させる。紐がもつれて団子状態になってしまったら、必要なのは紐のもつれを粘り強くほどく作業である。早急な結果を求めてしびれを切らすと、紐をぐいっと強く引っ張ってしまいやすい。すると団子は強固な塊となり、もつれをほどくことはいよいよ困難になってしまう。そういう事例を診るたびに、筆者は思想家ジャン=ジャック・ルソーの言葉を思い出す。それは、彼が著書『エミール』の冒頭で述べた、「万物をつくる者の手をはなれるときすべてはよいものであるが、人間の手にうつるとすべてが悪くなる」という言葉である。
本書は、筆者の前著『現場から考える精神療法―うつ、統合失調症、そして発達障害』を刊行して以後の筆者の著作をまとめたものである。テーマは精神科臨床全般にわたるので、まとまりがあるとは言えない。だが、これらの著作の根底に流れる筆者の基本姿勢があるとしたら、「こじらせない」ことだと感じたので、これを本書のタイトルに使うことにした。
事例については、本人から承諾を得たうえで改変しているものもあるが、実際の事例に似せて作った創作例も多いので、事例通りの人は実在しないことをお断りしておく。
医学論文とはとても言えない文章ばかりだが、専門家でなくてもわかりやすい文章を心がけてはいるので、寝っ転がってでも読んでいただければ幸いである。
第9章 虐待などない普通の育ちにおける愛着の問題
はじめに
愛着の障害といえば、まずは何と言っても虐待が重要であろう。それはその通りである。ただそうなると、愛着の問題は虐待という特殊な状況でだけ起こることだと考えてしまいやすい。本当にそうであろうか。これが本章の出発点である。本章においては、虐待などない、普通の家庭の普通の育ちの中に、愛着の問題はないのか? ということについて考えてみたい。
[事例]やせ症の女子高校生
高校1年生の女子。思春期やせ症にて筆者の外来に通院している。肥満恐怖はかなり強く、体重30㎏を切った状態が続いた。筆者は「これ以上、体重が減ると入院になるよ」などをやや厳しく言いつつも、「頭としてはやせたいのだと思うが、身体は悲鳴をあげているよ。医者だからわかるけど、身体は助けてほしいと言っている」など、身体の代弁者を努めながら、自分をいたわることを説き続けた。そんな中で、彼女としても、これ以上の体重減少には危機感も抱くようになり、さらに体重を減らしたいとは言わなくなった。だが、体重を増やすことへの抵抗と恐怖感は強かった。自己肯定感を話題にすると、「昔から自分が嫌いだった」と言うので、「こうなったのは、これまでの生き方に何か無理があったのだと思う」と述べ、「何か無理はなかったか?」「何が無理だったのか?」「それはいつからだろうか?」を話題にしていった。
彼女は小さい頃から「お利口さん」で手のかからない子だった。親が叱ったことは数えるほどしかなく、親が叱る前に本人が行動を正すので、叱る必要がなかった。小学校高学年からは学級委員をすることが多かった。「それは大変しんどいことではなかっただろうか?」と筆者が問うと、「えっ、普通でした」と言っていたが、「いつか怒られないか心配していなかったか?」「親や教師が機嫌を損ねないか、気を遣っていなかったか?」などを話し合う中で、「そう言えば、気にはしていたと思う」と教えてくれるようになった。そして、体重がもう少し増えた頃、「いつからか」について、思い出したことがあると言って、次のような話をしてくれた。
愛されていないかも?
小学生の頃のピアノの発表会での話。自分の番となり、小さなミスはあったのだが、何とか演奏を終えた。ミスを怒られると思ってビクビクしていたら、「よかったわよ」と母親は褒めてくれた。その言葉にホッとして胸をなでおろした。けど、手放しでは喜べない気持ちだった。そして、ほかの子の一人は、演奏途中で大きな間違いをして、演奏がいったん止まってしまった。その子はパニックになってしまったようで、すぐには演奏を再開できなかった。しばらくの沈黙が流れたあと、その子は何とか演奏を再開した。何とか演奏を終えたものの、終了と同時にその子は泣きだしてしまった。
それを見た時、もし自分があの子のような失敗をしたら、どうなっただろうか、と心配になった。そして、自分が褒めてもらえているのは、勉強でもピアノでも、そこそこの結果を出しているからであり、もしうまくできなくなったら、自分はダメな子と思われるのではないか、と思った。そう思ったらゾッとしたのだが、それ以上考えるのは怖いので、以後そのことは考えないようにした。それまでもそれなりにやってきていたが、以後はこれまで以上に、決して怒られないようにと思ってやってきたように思う、と話してくれた。
「それは大変な思いをしたのだと思う。人生が変わるくらいの大きな出来事だったのではないか。無理の人生がそこから始まったのかもしれない。よく思い出してくれたね。そして話してくれたね。ありがとう」と礼を述べた。そのうえで、「それは要するに、自分が褒めてもらえるのは、結果を出しているからであり、自分自身が褒められているのではないかもしれない。愛してもらえているのは自分が出した結果であり、つまり自分自身は愛されていないかもしれない、という不安なんじゃないかな?」と返すと、しばらくの沈黙が続き、彼女は涙を浮かべた。そして、「つらかったね。あなたがこんなふうに不安になっていたということは、お母さんは知らないと思うよ。この不安はお母さんに知ってもらったほうがいい。この話をお母さんに伝えてもいいかな?」と尋ねた。彼女はすぐには返事をせず、躊躇した。「お母さんはあなたのことが心配だから、ここに連れてきたんだし、あなたのことを愛していると思う。だから話をしてもわかってくれると思う。お母さんがわかってくれるまで、僕が責任を持って説明する。大丈夫だ。任せてほしい」と述べると、同意してくれた。
ハグしてあげてください
診察室に母親にも入ってもらい、先ほどの話を説明した。「えっ、そんなことを心配していたんですか?」と母親はびっくりした様子だった。
筆者:お母さん、娘さんを愛しておられますよね?
母親:はい。もちろんです。
筆者:本人が出すよい結果だけを愛しているわけではありませんよね?
母親:はい、そうです。
筆者:だけど不幸にも、ふとしたきっかけで、娘さんは誤解をしてしまったんです。誤解を解く必要があります。
母親:はい、わかりました。これまで以上に褒めてあげようと思います。
筆者:褒めることは大切ですが、成果を出した時だけ褒めると、自分自身は愛されていないのではないかと本人は不安になります。なので、成果を出せなかった時、失敗した時こそ、しっかり愛してあげてほしいです。
母親:愛しているって言えばいいですか?
筆者:それもありですが、何だか照れくさいですよね。失敗した時こそ、抱きしめてあげてください。何か言ってもいいし、言わなくていいです。
母親:わかりました。それならできます。失敗しても頑張ったんですから。
筆者:頑張った時も褒めてあげてほしいですが、頑張った時だけ褒めると、頑張れなかったら褒めてもらえないことになります。なので、頑張れなかったとしても、褒めてあげてほしいです。
母親:頑張れない時も?
筆者:そうです。頑張るかどうかは関係ないです。人間、頑張れない時だってあります。そうですねえ、生きていることを褒め、死なずに生きている本人をハグしてあげてください。
母親:わかりました。
この面接のあと、事態は少しずつ動きだした。頑張って食べることができなくて本人が泣きだした時、母親は思わず抱きしめた。それまでは「なぜ食べないの!」と言っていた母親が、初めて娘の本当のつらさがわかる気がしたのだった。そして、2人でしばらく泣いたのだそうだ。それから、やせ願望がなくなったわけではないが、これまでよりは食べることへの恐怖感はいくらか減じた。母親に安心して甘えるようになり、体重も少しずつだが増えていった。
[事例]味方になる
筆者の外来に通っている女性から、小学5年生の娘の不登校について相談を受けた。
患者:車で送ってあげるからと言っても、お腹が痛いと言って泣くんです。どうしたらいいんでしょうか?
筆者:学校に行けなくなったのは何か理由があるんでしょうか?
患者:娘もわからないと言います。どうしたら娘は登校するでしょうか?
筆者:娘さんは苦しんでいるんですよね?
患者:はい、そうです。
筆者:こんな時、一番大事なのは味方です。娘さんに味方はいますか?
患者:味方? 私が味方です。母親ですから。
筆者:そうでしょうか? 「そんなにつらいのね、わかったわ」と言ってあげる味方なのか、それとも、つらい気持ちを理解せず、「何しているの? 学校へ行きなさい!」とプレッシャーをかける側なのか、どちらですか?
患者:えっ、行かなくていいと言うんですか?
筆者:今の娘さんには味方がいないのではないですか? 学校に行かなきゃいけないことは百も承知なのに、どうしても行けない。親の期待を裏切っている。自分はダメな子なのかもしれない。なぜ行けないのか、自分でもわからない。そんな苦しい気持ちをわかってくれる人は誰もいない。母親も。孤立無援ですよね。
患者:……。わかりました。私、娘の味方になります。「つらかったのね」と言ってあげます。先生、ありがとうございました。
2週間後。「あれから、娘といっぱい話をしました。休んでいいよと言ってあげました。そしたら毎日15時間眠って、3日前から少しずつですが学校へ行っています」
この続きは本書でご覧ください!
目次
第Ⅰ部 発達障害をこじらせない
第1章 発達障害と精神療法
[事例]駆逐艦「松」の最期/[事例]国際紛争に興味がある中学生/[事例]新聞を読む小学生/特性+トラウマ累積としてのASD/精神医学と発達障害/発達障害の精神療法が問うもの
第2章 その子に合った育ち支援――普通の子になることを求めることによるこじれ
成人後の療育手帳希望/普通学級でのいじめ/特別支援教育の増加/年齢相応/思考実験/[事例]こじれていない例/子ども臨床の課題
第3章 発達障害の気づきと病識
病識と病感/発達障害における病識/典型的ASDの気づきと病識/大人のASDの場合/実感を伴った診断/与えられる病識/嫌々受診する例/病識を求める問題点
第4章 大人の発達障害への発達障害を前面に出さない支援
グレーな発達障害/病態の説明/得手不得手を話し合う/[事例]急に死にたくなる青年/障害名よりも特性理解/対応の実際
第5章 発達障害の外来診療での工夫
[事例]大学は卒業したけれど……/楽しい予定変更
第6章 自閉スペクトラム症グレーゾーンへの支援
自閉スペクトラム症のグレーゾーンとは/グレーゾーンの多義性/[事例]あとから困る/発達性トラウマ障害/かつて療育を受けていた人/「軽度」は軽度なのか?/発達障害は発達する/頑張らせる?/ASDを知ってもらう/謎解き/相談してもらう/環境調整/指導よりも解説を/助けてもらう/グレーゾーン概念の功罪
第7章 大人の発達障害の診断と支援
広義の適応障害/発達障害診断のジレンマ/あなたは健常者なのか?/あなたも私も発達障害/発達障害診断の難しさ/[事例]職場環境であぶりだされた公務員の男性/グレーゾーン診断/心理検査について/発達障害を疑う症状/統合失調症との鑑別/診断というゼロ百思考/グレー診断の利点/診断の実際/グレー事例の多様性/診断から支援へ/解説者/解説者と指導者/気軽に相談する人になってもらう/助けてもらう人生 vs 戦う人生/[事例]助け合う人生/助け合えば薄まる/凸凹と現代社会/発達障害の位置づけ
コラム1 『窓ぎわのトットちゃん』を読む
第Ⅱ部 愛着障害・トラウマの延焼を防ぐ
第8章 精神科臨床での不登校への対応
身体症状/本人の気持ち/無理の累積としての不登校/原因がわかる不登校/休んでもらう/二次的なこじれ/学校の対応/ゲームやネットについて/雑談を/親が味方に/充電後
第9章 虐待などない普通の育ちにおける愛着の問題
[事例]やせ症の女子高校生/[事例]味方になる/[事例]荒れる幼稚園児/[事例]抜毛症の小学生/愛情は無条件/褒めることが追い詰める/存在を喜ぶ/自分が好きですか?/愛着とは/現代日本と愛着──おわりに代えて
第10章 臨床現場における大人の愛着障害
[事例]自分を大切にできない女性/基本的な安心感/手のかかからぬよい子/自閉スペクトラム症と愛着障害/精神疾患の背景としての愛着障害
第11章 大人の愛着障害とその修復
[事例]情緒不安定な女性/愛着行動/愛着の形成/エジソンと龍馬/愛着の問題/愛着を話し合う/自分を育てる
第12章 トラウマに焦点を当てない治療
[事例]マンガを手放せない男性/考察
第13章 トラウマ関連症状に対する支持的精神療法
[事例]過食嘔吐とアルコール乱用の女性/考察
第14章 精神科日常臨床におけるトラウマへの精神療法
[事例]進級が怖い女子大学生/[事例]夫がストレスの50代女性/ふとした症状/[事例]工事現場で重傷を負った男性/まずは心理教育/トラウマの延焼を防ぐ/自己否定を隔離し、分解して捨てる/[事例]自責的な女性/純粋な自閉スペクトラム症
第15章 トラウマ関連疾患における病気と治療の伝え方
[事例]パニック障害の女性/[事例]適応障害の女性/[事例]摂食障害の女性/[事例]数年ごとに悪化する女性/心理教育/トラウマの延焼を防ぐ
第16章 精神科一般外来での複雑性PTSD診療
複雑性PTSDに気づく/信頼関係/「語ってもらう」/心理教育/延焼モデル/レジリエンスに目を向ける/神田橋に学ぶ養生/薬物療法
コラム2 『エミール』を読む
第Ⅲ部 もつれをほどく精神療法
第17章 統合失調症への精神療法的接近
妄想気分/[事例]警察官に連れてこられた男性/この世界につなぎとめる/気持ちを引き継ぐ/慢性期
第18章 精神療法の副作用と問題点
精神分析と副作用/ロジャーズ派の精神療法と副作用/認知行動療法と副作用/精神療法の副作用の定義/日常診療における精神療法の副作用/副作用に留意した精神療法
第19章 子どもへの薬物療法の留意点
[事例]小学校の問題児?/[事例]うつ病の高校生/[事例]うつ病? の中学生/薬の必要性について
第20章 児童思春期への薬物療法の問題点とプラセボ効果
プラセボとプラセボ効果/プラセボ効果と自然変動/プラセボ効果と期待/臨床試験と治療場面/子どもにおける薬へのイメージ/薬と病識/児童思春期への薬物療法の問題点/親の罪悪感/薬効 vs プラセボ効果/薬を中心とするコミュニケーション/薬物療法の位置づけの説明/プラセボ効果から連鎖反応へ/変化のスターターとしての薬物療法/好循環を保つための薬物療法/服薬の周辺を豊かに/[事例]多動の小学3年生/周囲へのプラセボ効果/母子同服
第21章 医療・保健領域における心理職へのスーパーヴィジョン
ある日のスーパーヴィジョン/コメントしないスーパーヴィジョン/素人スーパーヴィジョン/本人スーパーヴィジョン/ライブスーパーヴィジョン
第22章 山本昌知という精神療法
[事例]要入院? の男性/自宅の電話番号/猟銃を向けられて/教育カンファにて/境界人/精神療法として
あとがき/文献/初出一覧
書誌情報
- 村上 伸治 著
- 紙の書籍/電子書籍
- 定価:税込 2,970円(本体価格 2,700円)
- 発刊年月:2025年6月
- ISBN:978-4-535-98543-8
- 判型:A5判
- ページ数:264ページ
- 日本評論社で紙の書籍を購入
- Amazonで紙の書籍を購入
- 楽天ブックスで紙の書籍を購入
- セブンネットショッピングで紙の書籍を購入
- Amazon Kindle版を購入
同じ著者の書籍
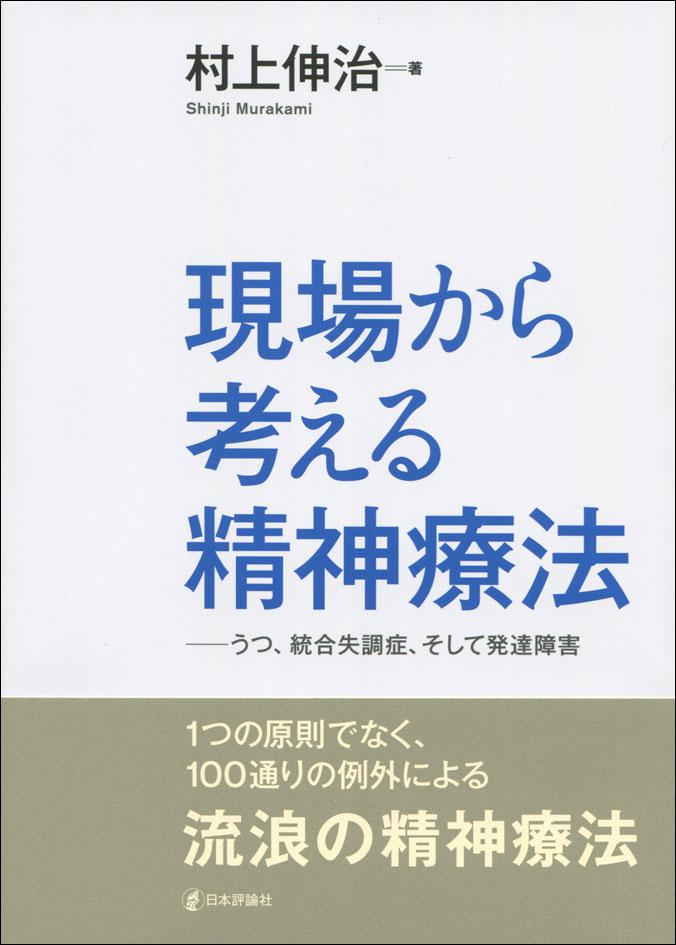 『現場から考える精神療法:うつ、統合失調症、そして発達障害』
『現場から考える精神療法:うつ、統合失調症、そして発達障害』