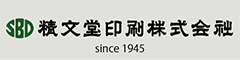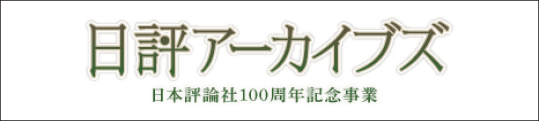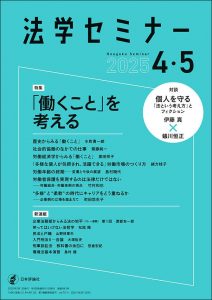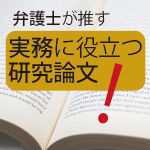(第80回)労働経済学からみる「働くこと」について(松井博昭)
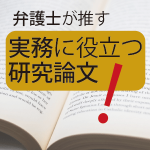 企業法務、ファイナンス、事業再生、知的財産、危機管理、税務、通商、労働、IT……。さまざまな分野の最前線で活躍する気鋭の弁護士たちが贈る、法律実務家のための研究論文紹介。気鋭の弁護士7名が交代で担当します。
企業法務、ファイナンス、事業再生、知的財産、危機管理、税務、通商、労働、IT……。さまざまな分野の最前線で活躍する気鋭の弁護士たちが贈る、法律実務家のための研究論文紹介。気鋭の弁護士7名が交代で担当します。(毎月中旬更新予定)
黒田祥子「労働経済学からみる『働くこと』」
法学セミナー843号(2025年4・5月号)34~39頁
法学セミナー843号「特集『働くこと』を考える」(本特集)は日本の労働環境のこれまでとこれからについて、解説した記事が充実しており、実務家としても興味深く感じる記事が多々含まれている。
その中でも、黒田祥子「労働経済学からみる『働くこと』」(本稿、以下頁数の引用は本稿のものを指す)は、統計を基に労働時間の推移を分析しており参考になる記事である。
本稿によれば、2021年のOECD統計上、日本の年間平均総労働時間は1,607時間とG7諸国中で4番目(1番は米国の1,820時間)となり、この結果のみからは他国と比較した日本人の長時間労働の問題は解消したかに見える。しかし、その背景には、正規社員(フルタイム就業者)の雇用の絞込み及び短時間就業者の増加による年間総労働時間の平均値の押下げが存在し、フルタイム就業者の週当たり労働時間は、日本人の長時間労働が最も顕著であった1980年代以降ほぼ横ばいで推移している(35頁、図1(平均労働時間の推移))。
1987年の(週法定労働時間を48時間から40時間に短縮する等の)労基法改正後、週休2日制が広く普及したが、実際には週当たりの労働時間に変化はなく、単純に就業日1日当たりの労働時間が伸びて行き、2016年時点では、男性の45.8%、女性の22.2%が1日10時間超の労働をしており、男性の17.8%、女性の5.2%が1日12時間超の労働をしている(35~36頁、図2(1日の実労働時間10時間超のフルタイム雇用者割合))。結果、就業日の労働時間の伸びと共に、睡眠時間はここ数十年で大きく減少するところとなり、メンタル疾患等の発生にも寄与していると指摘する。
しかし、本来、景気が悪くなれば減産、経済活動も減少するはずであり、労働時間は減少して然るべきところ、長期的な景気低迷が続いたバブル崩壊以降の30年では、むしろフルタイム雇用者の長時間労働は定着していった。本稿はこの点について、雇用不安により消費が低迷する中で、消費を喚起しようとする企業同士で価格引き下げ競争が激化した結果、モノやサービスが売れず、業績不振から賃金が上がらず、人々が消費を控え、企業は更に低価格と手厚いサービスの提供を求められ、こうした負のサイクルが続くうちに、価格引き下げと長時間労働を伴う過剰なサービス競争が常態化していったと推論する(36~37頁)。
その上で、本稿は近年の働き方改革後の労働時間の推移についても分析している。上記の長時間労働を是正するためになされた2018年の労基法改正は、働き方改革の目玉の一つとして、時間外労働時間に罰則付きの上限規制が設けられた(119条、32条、36条以下)。その後、バブル崩壊以降、30年間ほぼ横ばいであった男性の平均労働時間が2021年において大きく低下しており、(コロナ禍の影響もあり得るが)時間外労働の上限規制に一定の効果が認められたと見受けられる(37頁)。
これにより、週60時間以上の長時間労働者の割合は減少傾向にあるが、反面、週49~59時間で働く人の割合は企業規模が大きくなる程増え、特に大規模企業では2020年から2024年の4年間でほぼ横ばいとなっている(37頁~38頁、図3(2018年労基法改正前後の長時間労働者比率の推移))。
また、1986年時点では20歳台後半が最も長時間労働をしていた年齢層であったが、2006年時点では30歳台後半から40歳台後半にかけての年齢層の労働時間が増加し、2016年時点や2021年時点では30歳台後半の年齢層の労働時間が最も長くなっている(38頁、図4(フルタイム男性雇用者の年齢層別の平均労働時間))。時間外労働の上限規制から、若年層に早帰りを奨励し、管理監督者(労基法41条2号)である層に負担が寄っており、近年の初任給の引上げも相俟って、長時間労働を強いられるのであれば管理職への昇進を望まない若者が増える原因にもなっていると示唆する(38~39頁)。
以上を踏まえて、本稿は、今後、深刻化すると見込まれる人手不足の問題への対応として、働き方の選択肢が増えたり、働く時間や場所が多様化する中、従来のように企業が時間外労働の上限規制を通じて健康管理を行うことには限界もあり、今後は、企業だけでなく、労働者自身が主体的に健康管理を行うことも重大な課題になると結論付けている(39頁)。
本稿は、労働経済学の観点から労働時間の推移を分析した記事であるが、本特集の中には、他にも、緒方桂子「『多様な個人が包摂され、活躍できる』労働市場のつくり方」(40頁)、島村暁代「労働年齢の終期—変遷と今後の展望」(45頁)といった日本の労働環境のこれからについて言及した記事があり、興味深い。
前掲・緒方は2040年の総人口が現在の約9割に減少する一方、労働力人口のうち女性が占める割合が47%、60歳以上が占める割合が31%になるとし、企業は、希望する働き方を選べる職場となり、多様な個人が包摂される魅力的な環境を整え、選ばれる職場になることが重要であると指摘する(40頁)。
前掲・島村は、高年齢者雇用安定法(高年法)上の雇用システムとして、60歳未満の定年の禁止(8条)、65歳までの雇用確保措置の実施義務(9条)、70歳までの就業確保措置の努力義務(10条の2)があり、雇用確保措置として多く利用される継続雇用措置について、契約内容を一新することができるため、事業主には使い勝手が良い反面で労働者側の不満を招きやすいとし、その一方、高年法9条が公法上の規制に留まり、私法的な効力がないこと(最判平成24年11月29日集民242号51頁(津田電気計器事件)、大阪高判平成21年11月27日労判1004号112頁(NTT西日本事件)、東京高判平成22年12月22日判時2126号133頁(NTT東日本事件))等からも(特に契約が成立しない場合)救済にも限界があると指摘する(46~48頁)。その上で、いったん就職したらその企業と一蓮托生の時代は終わり、少しずつ雇用の流動性は高まりつつあり、高齢になってもスムーズに就職先を確保できるよう外部労働市場をより活性化させることも重要になると示唆している(48~49頁)。
厚生労働省「令和6年人口動態統計」では、日本人の年間出生数が68万6061人となって、史上初めて70万人を下回り、死亡数160万5298人の半数に満たない状況となっている。今後、労働力人口が大幅に減少することは避けがたい現実であり、労働法や社会保障法の規制も当然変容を迫られる。本特集や本稿は、雇用統計や働く環境の実態にも踏み込んでいる上、今後の労働環境の変化についての指摘、示唆も多く、実務家としても参考になる記事である。
本論考を読むには
・法学セミナー843号 購入ページへ
・TKCローライブラリー(PDFを提供しています。)
◆この記事に関するご意見・ご感想をぜひ、お問い合わせフォームよりお寄せください。
この連載をすべて見る
 松井博昭(まつい・ひろあき)
松井博昭(まつい・ひろあき)AI-EI法律事務所 パートナー 弁護士(日本・NY州)。信州大学特任教授、日本労働法学会員、日中法律家交流協会理事。早稲田大学、ペンシルベニア大学ロースクール 卒業。
『和文・英文対照モデル就業規則 第3版』(中央経済社、2019年)、『アジア進出・撤退の労務』(中央経済社、2017年)の編著者、『コロナの憲法学』(弘文堂、2021年)、『企業労働法実務相談』(商事法務、2019年)、『働き方改革とこれからの時代の労働法 第2版』(商事法務、2021年)の共著者を担当。