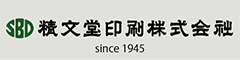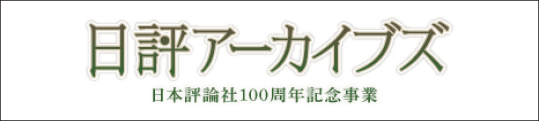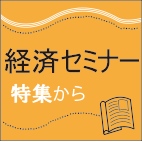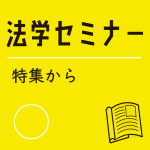AIと知的財産権—「温故知新」と「不易流行」(小島立)
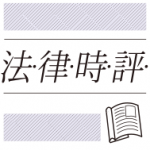 世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。
世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。ぜひ法の世界のダイナミズムを感じてください。
月刊「法律時報」より、毎月掲載。
(毎月下旬更新予定)
◆この記事は「法律時報」97巻5号(2025年5月号)に掲載されているものです。◆
1 はじめに
「コンテンツやモノについてデータから学習し、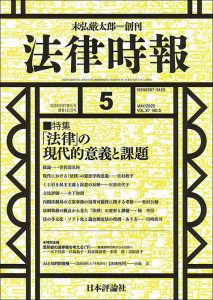 それを使用して創造的かつ現実的な、まったく新しいアウトプットを生み出す機械学習手法」1)である「生成的人工知能(Generative Artificial Intelligence)」または「生成AI(Generative AI)」(以下、「生成AI」という)の発展と普及が目覚ましい。知的財産法は、その保護対象である「発明」(特許法2条1項)や「著作物」(著作権法2条1項1号)などに「人間の創作的な関与」が存在することを前提としてきたが、生成AIが出力するもの(以下、「AI生成物」という)には、人間の創作的な関与が存在しないけれども、人間が作り出したのと見紛う水準のものが存在しており、AI生成物に知的財産法がどう向き合うべきかが喫緊の課題となっている。わが国でも、AIが発明者となりうるかという点に関する裁判例2)に加えて、「AIと知的財産権」3)について一定の方向性を指し示す報告書4)が公表されるとともに、理論的研究5)も蓄積しつつある。
それを使用して創造的かつ現実的な、まったく新しいアウトプットを生み出す機械学習手法」1)である「生成的人工知能(Generative Artificial Intelligence)」または「生成AI(Generative AI)」(以下、「生成AI」という)の発展と普及が目覚ましい。知的財産法は、その保護対象である「発明」(特許法2条1項)や「著作物」(著作権法2条1項1号)などに「人間の創作的な関与」が存在することを前提としてきたが、生成AIが出力するもの(以下、「AI生成物」という)には、人間の創作的な関与が存在しないけれども、人間が作り出したのと見紛う水準のものが存在しており、AI生成物に知的財産法がどう向き合うべきかが喫緊の課題となっている。わが国でも、AIが発明者となりうるかという点に関する裁判例2)に加えて、「AIと知的財産権」3)について一定の方向性を指し示す報告書4)が公表されるとともに、理論的研究5)も蓄積しつつある。
AIと知的財産権に関する国際的な関心の高まりを反映してか、筆者が奉職する九州大学大学院法学府国際コース修士課程(LL.M.)でも、2024年9月と2025年3月に修了した少なくとも5名の学生がこのテーマを取り上げたが、それらの論文の多くは、「AIと知的財産権は『新しい課題』である」という前提で議論を展開していた。筆者は、それらの論文を読みながら、AIと知的財産権という「新しい課題」に「固有の新しさ」は何かということに加えて、この課題を知的財産法の歴史や従来の議論にどのように位置づけるべきだろうかと自問自答してきた。
脚注
| 1. | ↑ | 「AI時代の知的財産権検討会中間取りまとめ」(2024年)【PDF】1頁。 |
| 2. | ↑ | 東京地判令和6年5月16日(令和5年(行ウ)第5001号)[フードコンテナ並びに注意を喚起し誘引する装置及び方法事件]。 |
| 3. | ↑ | 本稿の「知的財産権」には、特許権、著作権などの物権的権利に加え、不正競争防止法によって保護される利益を含む。 |
| 4. | ↑ | AI時代の知的財産権検討会・前掲注1)に加えて、文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(2024年)【PDF】。 |
| 5. | ↑ | 例えば、金子敏哉「生成するAIとせいせいしない著作権法」法学セミナー69巻1号(2024年)51頁、上野達弘=奥邨弘司編著『AIと著作権』(勁草書房、2024年)、谷川和幸「AI時代の創作・享受と著作権法の課題」別冊パテント78巻31号(2025年)15頁【PDF】などに加えて、2024年の著作権法学会のシンポジウム「生成AIと著作権法の現在地」(著作権研究50号〔2025年刊行予定〕に掲載)、ジュリスト1599号(2024年)の特集「AIと著作権—『AIと著作権に関する考え方について』のインパクト」などを参照。 |