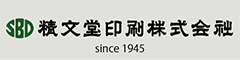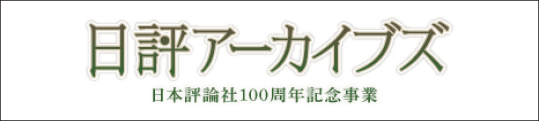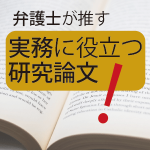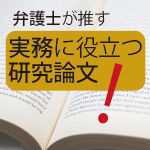(第16回)ワインと真実の親密な関係:in vīnō vēritās/ワインの中に真実がある(第2部)
 格言といえばラテン語, ラテン語といえば格言.
格言といえばラテン語, ラテン語といえば格言. 『オデュッセイア』における「ワインと真実」
前回のエッセー(第15回)では, ホメーロス『オデュッセイア』の英雄オデュッセウスが, パイアーケス人たちの王アルキノオスの宮殿で開かれた宴会の場面において(つまり皆でワインを飲んでいたときに), ある「真実」を検証し, 認定したというお話をしました.
つまり, オデュッセウスはその宴会で, ホメーロスのような英雄叙事詩のパフォーマンスを披露していた盲目の吟誦詩人デーモドコスに対して, 自分自身こそがその真実を誰よりもよく知っていたはずのトロイア戦争の「木馬のはかりごと」のエピソードを歌うようにと促しますが, その吟誦詩人のパフォーマンスを聴き終えたとき, 涙を流して泣いていました. オデュッセウスは詩人の物語の真実を検証し, 自身の涙によってその物語が真実であったことを認定したということになります(『オデュッセイア』8.463-531).
この場面は盲目の吟誦詩人が語る詩(英雄叙事詩)に関する真実の検証であり, 詩の物語を虚偽ではなく真実を語る「歴史」として認定した(私の知る限り)最初の例であり, その真実(vēritās)は, 他でもない宴会(symposion)という, 皆でワインを飲む場において, まさにワインにおいて(in vīnō)検証され, 確かめられたのだと述べました. このように, ホメーロスという西洋古典文学の始まりから, ワインと真実は密接な関係にあるようなのです.
「大嘘つきの英雄」が真実を語る
さて, 実はその同じアルキノオスの宴会の場面において, オデュッセウスは自分自身に関して, もうひとつ別の非常に重要な「真実」を明らかにしていました. というのも, オデュッセウスは自分が他ならぬ「オデュッセウス」であるという「真実」を, アルキノオスと宴会の参加者たちに明らかにしたのでした(『オデュッセイア』9.16-38). 通常であれば, 本当のことなど決して語らない, むしろ「大嘘つきの英雄」であるオデュッセウスが, 宴会というワインを飲む場においては真実を語ったということになりますが, ワインと真実の密接な関係を示唆するという意味で, 特筆に値するエピソードであると言えるでしょう.
自分の真実の名前を明かした直後, オデュッセウスはアルキノオスに促され, 彼自身を主人公とする冒険譚を, 吟誦詩人デーモドコスに代わって, 今度はオデュッセウス自身が物語ることになります (『オデュッセイア』9.39-12.453). 物語の中の物語として構成されたこのオデュッセウスの冒険譚は, カリュプソー, キュプロープス, アイオロス, カリュブディスとスキュラ, キルケー, 冥界訪問, 太陽神の牛の群れといった, 誰もが知っている数々の神話のエピソードを含み, 実に『オデュッセイア』全体の6分の1を占める長大な「劇中劇」となっています. ところが, この冒険譚はその場面に居合わせた誰ひとりとしてその真実を検証できない, 御伽話のような物語でもありました. また, 詩の中に挿入され, 詩の形で歌われた物語ですから, オデュッセウスは冒険譚の主人公であると共に『オデュッセイア』に登場する最大の詩人であるとも言えそうな構造になっているのです.
そもそも, この「詩人」オデュッセウスの冒険譚は真実なのでしょうか? あるいは, 大嘘つきの英雄に相応しく, 壮大な虚構の物語なのでしょうか? 困ったことに, この物語には検証者たる「オデュッセウス」がいません. いずれにせよ, ホメーロスの『オデュッセイア』では, 少なくとも第8歌の途中から第13歌の最初の部分までずっと宴会(symposion)は続いており, その間, アルキノオスとパイアーケス人たちはワインを飲みながら(in vīnō), オデュッセウスが語る(あるいは歌う)物語を楽しんでいたのでした. 少なくとも in vīnō vēritās という状況から推測する限り, オデュッセウスの冒険譚は少なくとも『オデュッセイア』という物語の中では真実であると見なされなければならないのだと思われます.
信州大学人文学部教授。専門は西洋古典学、古代ギリシャ語、ラテン語。
東京大学・青山学院大学非常勤講師。早稲田大学卒業、東京大学修士、フランス国立リモージュ大学博士。
古代ギリシア演劇、特に前5世紀の喜劇詩人アリストパネースに関心を持っています。また、ラテン語の文学言語としての発生と発展の歴史にも関心があり、ヨーロッパ文学の起源を、古代ローマを経て、ホメーロスまで遡って研究しています。著書に、『ラテン語名句小辞典:珠玉の名言名句で味わうラテン語の世界』(研究社、2010年)、『ギリシア喜劇全集 第1巻、第4巻、第8巻、別巻(共著)』(岩波書店、2008-11年)など。