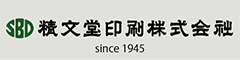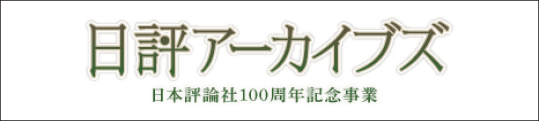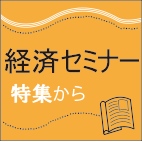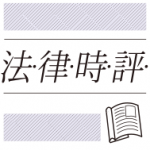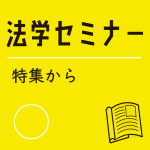リベラリズムが根源的な問いを回避する理由(松尾陽)(連載:笑ってはいけない法哲学 第1回)
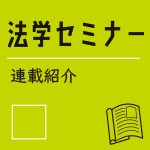 隔月刊「法学セミナー」の連載より、お勧めの回をご紹介します。読んで興味を持たれたら、ぜひ本誌を手に取ってみてください。
隔月刊「法学セミナー」の連載より、お勧めの回をご紹介します。読んで興味を持たれたら、ぜひ本誌を手に取ってみてください。(不定期更新予定)
◆この記事は「法学セミナー」843号(2025年4・5月号)に掲載されているものです。
1 楽しく生きろ―バッテリィズの漫才
年末に決勝戦が開催されるM-1グランプリ。劇場の漫才に比べれば短い4分という制約の中でどれほどネタを詰め込めるのかという競技になっている側面があるものの、それでも繰り広げられる笑いの多様さにはいつも驚かされる。
2024年の大会では、令和ロマンによる圧巻の2連覇があったが、寺家とエースのコンビであるバッテリィズの「偉人の名言」ネタも秀逸であった。彼らのネタは、偉人の名言を参考にしながら善く生きたいと考える寺家がエースにさまざまな名言を紹介し、それに対してエースがツッコミを入れていくという形である。観ていない人もいるだろうから、以下で簡単に内容を説明する。
上方のオーソドックスな漫才であれば、ボケに対してツッコミがなされ、ツッコミで観客の笑いが生じる。バッテリィズの漫才では、エースのツッコミで笑いが生じているものの、しかし、寺家がボケているわけではない。まず冒頭でエースが「アホ」1)であるという前置き(いわゆるフリ)がなされ、寺家が紹介する名言に対してエースが次々とツッコんでいくわけだが、そのツッコミが名言を台無しにする「ボケ」になっているというスタイルである(すぐ後で触れるように、本当にボケといえるかは解釈の余地がある)。
たとえば、「生きるために食べろ、食べるために生きるな」という哲学者ソクラテスの名言2)を寺家が紹介すると、間髪入れずにエースが「食べたい時に食べろ!」というツッコミを入れる。生きることと食べることを違う次元に位置付け、後者に対する前者の優位性を説く名言が、このツッコミにより、食べるタイミングの問題へとズラされてしまう。このズラしは「そんな難しいことを考えず、食べたい時に食べろ!」というメッセージとしても解釈できる。
脚注
| 1. | ↑ | 関西弁における「アホ」は、必ずしも否定的なニュアンスを伴うわけではなく、肯定的なニュアンスを帯びることもある。 |
| 2. | ↑ | この名言がソクラテスによるものか、文献学的な根拠ははっきりとしない。しかし、ソクラテスが言いそうなことではある。 |