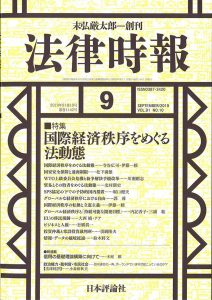政治権力・裁判官・市民社会─欧州連合の一角、ポーランドでいま何が起こっているのか?(小森田秋夫)
 世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。
世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。ぜひ法の世界のダイナミズムを感じてください。
月刊「法律時報」より、毎月掲載。
(毎月下旬更新予定)
◆この記事は「法律時報」91巻10号(2019年月9号)に掲載されているものです。◆
1
5月下旬、欧州連合(EU)構成国で、いっせいに欧州議会議員の選挙が行なわれた。注目されたいわゆる欧州懐疑派の諸政党は、一部の国で伸長したものの、全体としては2割強程度の議席にとどまった。他方、これまでEUにおける意思形成を牽引してきた第1党の欧州人民党(EPP)と第2党の社会主義者=民主主義者進歩同盟(社会民主進歩同盟、S&D)は、合わせても2分の1を割り込む結果となった。このことの帰結は、欧州委員長の人事における波乱となってさっそく現われた。メルケル・ドイツ首相とマクロン・フランス大統領が主導した、S&Dに所属するティムメルマンス前第一副委員長を委員長候補とする案が拒否されたのである。決定的だったのはメルケルのお膝元であるEPPの異論だったとされるが、ポーランドもハンガリーなどとともに強く反対した。その理由は、ティムメルマンスは「中欧諸国のことを理解していない」、ということだった。モラヴィェツキ首相は、ティムメルマンスの委員長就任を阻止したことをポーランドの「勝利」として誇って見せた。どういうことだろうか?
2
ポーランドでは、2015年10月の議会選挙の結果、1989年以来初めての単独政権として、「法と公正〔PiS〕」政府が成立した。PiSは、ポピュリスト政党と規定されることが多いが、ナショナリズムの観点から市場経済を規制する政府の役割を容認する「ソーシャル」な立場とカトリック的価値観を公的生活に浸透させることを重視する保守的立場とを結合した〈国民カトリック〉というイデオロギー的立ち位置にある政党である。PiSは、現行の97年憲法に全面的にとって代わるべき新憲法草案を準備しているものの、同党に同調することの多い1野党を加えても憲法改正に必要な3分の2の議席は持たない。そこで真っ先に着手したのは、絶対多数をもつ国会(下院)の人事権を通じて、政権の意向に忠実な裁判官を憲法法廷(憲法裁判所)に順次送り込むことであった。政権掌握から1年後、PiS選出裁判官が多数派になると、新長官は、裁判体の構成を操作し、ある事件については迅速に判決を下し、別の事件はたなざらしにするというやり方を駆使して、憲法法廷を立法権と執行権の行為を追認し正当化する機能を果たす機関に変質させた。このような状態のもとでPiSは、議会を文字どおり投票機械として扱いながら、違憲の疑いのある法律を次々に成立させている。
いち早く実現した公共放送の掌握とならんで政権が重視したのは、裁判官の統制であった。2017年に実現された「裁判所改革」の帰結は、次のようなものである。
第1に、検事総長を兼ねる司法大臣が新たに獲得した権限を通じて、下級裁判所の所長・副所長の相当数が交替させられ、司法省への出向経験のある者をはじめとして、与党の幹部政治家である司法大臣に忠実と見られる裁判所幹部群が作り出された。
第2に、公募を起点とする裁判官の人事手続において任命権者である大統領に最終候補者を提案するという中核的な位置を占める全国裁判評議会(KRS)が、政権の意向に忠実な機関に変えられた。KRSは、国会議員4名、元老院(上院)議員2名、大統領代表1名、司法大臣、最高裁長官、最高行政裁長官、裁判官の中から選出された15名という構成が憲法によって定められている。裁判官15名は、従来、各級の裁判官集団自身によって所定の手続で選出されてきた。政権は、憲法は「裁判官の中から」選出されると定めているだけで「誰が」選出するかは定めていないとして、これを国会が選出することに改めたのである。その結果、KRSには上記のような裁判所幹部などが送り込まれ、合計25名のKRSは立法権と執行権、つまりは政権党の圧倒的な影響下に置かれるに至った。
そのうえで、第3に、最高裁裁判官の大幅な入れ替えが行なわれた。ポーランドの最高裁は、民事、刑事などの専門部(院)に分かれ、70人を超える裁判官を擁する大陸型の最高裁である。この最高裁で、70歳の退任年齢を65歳に引き下げるという手段によって4割近くの現職裁判官がいっせいに裁判所を去ることを求められ(残留を希望する場合は、その可否が大統領の裁量に委ねられた)、その結果として生まれた空席と増員された定員は、上記のようにして構成されたKRSの審査を経て与党出身の大統領が任命した裁判官たちによって埋められることになった。
第4に、最高裁には、最高裁裁判官を含むすべての裁判官、検察官、弁護士など法曹の懲戒手続の最終審となる懲戒院が新設された。懲戒を発議する権限をもつ裁判官の人事は司法大臣が握り、懲戒院の半数は検察官出身者で埋められるというように、懲戒手続の起点から終点に至るまでの過程に司法大臣が事実上影響力を行使するシステムが整えられた。とくに問題なのは、このシステムのもとで、以上のような裁判所改革を批判する言動だけではなく、個々の判決や後述するEU司法裁判所への申立てのような裁判官としての職権行使の中核的部分についてさえ、司法大臣が問題視する行動をとった裁判官は懲戒の対象となりうるという状況が作り出されていることである。最終的に懲戒処分にまで至ることはないとしても、事情聴取や釈明要求という手段で裁判官を委縮させる効果を生む可能性が生じている。
欧州委員会は、PiS政権が強引な手段で憲法法廷の掌握に着手した当初から、EU条約2条の定める「法の支配」という共通の価値を構成国に遵守させるための同7条の手続をポーランドに適用する構えを見せてきた。しかし、この手続による制裁の発動には全会一致を必要とするため、同様の問題を抱えたハンガリーが反対している状況のもとでは実現困難であった。そこで、欧州委員会は、ポーランド政府とのあいだでぎりぎりの交渉を重ねたうえで、EU運営条約の定める義務違反手続を適用する道に進んだ。この手続による欧州委員会の申立てにもとづき、2019年6月、EU司法裁判所は、退任年齢の引き下げという手段による最高裁裁判官の排除をEU法違反と認める判決を下している。ここまでの道のりを担当者としてリードしてきたのが、ティムメルマンスに他ならない。彼が「中欧諸国のことを理解していない」というのは、最高裁にまだ残っている共産主義時代の裁判官を排除するためという、PiS政権が「裁判所改革」を正当化する理由のひとつとしてあげている事情を指している。しかし、この理由づけには幾重にも合理性が欠けている。さらにEU司法裁判所は、KRSの人事手続や懲戒院についての審理も続けている。申立てを行なったのは、ポーランドの裁判官たちである。
3
いまポーランドでわれわれが目撃しているのは、次のような事態である。
第1に、有権者が民主的選挙によって議会を選び、議会が政府を信任し、主として政府が提出した法案を議事規則に従って審議し、必要があれば修正したうえで採択し、大統領は場合によっては拒否権を行使するか憲法法廷に合憲性の審査を申し立て、やがて有権者は選挙によって政権継続の是非を改めて判断する─このようなシステムが、さまざまな問題がありつつもそれなりに機能しているように思われた国で、政権を握った政治勢力が議会における多数の意思を「主権者」の意思と同一視して絶対化する統治哲学に徹したとき、立法プロセスは驚くほど急速に劣化することが明らかとなった。政権が裁判部門、とりわけ違憲審査制を担う憲法法廷を掌握すれば、その暴走を食い止める制度的担保はほとんど無力となる。多くの論者が指摘するように、制度の陰に隠れていた“政治文化”の質という問題がむき出しになってきた、ということかもしれない。
第2に、裁判官の独立を脅かす「裁判所改革」に対して、議会に働きかけ、裁判官を励ます市民の運動がかつてない規模での盛り上がりを見せた。運動の合言葉となったのは、〈憲法〉である。〈Konstytucja〉と大書されたシャツを着用することが、連帯のシンボルとなった。にもかかわらず、このような市民の立ち上がりが政権を立ち止まらせるには至らなかった。反法治国家的な暴走にもかかわらず、この間PiSは40%前後の支持率を安定的に維持し、欧州議会選挙でも連合した野党に7%近くの差をつけて勝利した。この勝利を秋に予定されている議会選挙につなげ、非リベラルな政権を維持するかなりの蓋然性が存在する。なぜだろうか?
多くの市民にとって、裁判所は縁の薄い存在である。裁判官の独立が脅かされているといわれても、それをわがこととして受け止めるには距離がありすぎる。訴訟遅延や納得のいかない判決など裁判所にあれこれの不満をもっている市民は、それらの病理にもっぱら責任があるのは裁判官の独立という原則によって守られた特権的なエリート集団(「コルポラツィア」)であり、だから裁判所は「民主化」されなければならないと政権から聞かされれば、そのようなポピュリスト的言説を容易に受け入れる可能性もある。これに対して、政権を支持する市民たちが何よりも重視するのは、「ソツィヤル」(ソーシャル)と呼ばれる暮らしに直接かかわる事柄、具体的には政権が公約し実行した子ども手当や追加的年金のような、手に取るようにわかりやすい論点である。法治国家か「ソツィヤル」か─市民社会の意識は引き裂かれている。
第3に、裁判所を立法権と執行権の影響下において「政治化」し、裁判所と裁判官の独立、権力分立の原則を侵害する疑いの濃厚な「改革」に対する約1万の裁判官たちの態度は三分されている。一方には、司法大臣によって新所長に取り立てられたりKRSに選出されたりする者のように、政権による制度の改変を受け入れ、それに乗って地位の上昇を実現している裁判官たちがいる。他方には、さまざまな形で「改革」に異議を申し立てる裁判官たちがいる。その中間には、いずれでもなく、粛々と日々の職務をこなしている多くの裁判官たちがいる。その中で、国の内外に示される裁判官集団の姿勢に主旋律を与えているのは、異議を申し立てる裁判官たちである。
異議申立ての形は、驚くほど多様である。自ら65歳を超える裁判官であるとともに、憲法の明文の規定で6年間の任期を保障されている最高裁長官のように、憲法を直接の根拠に違憲とみなす法律に従うことを拒否する裁判官がいる。具体的な事件処理にかかわる職権行使の枠内で、あるいは「裁判所改革」の手続的不備を問い、あるいはEU司法裁判所の先決裁定を求める申し立てを行なう裁判官たちがいる。裁判官候補者の評価というKRSによる手続への関与の留保を宣言する裁判官組織がある。新所長の権力的な裁判官運営に不信任を表明する現場の裁判官集団がいる…。粛々と職権を行使しているにすぎない裁判官でも、その判決が政権の意に沿わないものであれば、結果として異議申立てという意味を帯びることになる。メディアでの発言や対話を通じて、裁判官が独立であることの意味を市民社会に対して直接に説明することを試みる裁判官たちが現われている。まさにこのように異議申し立てする裁判官が、新たな懲戒手続を用いた威嚇の対象となっている。その多くは、裁判官の約3分の1を組織する任意組織「ユスティチア」の会員である。
第4に、欧州委員会やEU司法裁判所は、構成国裁判所はEU法を適用するかぎりでEUの裁判所として機能するがゆえに、EUは個々の構成国で裁判官の独立などの基本原則が遵守されているかどうかに関心をもたざるを得ないという立場を、ポーランド問題を通じて初めて明確にした。注目すべきなのは、このような進化の前提として、権力分立や裁判官の独立の原則についての共通理解がヨーロッパの裁判官たちのあいだで国家を超えて形成されつつある、ということである。そのことは、欧州評議会の諮問機関であるヴェニス委員会、欧州裁判官諮問評議会、欧州裁判評議会ネットワーク、欧州裁判官協会などいくつもの組織が、ポーランドの状況に懸念を示す意思表明を早くから行なっていることに現われている。ただし、このような“欧州アイデンティティ”がポーランドの裁判官全体にどこまで浸透しているかは、なお問われるべきこととして残されている。
このように書いてきた筆者は、これを「時期尚早に」EU加盟を認められた東欧の「若い民主主義」において起こっている困った問題として、“上から目線”で語る気にはなれない。なぜなら、ポーランドで目撃される事柄のうち、あるものはこの日本でも現に生じており、あるものはかつて経験し、あるものは今は表面化していなくても潜在的に問題が存在しており、あるものは日本には欠落している価値あるものを示している、と思うからである。
(こもりだ・あきお 神奈川大学教授)
「法律時評」をすべて見る
「法律時報」の記事をすべて見る
本記事掲載の号を読むには
・雑誌購入ページへ
・TKCローライブラリーへ(PDFを提供しています。次号刊行後掲載)