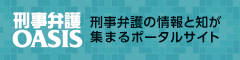(第16回)答弁書の作法(2)
民事弁護スキルアップ講座(中村真)| 2021.09.07
 時代はいまや平成から令和に変わりました。価値観や社会規範の多様化とともに法律家の活躍の場も益々広がりを見せています。その一方で、法律家に求められる役割や業務の外縁が曖昧になってきている気がしてなりません。そんな時代だからこそ、改めて法律家の本来の立ち位置に目を向け、民事弁護活動のスキルアップを図りたい。本コラムは、バランス感覚を研ぎ澄ませながら、民事弁護業務のさまざまなトピックについて肩の力を抜いて書き連ねる新時代の企画です。
時代はいまや平成から令和に変わりました。価値観や社会規範の多様化とともに法律家の活躍の場も益々広がりを見せています。その一方で、法律家に求められる役割や業務の外縁が曖昧になってきている気がしてなりません。そんな時代だからこそ、改めて法律家の本来の立ち位置に目を向け、民事弁護活動のスキルアップを図りたい。本コラムは、バランス感覚を研ぎ澄ませながら、民事弁護業務のさまざまなトピックについて肩の力を抜いて書き連ねる新時代の企画です。(毎月中旬更新予定)
東京オリンピックも終わり、東京パラリンピックも終盤に入りました。今年復活した夏の高校野球では、決勝が智弁学園対決となりましたね。各地で緊急事態宣言が続いていますが、気を緩めず悲観せず、前向きに生きたいものです。
1 答弁書についての話は続く
前回から始まった答弁書の記載について、今回は、予告どおり「請求の趣旨に対する答弁」について取り上げたいと思います。なお、「請求の原因に対する答弁」については、また回を改めて取り上げる予定です。
2 請求の趣旨に対する答弁
当たり前の話ですが、答弁書は原告から提出された訴状に対して、作成・提出されるものです。訴状がないところには答弁書が成立する余地はありません。
そして、この「訴状に対して作成提出される」という答弁書の役割から見た場合、訴状の請求の趣旨に対する答弁が適切な内容になっていることが非常に重要になってきます。
 中村真(なかむら・まこと)
中村真(なかむら・まこと)1977年兵庫県生まれ。2000年神戸大学法学部法律学科卒業。2001年司法試験合格(第56期)。2003年10月弁護士登録。以後、交通損害賠償案件、倒産処理案件その他一般民事事件等を中心に取り扱う傍ら、2018年、中小企業診断士登録。現在、大学院生として研究にも勤しみつつ、その一方で法科大学院の実務家教員として教鞭をとる身である。
著者コメント 予告どおり今回は訴状の請求の趣旨に対する答弁について取り上げました。
附帯請求の日割計算のところで述べたように、4年に一回やってくる閏年というのは利息や遅延損害金の計算上面倒で、全く頭の痛い問題です。これは地球の公転周期が4年よりも若干長いために生じるものですが、私が試しに計算してみたところ、地球を軌道半径平均で内側(太陽側)に約10万2400キロほど押し込むことができれば閏年は消滅することがわかりました。ただそれも現状はなかなか難しいので、答弁書作成の際は、本文に書いたような方法を検討して頂けるとよいのではないかと思います。
次回も、答弁書について取り上げます。