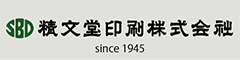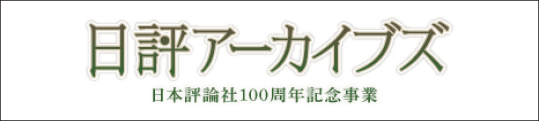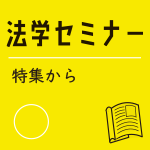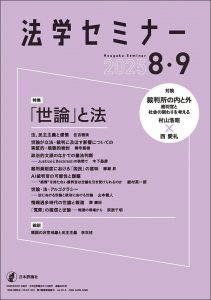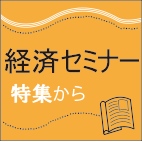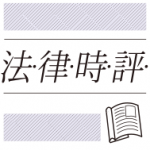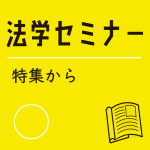世論が立法・裁判に及ぼす影響についての実証的・規範的検討(御幸聖樹)(特集:「世論」と法)
特集から(法学セミナー)| 2025.07.12
◆この記事は「法学セミナー」845号(2025年8・9月号)に掲載されているものです。◆
特集:「世論」と法
法は、「感情」とは一定の距離を持って運用される理性的なものでありつつ、
社会の変化に応じて、常に変革を求められる。
法が「世論」とみなすものはなにか。
「世論」を、法はいったいどのように吸い上げるのか。
そして、法に「世論」は反映されるべきなのだろうか。
立法・法改正、裁判といった場面から検討する。—編集部
1 世論とその表出過程
主権者である国民の意識・意見を知るために、現代の日本では多くの世論調査が実施されている。政党支持率や内閣支持率のような定例のものもあれば、法制度や政策に関わる様々な世論調査(例えば、同性婚を法律で認めるべきか、選択的夫婦別姓制度を導入すべきか、消費税減税に賛成か、女性天皇・女系天皇に賛成か等)が内閣府やマスメディアなどの公的・私的機関によって実施されている。
そもそも、「世論」とは何か。本稿では、「社会的な出来事や問題・争点に関する一般国民の意識・意見の集合体1)」と定義する。ここでの世論は世論調査などによって顕出可能な実証的意味で用いており、「社会通念」のような規範的意味を有する概念とは区別する。また、世論は国民の主観であり、客観的な「社会状況」(例えば、生殖補助医療のような既存の法について法の欠缺をもたらす科学技術の進化などや、単身世帯の増加のような家族形態の変容など2)とは異なる。また、公論に基づく「輿論」とは異なり、世論は理性的討議を前提とするものではない3)。世論は、一時点における事件・事故・災害等によって揺れ動くなど、流動的な性質を有する。また、性別や年齢等の属性によって傾向が異なりうる。
脚注
| 1. | ↑ | 大石裕『メディアの中の政治』(勁草書房、2014年)19頁参照。ただし、同書では「一般市民の」「意見の集合体」とされているが、本稿では「一般国民の」「意識・意見の集合体」とする。 |
| 2. | ↑ | 近時、身分法関係での注目すべき最高裁判例が続出しているところ、その背景として①家族をめぐる社会的変化(1991年時点で立法的対応が検討されていたものの、立法がなされなかったため、課題がそのままとなった)、②科学技術の発展による既存の法の欠缺の発生、③性の多様性への社会的認識の変化等が挙げられる。渡辺千原「『応答的司法観』と立法事実変遷論の展開—ポスト司法制度改革期の最高裁の司法行動に着目して」法学雑誌71巻3・4号(2025年)112、134-135頁。本稿の整理によると、①・②は客観的な社会状況、③は主観的な世論であり、近時の最高裁の姿勢はこれらの要因が複合的に重なっていると説明しうる。 |
| 3. | ↑ | 佐藤卓己『輿論と世論—日本的民意の系譜学』(新潮社、2008年)。 |