(第1回)ラスト・ジェンガ、ファースト・ジェンガ
 外来のバックヤード、あるいは飲み会などフォーマルでない場で、臨床のできる精神科医と話していると、ある共通した認識を備えていると感じることがあります。こうした「プロの精神科医」ならではの「あるある」、言い換えれば教科書には載らないような暗黙知(あるいは逆に認識フレームの罠という場合もあるかもしれません)を臨床風景からあぶり出し、スケッチしていくつもりです。
外来のバックヤード、あるいは飲み会などフォーマルでない場で、臨床のできる精神科医と話していると、ある共通した認識を備えていると感じることがあります。こうした「プロの精神科医」ならではの「あるある」、言い換えれば教科書には載らないような暗黙知(あるいは逆に認識フレームの罠という場合もあるかもしれません)を臨床風景からあぶり出し、スケッチしていくつもりです。(毎月中旬更新予定)
医学部の学生さんに、私の診察に陪席してもらっていたとき、患者さんが退席してから自分の処方を見てもらって、「この処方は精神科でのよい処方のひとつの条件を備えていますが、どの点がそうかわかりますか」とよく尋ねていました。答えは「その処方を見てすぐに病名がわかるような処方」です。たとえば炭酸リチウムという薬なら双極症、ドーパミン遮断剤なら統合失調症、カルバマゼピンなら側頭葉てんかんというように、定型的な第一選択薬がひとつだけ出ている場合は、診たてた病名が当たり、治療が最初からうまくいく事例であることが多いのです。そうした場合は、患者さんやご家族にも、どうしてその薬が出ているのか、きちんと説明ができ、多くは処方する前の予想が当たったことにもなりますから、当面は万事めでたしめでたしということになります。こうした処方は、ある意味とても平凡で、教科書にも書いてあり、きちんと訓練を受けた人であれば、誰にでもできるものですが、処方する側の医師も処方される側の患者さん・ご家族もみんながハッピーになるもので、私たちはこうした処方ができるだけ多くできるよう、まずは訓練を重ねるものだと思います。
七味唐辛子処方
その対極にあるのが七味唐辛子処方と呼ばれている悪名高い精神科処方です。SSRIとか、ベンゾジアゼピン系薬剤、時にはドーパミン遮断剤などがごく少量ずつ色とりどりに並べられており、薬局で売っている総合感冒薬のようなラインナップになっています。精神科のどんな診断もほぼカバーでき、しかも高齢者とか子どもでなければ、まず副作用はでないという、とてもドクター・フレンドリーな処方です。
この処方にだめだしをするのは実は見かけほど簡単ではありません。DSMという精神科で汎用されている診断マニュアルには基本的には確定診断というものがなく、その構造を巧みに利用しているからです。新型コロナウイルス感染症かどうかは、コロナウイルスの存在をPCR検査などで確認すれば確定できますし、心因性発作かてんかん発作かを区別するには、発作のときの脳波をとって判別すればとりあえずOKです。これに対して、DSMでは、いくつかの症状が拾えればそれである、拾えなければそうではないという構造をとっています。症状が揃えばそれとみなし、揃わなければそうではないというだけで、何かを物理的に測定することで判別がつくような答え合わせの基準が載っているわけではありません。つまり、誰かが「症状がマニュアルどおり揃ってるのだから、これでいいんだ」と言い張ったときに、それではないと反論するのが、なかなかに困難であるということになります。
七味唐辛子処方がはびこるのは、もうひとつ、最近ディメンジョン的診断が推奨されていることともかかわりがあるでしょう。ディメンジョン的診断による処方とは、極端にいうと、統合失調症でも気分障害の要素があり、気分障害でも統合失調症の要素もあるのだから、病名の診断(これをカテゴリー的診断といいます)よりも個々の症状を重視し、症状に対して処方をすればよいという考えです。目の前にいる患者さんは気分が落ち込んでいるところがあるので抗うつ薬のSSRI、それに人のことを気にし過ぎるところもあるから関係念慮に効くドーパミン遮断剤も、ちょこっとずつだしてどうして悪いんだ、という理屈がそこから出てくるわけです。もちろん、これは屁理屈であって、DSMやディメンジョン的考えのあるべき作法からすれば誤用と言っていいでしょう。しかし、一時ほどではないにせよ、今でも少なからず見かける処方であることは間違いなく、DSMやディメンジョンに基づく思考の仕方が生んだある種の鬼子として七味唐辛子処方が広まった側面はあるように思います。
ジェンガ的処方
これと似て非なる処方にジェンガ的処方があります。やはり多剤併用となってしまっている点は七味唐辛子処方と同じですが、多くの場合、一つひとつの処方の用量は、七味唐辛子処方と比べるとはるかに多く、少なからず明瞭な副作用が出ていることもあります。この処方の特徴は、以前の主治医がよくならない症状に四苦八苦してついにその処方に至った(至ってしまった)という点にあります。何とかそれで小康状態を保つことができて急場をしのいでいたわけですが、あとを引き継いだ医師からすれば、どの薬をどうさわればよいのか、なかなか難しい判断を迫られることになります。つまり、ブロックゲームのジェンガのように、ブロックが組まれた塔は絶妙のバランスをとって倒れないでいるものの、安全に動かせるブロックはどれか、動かすとタワーのバランスを崩してしまうブロックはどれか、容易に見通せない状態にあるのです。こうした処方のことを、筆者が勤めていた医局ではジェンガ的処方と呼んでいました。
てんかんの処方はジェンガ的処方が生じやすい典型例のひとつです。6~7割のてんかんの患者さんは、最初の1剤か2剤目で発作が止まりますからジェンガ的処方にはもちろんなりません。一方で、3剤目以降となると、おおよそどんな新薬も発作を完全に止めることができる確率は4~6%程度しかありません。そこでさまざまな試行錯誤が行われることになります。外科手術やその他のステップに行けない患者さんの場合、抗てんかん薬の試行錯誤的な足し算引き算が始まり、あるときジェンガ的処方が奏功して、発作が止まることがあるのです。そういった場合には、どの薬がどんなふうに効いて止まったのか、専門医でも容易に見通すことはできません。うつ病や統合失調症でも、セオリーどおりにいかない場合に、たまたまこうした処方が天の配剤のように当たってしまうということが、まれにあります。
精神科専門病院に赴任するとなると、このようなジャンガ的処方に出会うことがあります。こうした処方に出会ったならば、それを検討し、セオリーどおりの処方(つまりエビデンスに基づき、副作用がミニマムで効果が最大であるといわれている処方)に近づけるよう努力することが重要であるのはもちろんです。しかし、エビデンスとは確率の問題であり、何ごとにも例外があるのを私たちは知ることになります。少し手慣れた精神科医ともなると、待ったなしの副作用が出ていると判断した場合を除いて、看護師さんやその他のスタッフとよく話し合い、不測の事態に対するセーフティ・ネットが構築されてから、おもむろに薬剤変更を開始するのがデフォルトです。主治医が七転八倒して最後にたどり着いた処方と最初から七味唐辛子のような処方とでは同じように見えても違うように感じています。前者をラスト・ジェンガ、後者をファースト・ジェンガと呼ぶとすれば、ファースト・ジェンガはほぼ間違いなく悪い処方ですが、ラスト・ジェンガはよりデリケートに取り扱われるべきではないかと思っています。
「背中を見て学ぶ」はまったく無意味になったのか
精神科臨床において、先輩の背中を見て学ぶことは無意味になった、文献を読み込み、それに忠実にしたがえばもっともよい診療ができるという考えはかなり広く広がっています。エビデンスの時代が来る前、たしかに自分の狭い経験を絶対のように思い込み、実際には敷衍可能性がどの程度あるのかが怪しい2~3例での自分の経験を、あたかも絶対的な法則であるかのごとく後輩に伝授する悪い慣習がなかったとは言えないでしょう。そうした前時代的な「教育」への反発が、「医局において学ぶものはない」「できるだけ早く開業するほうが、精神科医人生のコスパがよい」という考えのひとつの根拠となったことは否定できないと思います。
しかし、臨床教育における模倣は、シャドウィング(shadowing)と呼ばれ、最も高価で手間はかかるが必須のプロセスとして多くの職業教育では仕上げの段階で実践されています。それにかかる人的コストを軽減するために、フランスではロール・プレイなどを含めたシミュラシオン(simulation)の手法がさまざまに工夫されつつあるそうです。フランスの精神医学教育の責任者の1人であるストラスブルク大学のヴィダイエ教授によって先日行われた特別講義によれば、フランスでは陪席が諸般の事情で難しくなっているため、このシミュラシオンという手法を洗練させることが避けては通れない精神科医の養成のプロセスのひとつとして考えられているとのことでした。
座学で十分に学ぶことが最終的なシャドウィングを実りあるものとするための必要条件であることは間違いありません。問題は、先輩の背中を見ることが意味のないものだと断じてよいのかどうかです(少なくともフランスではそうではないようです)。論文によるエビデンスの取得は、座学以外のなにものでもないでしょう。特に若くして開業してしまえば、そこは、その先生に歯向かうものがいないキングダムのようなものです。しばしばとまでは言いませんが、自分の認知行動療法でほとんどの患者さんがよくなるといったことを書いていらっしゃるWEBサイトに遭遇することがあります。自分とは別の見方で世界が見えている人もいて、それは自分には理解できないけれど、自分には理解できないことが必ずしも価値のないことだとも間違ったことだとも限らないという感覚は、精神科医がどうしても持っていなければならない最低限の心得だと思うのですが、自分の流儀の判断が唯一の正しい判断の仕方で、それ以外は間違っているといわんばかりのWEBサイトに遭遇して驚くこともあります。もちろん、これは客寄せのためのただの宣伝で、本当はそう思っていらっしゃらないのかもしれませんが。
高校生の終わりから6~7年フォローして、私が統合失調症だと思って治療していた方がいらっしゃいました。初診のとき、おそらくは破瓜型、成績の低下などから推察するに、発病後1~2年は経過しているのではないかという印象で、若干の関係念慮もあり、緊迫感もあって、今にも発病しそうな雰囲気があったので、ドーパミン遮断剤を処方し、何とか再発せずに大学を卒業されました。しかし、卒業後は、営業職につきたいとおっしゃっていて、ちょっと人にもまれる仕事は難しいのではないかと内心思いながら、結論を出さずにゆるゆると、どうしようかを付き添いのご両親とも一緒に考えるという外来を続けていました。ところが私の煮え切れない態度に業を煮やしたご本人が広告で見たクリニックにセカンド・オピニオンを聞きに行きたいと言われ、言われるがまま紹介状を書いたところ、紹介先の先生が「今の主治医の先生は、誤診をしているよ。君は社交不安障害です。今の薬ではだめだ。すぐにもっとちゃんとした病院に行ってきちんとした診断をつけてもらいなさい。主治医の先生にもう一度、この地域で有名な〇〇大への紹介状を書いてもらうといい」と勧められて戻ってきました。
それから紆余曲折があって、結局彼は私のもとを離れます。病院の苦情係には、私に余分な薬を飲まされたと苦情の電話をかけてこられたようでした。
そんなことがあってから半年後、突然、とある精神病院から電話がありました。「先生が長年診てらっしゃった△△君が、今、私の病院に急性の幻覚妄想状態で入院しているのですが、ドーパミン遮断剤をいくら使ってもまったく幻覚妄想がおさまらず困っています。先生のところでは長年落ち着いていたようなのでどんな薬剤を使ってらっしゃったのか教えてもらおうと思って電話させてもらいました」との連絡です。私が使っていた薬剤名と用量をお答えすると、「その程度の薬でその量で症状が出ていなかったんですか……」と絶句されました。
ラスト・ジェンガに唾を吐く前に
私自身は、自分の診断がある確率で必ず間違うことをいつも意識しようと思っています。エビデンスとは確率ですから、一定の確率で、エビデンスどおりにならないことが起こりうるのは当然です。エビデンスは臨床上の座標軸のようなもので、それがなければ臨床という航海に漕ぎ出すことはできませんが、座標軸だけを知っていれば航海ができるというものでもないでしょう。現に私自身、何度も忸怩たる難破をしてきました。
△△君に関しては、結果から見ればおそらく私の診たてのほうが正しかった可能性が高く、紹介先の先生は結果として△△君の人生をかなりの程度破壊したのも間違いないと思われます。もちろん、これは結果論であって、私のほうが間違っていた可能性も当然あるでしょう。ただ、結果から見るに、操作的基準を杓子定規に拾って大言壮語した紹介先の医師のあれだけの自信にはなんら根拠がなかったということです。
操作的基準に当てはまっていれば、たしかにそれは誤診ではないのでしょう。破瓜型の統合失調症は操作的基準では、統合失調症にならないこともあります。「こちらはちゃんと操作的基準に従って診断したんだから、責められるべき筋合いはない」と言われればそれはそうなのかもしれません。しかし、結果として、紹介先の先生は△△君の人生に大きなマイナスを与えました。
ラスト・ジェンガに唾を吐く前に、自分が本当に井の中の蛙ではないか、私自身は少なくとも自問自答したいと思っています。たくさんの失敗をしたからこそ思うことなのかもしれませんが。
◆この記事に関するご意見・ご感想をぜひ、web-nippyo-contact■nippyo.co.jp(■を@に変更してください)までお寄せください。
この連載をすべて見る
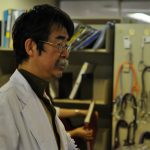 兼本浩祐(かねもと・こうすけ)
兼本浩祐(かねもと・こうすけ)中部PNESリサーチセンター所長。愛知医科大学精神神経科前教授。京都大学医学部卒業。専門は精神病理学、臨床てんかん学。『てんかん学ハンドブック』第4版、『精神科医はそのときどう考えるか』(共に医学書院)、『普通という異常』(講談社現代新書)など著書多数。




