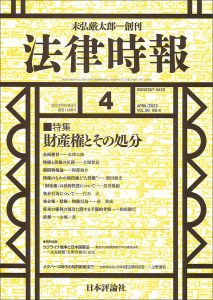メタバース時代の知的財産法?ーー生鮮食料品と求道者(上野達弘)
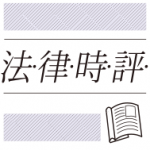 世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。
世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。ぜひ法の世界のダイナミズムを感じてください。
月刊「法律時報」より、毎月掲載。
(毎月下旬更新予定)
◆この記事は「法律時報」95巻4号(2023年4月号)に掲載されているものです。◆
1 流行としての「メタバース」
周知のように、「メタバース」が世間を賑わしている。定義については諸説あるが、メタバースとは、多数人が同時にアクセス可能な三次元のオンライン仮想空間を意味すると考えてよかろう。読者の中にも、VRヘッドセットまで持っている強者は稀だとしても、何らかのメタバース経験を有する方も少なくなかろう。
そんなメタバースをめぐって、実に様々な法律問題が生じている。仮想空間内におけるアイテム取引に関する問題や、NFT(非代替性トークン)を活用した仮想オブジェクトの「所有」に関する問題、あるいは、いわゆるアバター(仮想空間における自己の分身となるキャラクター)に対する誹謗中傷等の権利侵害問題など、それは枚挙に暇がない。
知的財産法も例外ではない。現実空間の街を仮想空間に再現する際の著作権や商標権の問題、現実世界のデザインを仮想世界のアイテムに用いる場合の著作権や意匠権の問題、アバターの肖像権・パブリシティ権に関する問題など、これも枚挙に暇がない。そのため、2022年11月には、内閣府の知的財産戦略本部に「メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議」が設置され、3つの分科会において多面的な検討が行われている。また、民間の動きも盛んであり、例えば、一般社団法人日本デジタル空間経済連盟がデジタル空間経済の発展に向けた課題やニーズの意見集約等を行っており、特に知的財産法上の課題は2022年11月の報告書においても1つの柱になっている1)。こうした議論を受けて、早くも立法論が展開され、2023年通常国会においても、現実世界における商品形態の保護を仮想空間にも及ぼすための不正競争防止法の改正法案が審議される予定である。学界においても、2023年度の著作権法学会(2023年5月27日)において「メタバースにおける著作権」をテーマとするシンポジウムが行われることになっている。
筆者自身、メタバースと知的財産法について講演や座談会に携わったり2)、小稿を認めたりしている3)。本稿の執筆依頼も、その流れで筆者に到達したものと推察される。
2 “生鮮食料品”的な研究?
ところが、かくいう筆者も、実は最近までメタバースについて何も知らなかった。2021年10月、とある懇親会の場でロースクールの元教え子でもある弁護士が「最近はメタバースの仕事をしています」と挨拶していたのを聞いて、あとで「メタバースって何?」と尋ねたのは他ならぬ筆者なのである。
とはいえ、「昔のセカンドライフみたいなものです」という彼の一言だけで、おおむね状況を理解できたのは、2000年代に大ブームとなったセカンドライフを試した経験のおかげなのであるが、他方で、あの頃、「セカンドライフにおける○○法上の課題」などと題する議論が世間を賑わしている様子を、かなり冷ややかに眺めていた筆者には、その後、すぐにセカンドライフが廃れるに伴って、これに関する研究成果が瞬時に意味を喪失したように感じられた経験もあっただけに、現代のメタバースとやらも同種のものに見えたかも知れなかったのである。
そういえば、セカンドライフが流行した2000年代、たしか大阪で情報法関係の会食のようなものがあり、当時すでに著名だったある弁護士の先生が、「俺たちの論文は生鮮食料品みたいなものだからな」とおっしゃっていたことが、今でも強く印象に残っている。あっという間に賞味期限は過ぎてしまうかも知れないが、鮮度の高い研究をリアルタイムに提供することの意義ないし自負を示されたものと理解した。たしかに、少なくとも実務上そのような研究は必要とされていると言えよう。
しかし、当時の筆者は30代で、それなりに研究者としての理想を持っていたのであろうか、やはり研究者としては、50年たっても読まれる古典のようなものを残すべきという(おそらくは分不相応な)意気込みを持っていたため、すぐに意味がなくなってしまう生鮮食料品的な研究などというのは、むしろ理想の対極にあるダークサイドへの入口のように感じてしまったのも事実である。
脚注
| 1. | ↑ | 一般社団法人日本デジタル空間経済連盟「デジタル空間の経済発展に向けた報告書」(2022年11月16日)6頁以下参照。 |
| 2. | ↑ | 小塚荘一郎=石井夏生利=上野達弘=中崎尚=茂木信二「〔連続座談会〕新技術と法の未来――第1回仮想空間ビジネス」ジュリスト1568号(2022年)62頁。 |
| 3. | ↑ | 上野達弘「メタバースをめぐる知的財産法上の課題」Nextcom52号(2022年)4頁。 |