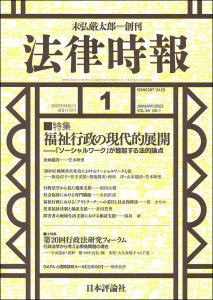GAFAと国際課税ルール(増井良啓)
 世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。
世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。ぜひ法の世界のダイナミズムを感じてください。
月刊「法律時報」より、毎月掲載。
(毎月下旬更新予定)
◆この記事は「法律時報」94巻1号(2022年1月号)に掲載されているものです。◆
1 2021年の妥協
2021年は国際課税ルールの見直しが進んだ年であった。米国の政権交替とともに、経済のデジタル化への対応をめぐって国際交渉が加速した。7月のG20財務相・中央銀行総裁会議では、解決策の大枠が合意された。そして10月には、140(現在は141)の国・地域が参加する「BEPS包摂的枠組み」で、残された論点と詳細な実施計画につき政治的合意が示された。以下これを「今回の合意」という。
今回の合意は、①デジタル課税と②最低税率の2つの柱から成る。①柱1(Pillar One)は、GAFAをはじめとする巨大IT企業を念頭において、新しい課税権を市場国(market jurisdiction、ユーザーの所在する国)に配分する。②柱2(Pillar Two)は、法人税の引き下げ競争に歯止めをかける。1920年代に原型が成立した国際課税ルールを見直す、大がかりなものである。作業日程も野心的で、2022年に多国間条約を策定し、2023年に実施することを目指している。他方で、今回の合意が触れていない重要課題が残されている。
そこで以下では、柱2、柱1、より大きな課題、の順に、今回の合意に対する時評を試みる。その際、せっかく本誌で時評の機会を与えられたのであるから、本誌の最近の論説による問題提起を参照して論をすすめることにしたい。
2 租税競争は手なずけられるのか
吉村政穂「租税競争は手なずけられるのか?─OECDの挑戦」法律時報92巻9号(2020年)56頁は、可動性の高い課税ベースを誘引する法人税率引き下げ競争が生ずる中で、これに対する国際的な課税ルール策定の枠組みの変容をレビューした上で、OECDのとりくみが分岐点に直面しているとする。この論説は、租税競争(taxcompetition)は手なずけられるのか、という問いを読者に投げかけた。
今回の合意はこれにどう応答しているか。柱2は、租税競争に対する制限として、実効税率ベースで法人税最低税率15%という下限を設ける。これだけを読めば、租税競争を手なずけることにすんなり成功したと誤解する向きもあるかもしれない。しかし話はそう単純ではない。
もともと、課税権は各国の主権の発現と目されており、各国それぞれの憲法秩序の下で(日本の場合は憲法84条を参照)、法人税率や課税ベースの設計も各国に委ねられている。その中でグローバルに最低税率を設けるやり方として、柱2は、有志国が共通アプローチを採用することで、軽課税国の課税が足りない部分にトップ・アップ課税することとしている。これがいわゆる所得合算ルール(Income Inclusion Rule, IIR)であり、軽課税国にある子会社等の実効税率が15%に満たない場合、15%に至るまで上乗せする形で(=top up)、親会社の居住地国が課税する。加えて、これを補完するものとして、軽課税国にある親会社等の実効税率が15%に至るまで子会社等の居住地国が課税するルール(軽課税支払ルール、Undertaxed PaymentRule, UTPR)を組み合わせることとした。
重要なこととして、柱2において、これらのルールの採用は各国の義務ではない。もし各国が採用を選択する場合には、上記の合意内容に整合的な形でこれを行う、ということが合意されたにとどまる。また、他の国がこれらのルールを適用することを承認することとされた。
つまり、一口に最低税率15%などといっても、各国がばらばらに税率を設定するという基本は何ら変わるところがない。そのことを前提とした上で、現地国の課税だけでは15%に足りないところを(やる気のある)親会社居住地国が追加的に課税しましょう、という合意なのである。
したがって、柱2が租税競争の制限としてどこまで効果的なものになるかは、各国がどの程度これを採用するかにかかっている。この点、すでに米国には類似の制度がある。EU域内で同様の主張をしていた独仏や、法人税率がOECD平均よりも高い日本は、柱2の採用に前向きである。これに対し、中国は開発の観点から慎重姿勢を崩していない。軽課税国たることを国家戦略としてきたアイルランドやシンガポールなど、租税以外の投資誘致策へと動き出す国もある。中にはケニヤやナイジェリアのように合意に参加しなかった国さえ存在する。今回の合意が以上のような性質のものである以上、「課税権力のグローバル化」(諸富徹『グローバル・タックス』〔岩波書店、2020年〕)といった将来像からはほど遠い。
3 デジタル・プラットフォームビジネスに関する税制の設計
千葉惠美子「デジタル・プラットフォームビジネス研究の最前線 本企画の目的」法律時報93巻5号(2021年)104頁は、デジタル・プラットフォームビジネスを切り口として、ビジネスと法制度をどのようにデザインすると社会的な価値の最適化を図ることができるのか、という問題を提示する。これを皮切りに、さまざまの法領域を横断する連載が続いている。
デジタル・プラットフォームビジネスの典型例がGAFAであり、今回の合意の柱1はGAFAを念頭においている。より正確にいうと、2015年以降の「経済のデジタル化」に対するOECD/G20のとりくみが、IT企業に対象を限定するか否か(=GAFAを狙い撃ちするか)をめぐる熾烈な交渉を経て、今回の柱1の形をとるに至った。
柱1の対象企業は、全世界売上が200億ユーロ(約2.6兆円)超、かつ、利益率が10%超の多国籍企業である。この要件を充たす企業は全世界で100社程度である。ちなみに、柱2の対象企業は、年間総収入金額が7.5億ユーロ(約1000億円)以上の多国籍企業を対象としているから、柱1はそれよりもはるかに限定された企業群を相手にしていることになる。
柱1は、これら対象企業の売上の10%を超える超過利益の25%を売上に応じて市場国に配分する。これがいわゆる「利益A(Amount A)」と呼ばれる部分である。従来の課税ルールでは、いくら国内ユーザーが消費を行っていても、多国籍企業の物理的拠点が国内にないとか、無形資産が軽課税国に移転されるとかの理由で、その企業の利益に対して市場国は課税できなかった。これを変更して、利益Aに限っては例外的に、市場国に新しい課税権を配分することにしたのである。配分するといっても、超国家機関の如き何者かが出張ってきて賦課徴収するというような話ではない。各国がそれぞれの国内法にもとづいて課税権を行使して差し支えない、ということに合意したわけである。
したがって法的な変更が必要になるのは、まずもって租税条約についてである。というのも、これまで市場国に課税を許容してこなかったのが、従来の合意を法的に体現する二国間租税条約ネットワークであったからである。既存の条約網を上書きすべく、新しい課税権の配分を盛り込んだ多国間租税条約の策定を予定している。
注目すべき点として、この多国間条約において、すべての企業に対するすべてのデジタルサービス税(Digital Services Tax)とこれに類する税を廃止し、将来にわたり導入しないことを定めることが合意された。これにはさしせまった実益がある。欧州がGAFAを標的とするデジタルサービス税を導入したことが、GAFAの本拠地国と目される米国との間の摩擦を生んでいたからである。一国主義的措置の乱立を避ける方向を打ち出したことは、ひとつの成果ということができよう。
もっとも、政治的妥協にこぎつける過程で、新たな課税権の性格や根拠についての明示的考慮は、少なくとも公表文書をみる限り、後景に退いていった。検討の初期においては、デジタル・プラットフォームのビジネスモデルを分析し、グローバル・バリュー・チェーンにおいてどこで価値創出(value creation)がなされているかに着目していた。しかし2019年はじめには、新たな課税権の構想として、GAFAを念頭においたユーザー参加(英国案)、業種を限らないマーケティング無形資産(米国案)、新興国の伝統的な主張である重要な経済的プレゼンス(インド案)が並立する状態になった。2020年にはこれらをなんとか統合する形で交渉の基礎が示され、対象企業を「自動化されたデジタルサービス(Automated digital services)」と「対消費者ビジネス(Consumer-facingbusinesses)」とすることなどが示された。この議論が膠着する中で、2021年には米国新政権の提案を受けて、発想を変えて、数量基準で世界トップ100社を対象とするという妥協が成立した。妥協にありがちなこととして、新たな課税権の理論的根拠については、各国政府の間で同床異夢の状態が続いているとみられる。
もちろんこの間、学説が手をこまねいて議論の進展を傍観していたわけではない。いわく、価値創出という基準は機能するか。ユーザー参加は課税権拡大の根拠になるか。市場国に地域特有レント(location-specific rent)の存在を観念できるか。いやそもそも、法人所得税の課税権配分基準は原産地(origin)ベースから仕向地(destination)ベースに切り換えたほうが最適なのではないか。このような議論が地球上のあちこちで展開され、BEPS包摂的枠組みの公聴会でインプットされた。それらの一部は活字や録画になって、さらに議論を誘発した。
しかしそのような学説のいずれかが決定的な論拠となって今回の合意を主導したという証拠は、少なくとも筆者には見当たらない。新しい課税権を支える明示的根拠の不在は、今回の合意がはたしてどの程度国際課税ルールに安定性をもたらすものであるかについて、疑念を抱かせる材料である。
以上述べたことは、柱1を盛りこむ新多国間条約が各国で批准された場合の話である。現実には、肝心の米国で、上院の3分の2といったハードルをどう超えるのか。より手前のところで実施にほころびが生じ、振り出しに戻る可能性すら否定できない。
4 再分配による社会再統合への処方箋
藤谷武史「グローバル資本規制─『複合的分断と法』の視角から」法律時報89巻9号(2017年)13頁は、グローバル資本が福祉国家を弱体化させたという単純な見立てを排したうえで、グローバル化の下で分断された社会を再分配によっていかに再統合するか、という問題を鋭く読者につきつける。
今回の合意がこの問題に応えていないことは、勘のいい読者にはもう自明のことであろう。たしかに、GAFAに代表されるグローバル企業が地球上のどこに資本を移動しても最低税率に服するようにすれば、税引後でみた資本と労働の取り分のうち労働に分配される部分が相対的に増加するかもしれない。また、テクニカルに切り取られた「利益A」について市場国が課税できるようにすれば、その税収分配額の大小はともかく、ユーザー所在地国の人々の抱える政治的鬱憤がいくぶんかは解消されるかもしれない。途上国の税収構造が法人税に依存していることからは、「どの国でも課税されない所得(stateless income)」の発生源をつぶすことで、貧しい国の人々の厚生が高まる可能性すらある。しかしながら、これらが希望的可能性であることに加え、診断結果としてつきつけられた複合的な病理に適合的な処方箋になっているとはいいがたい。
今回の合意は、デジタル経済の投げかける根本的な課題の一部に触れただけである。GoogleやFacebookが「労働としてのデータ」に対価を支払わないことは、データの品質を高めるインセンティブを欠く点(PosnerとWeylのRadical Marketsの指摘)に問題があるだけではない。市場構造の根っこに問題があるときに、いかにこれまでの国際課税ルールを大胆に改変するものであるにせよ、限られた「利益A」の課税を許容する程度の解決で何になるのか。生活のすべてがインターネットに依存し、嬉々としてデータを提供し、知らず知らずのうちに「おすすめ」に誘導される人生。「監視資本主義」という見立てに必ずしも同意しない読者に対しても、現実の解決策と問題の深さとのミスマッチを、訴えたいと思う。
(ますい・よしひろ 東京大学教授)
「法律時評」をすべて見る
「法律時報」の記事をすべて見る
本記事掲載の号を読むには
・雑誌購入ページへ
・TKCローライブラリーへ(PDFを提供しています。次号刊行後掲載)