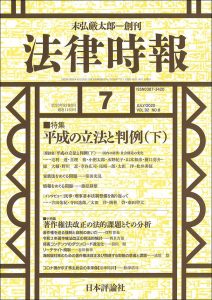(第31回)企業活動に対する法規制と行動経済学的分析(沼田知之)
 企業法務、ファイナンス、事業再生、知的財産、危機管理、税務、通商、労働、IT……。さまざまな分野の最前線で活躍する気鋭の弁護士たちが贈る、法律実務家のための研究論文紹介。気鋭の弁護士7名が交代で担当します。
企業法務、ファイナンス、事業再生、知的財産、危機管理、税務、通商、労働、IT……。さまざまな分野の最前線で活躍する気鋭の弁護士たちが贈る、法律実務家のための研究論文紹介。気鋭の弁護士7名が交代で担当します。(毎月中旬更新予定)
得津晶「企業における行動学的転回(behavioral turn)と消費者取引規制の在り方」
法律時報92巻8号(2020年7月号)116~121頁より
伝統的な経済学においては、消費者や企業の経済活動は、自己の効用・利益を最大化させるために合理的な意思決定に基づいて行われることが前提とされている。しかし、現実の人間の行動は、必ずしも合理的で一貫しているとは限らないことが、心理学的な研究によって明らかになって来た。法制度論や法解釈に経済学的知見を活用する「法と経済学」においても、「仮定されているモデルが現実的でないのではないか」といった疑問が投げかけられることがある。法と経済学の利点のひとつは、社会をモデル化して議論を行うことで事前的アプローチ(「こういった法制度を導入すれば人々はこう行動する」)をある程度可能にする点にあるところ、一定の仮定を置いたモデル化をしなければ結果の合理的予測はできない以上、モデル化自体が否定されるものではない。しかし、仮定の設定次第で予測される結果が異なる点には確かに注意が必要である1)。
このような伝統的な経済学におけるモデルに対して、認知心理学の影響の下で発展した行動経済学においては、人間の認知プロセスや意思決定の合理性には限界があること(限定合理性)を前提とした上で、人間行動及びその相互作用を分析・探求し、より現実に根ざしたモデルの構築が目指されている。行動経済学の研究は1990年代以降盛んに行われるようになり、法律学との関係でも、法制度の立案や法律の運用・解釈など様々な文脈において行動経済学的な知見が参照されるようになってきている。例えば、消費者契約においては、消費者の持つ情報が不十分であることに加え、楽観主義・近視眼バイアス・利用可能性バイアスなどの認知バイアス2)により判断がゆがんだり、ナイーブさ故に合理的な行動をしない可能性があることから、この点に着目して規制を根拠付けたり、法解釈に活用する可能性が論じられている3)。
行動経済学は個人の限定合理性に着目するものであることから、消費者の行動分析等には適用しやすいが、企業行動にはそのまま当てはまらないとの指摘もなされている。しかし、本稿の著者である得津教授は、企業の活動も終局的には個人によってなされるものである以上、行動経済学が前提とする個人の限定合理性や認知バイアスの影響を受けるはずであると指摘する。そして、会社法と行動経済学に係る米国のサーベイ論文4)等を参考に、行動経済学的アプローチを企業側の行動の分析にも活用できるのではないかにつき検討を加えている。
得津教授は、行動経済学的であるとされるものの中には、主体の限定合理性を必ずしも前提とせず、他の要素によっても説明が可能なものが含まれていることを指摘する。例えば、インサイダー取引規制が前提としている市場の効率性の不成立は、広義の取引費用(情報伝達コスト、エージェンシーコスト)によってももたらされるものである。また、金融機関の経営者が回収可能性が低い融資を実施するといった過度なリスクテイクの問題は、金融機関にとっては不合理であっても、経営者レベルでは自らの経済的利益(報酬)を最大化させるべく合理的に行動した結果であり、エージェンシー問題であって限定合理性の問題ではないとの説明も可能とされる。他方で、経営者が過度のリスクテイクを行う背景には、自信過剰(overconfidence)というバイアスが働いている可能性も指摘される。同様に、証券市場の短期主義についても、機関投資家の報酬体系等に起因するエージェンシー問題としての側面と、認知バイアス(本稿で明示的な指摘はなされていないが、例えば現在バイアス)の双方が影響している可能性があると考えられる。
次に、本稿では、既存の法律学の法理には、既に行動経済学的な発想が取り込まれていることが指摘される。例えば、取締役の善管注意義務に関するいわゆる経営判断原則は、経営者がリスク回避的であることを前提にしているが、これはプロスペクト理論5)における分析とも軌を一にするものである。すなわち、プロスペクト理論からは、確率に対する人の反応は線形でなく、同じ期待値であっても、目の前に利益を得る機会がある場合にはより確率の高い行動を選択し、逆に、損失を回避する機会がある場合には確率が低くとも損失全体を回避し得る行動を選択する傾向があることが導かれる。このため、経営者は確率は低いが大きな利益を生む機会のある経営行動を選択しない傾向があるが、そのような傾向を是正し、期待値がより大きい行動を選択するインセンティブを与えることが、経営者に企業の利益を最大化させる上で有用であると考えられる。他方で、プロスペクト理論からは、損失回避の機会がある場合には経営者は過剰にリスクテイクをする可能性が示唆される。このことから、得津教授は、既に損失が生じている場面での経営判断原則の適用は望ましくない場合があると指摘している。
また、米国における研究状況との比較として、得津教授は、米国では集団心理・同調圧力によって招かれたバイアスにより、経営者が法令違反を行いやすくなるといった分析がなされているのに対し、日本の経営者については、むしろ法規制ができることで、禁止領域のみならず、そのグレーゾーンも避けようとするなど、法令違反を過度に重視するバイアスがかかっており、リスクを取れずイノベーションのための行動を起こせない点が課題だと指摘する6)。
この点については、評者のささやかな実務経験に照らして、2点の留保をしておきたい。第一に、得津教授自身が、法令違反リスクの過度な回避という「効果が発生するかはケースバイケース」と指摘されているとおり、場面によっては異なるバイアスが働くこともあるように思われる。例えば、経営者が自ら旗振りをして進出しようとしている事業分野がある場合、「当該分野に投資を行うことが企業に利益をもたらす」という仮説を支える事実ばかりを集め、仮説に反する情報を無視してしまう「確証バイアス」が働き、その結果不合理なリスクテイクがなされる可能性がある。
第二に、先に登場したプロスペクト理論との関係で、法令違反についても、既に法令違反の結果が生じている場合には、過度なリスクテイクがなされるケースがあると思われる。すなわち、経営者が法令違反を認識した場合にこれを直ちに開示・是正して現時点で一定の損害を被ることと、これを隠蔽し続けて一定の確率で将来的により大きな損害のリスクを負うことを天秤に掛けた場合、後者の方が損害の期待値が大きいにもかかわらず、後者を選択してしまうケースが、過去の不祥事の実例を見ても散見される7)。
本稿は、直接的には消費者取引規制についての適用可能性を論じたものであるが、行動経済学的アプローチを企業側の行動の分析にも活用できるのではないかとの問題意識は、広く他の法律分野における研究や、企業実務家の業務(例えば、不正防止体制の構築やイノベーションを促す人事制度・組織作りなど)にも有益な示唆を与えるものと考えられる。
本論考を読むには
・雑誌購入ページへ
・TKCローライブラリーへ(PDFを提供しています。次号刊行後掲載)
◇この記事に関するご意見・ご感想をぜひ、web-nippyo-contact■nippyo.co.jp(■を@に変更してください)までお寄せください。
この連載をすべて見る
脚注
| 1. | ↑ | 同趣旨を指摘するものとして、例えば仮屋広郷「『法と経済学』への招待-法学の側面から-」一橋論叢113巻4号446頁(1995年)参照。 |
| 2. | ↑ | 過去の経験や常識に基づく思い込み等によって生じる、事実認識の歪み・偏りを指す。例えば、仮説を検証する際に都合の良い根拠ばかりを集めて、仮説に反する情報を無視してしまう「確証バイアス」、異常事態が発生しているにもかかわらず、正常な範囲に留まっていると思い込む「正常性バイアス」、人や物を評価する際、顕著な特徴に引きずられて他の特徴についての評価が歪められる「ハロー効果」など、多くの認知バイアスが知られている。 |
| 3. | ↑ | 一例として、西内康人『消費者契約の経済分析』(有斐閣、2016年)、オレン・バー=ギル著・太田勝造監訳『消費者契約の法と行動経済学』(木鐸社、2017年)、室岡健志「消費者保護政策の経済分析と行動経済学」行動経済学13巻105頁(2020年)。 |
| 4. | ↑ | Donald C. Langevoort, Behavioral Approaches to Corporate Law, in Claire A. Hill and Brett H. McDonnell eds., RESEARCH HANDBOOK ON THE ECONOMICS OF CORPORATE LAW (Edward Elgar, 2012) 442-455. |
| 5. | ↑ | 不確実性の下で人がどのような選択をするかを記述したモデルであり、行動経済学における代表的な研究成果とされる。 |
| 6. | ↑ | もっとも、得津教授は、そのような認知バイアスは規範の内面化・受容を促し、エンフォースメントコストの節約になっている可能性も指摘する。 |
| 7. | ↑ | 但し、経営者がこのような法令違反状態の開示を先送りする原因は必ずしも認知バイアスによるものとは限らない。オーナーでない経営者にとっては、自身の任期中に不祥事が発覚しなければ、責任追及のリスクは限定的であると考えた結果、法令違反を隠蔽するという場合もあると思われ、このようなケースでは、限定合理性の問題というよりもエージェンシー問題であると考えられる。 |
 沼田知之(ぬまた・ともゆき)
沼田知之(ぬまた・ともゆき)東京大学法学部、同法科大学院修了後、2008年より西村あさひ法律事務所。主な業務分野は、危機管理、独禁法。海外公務員贈賄、国際カルテル、製造業の品質問題等への対応のほか、贈収賄防止、競争法遵守、AIを活用したモニタリング等、コンプライアンスの仕組み作りに関する助言を行っている。主な著書・論稿として『危機管理法大全』(共著、商事法務、2016年)、「金融商品取引法の課徴金制度における偽陽性と上位規範の活用による解決」(旬刊商事法務1992号(2013年3月5日号))等。