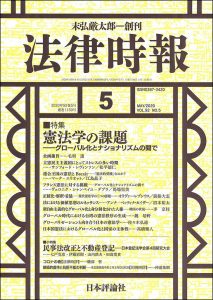継続的虐待と抗拒不能の判断(仲道祐樹)
 一つの判決が、時に大きな社会的関心を呼び、議論の転機をもたらすことがあります。この「判例時評」はそうした注目すべき重要判決を取り上げ、専門家が解説をする「法律時評」の姉妹企画です。
一つの判決が、時に大きな社会的関心を呼び、議論の転機をもたらすことがあります。この「判例時評」はそうした注目すべき重要判決を取り上げ、専門家が解説をする「法律時評」の姉妹企画です。月刊「法律時報」より掲載。
(不定期更新)
◆この記事は「法律時報」92巻5号(2020年5月号)に掲載されているものです。◆
名古屋高裁令和2年3月12日判決
1 はじめに
名古屋地裁岡崎支部が、平成31年3月26日に下した準強制性交事件に対する無罪判決(名古屋地岡崎支判平成31年3月26日LEX/DB25562770)は、いわゆるフラワーデモの呼び水となり、社会的なうねりを作り出す一因となった。本件は、当時19歳の被害者Aに対し、平成29年8月および9月の2度にわたり性交をしたとの公訴事実に関するものであり、幼少期からの虐待および思春期になって以降の性的虐待を背景としたものであった。
家庭内における継続的な虐待の問題は、平成29年の刑法改正による監護者性交等罪(179条)の立法事実の1つであった。そこでは、実親等の監護者からの性的虐待が幼少期から継続的に行われている事案では、個別の性行為だけをとらえると、抗拒不能とは言えない事案が存在することが確認されている(法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会第3回会議議事録参照)。
しかし、監護者性交等罪は、18歳未満の者を客体とするものとして設計された。本件は、継続的な虐待を背景とした事案でありながら、被害者が19歳の時の性交を対象とするがゆえに、監護者性交罪の適用ができない事案であった。虐待が18歳以降にも継続していた場合に、それ以降の行為をどのように処罰するかが問題となる。
第一審判決のおよそ1年後の令和2年3月12日、注目の集まる中、控訴審である名古屋高裁が下したのは逆転での有罪判決(懲役10年)であった。本稿では、第一審判決と控訴審判決とを比較し、何が結論の差につながったのかについて若干のコメントをする。
2 第一審判決
第一審は、本件の背景に、Aが小学生の頃に始まった身体的虐待およびAが中学2年生の頃に始まり高校卒業後も継続していた性的虐待があったことを指摘し、Aの同意を否定しつつも、抗拒不能とするには合理的な疑いが残るとして、準強制性交罪の成立を否定した。
第一審の示した抗拒不能要件の理解は、「行為者と相手方との関係性や性交の際の状況等を総合的に考慮し、相手方において、性交を拒否するなど、性交を承諾・認容する以外の行為を期待することが著しく困難な心理状態にあると認められる場合を指す」とするものである。
第一審の抗拒不能解釈自体は、抗拒不能の解釈についての最高裁判例が存在しない中で、177条の暴行脅迫要件に関する最判昭和24年5月10日刑集3巻6号711頁、最判昭和33年6月6日集刑126号171頁とのバランスを考慮したものであり、従来の裁判例や学説とも軌を一にする。控訴審もこの点は是認する。
第一審はしかし、継続的な虐待があったことや、被告人がAを精神的支配下に置いていたことを認定しつつも、a)8月の性交の前日までの期間に被告人からの性交要求を拒否して受けた暴行は、頻度や態様の点からも、実父との性交を「受忍し続けざるを得ないほどの極度の恐怖心を抱かせるような強度の暴行とはいえない」、b)両親の反対を押し切って大学入学を決め、また月8万円前後のアルバイト収入があり一人暮らしを検討しているなど、「日常生活全般において、Aが監護権者である被告人の意向に逆らうことが全くできない状態であったとまでは認め難い」との評価から「被告人がAの人格を完全に支配し、Aが被告人に服従・盲従せざるを得ないような強い支配従属関係にあったとまでは認め難い」との評価を導き、もって抗拒不能の状態に至っているとはいえないとし、被告人に無罪を言い渡した。
控訴審は、この推論を批判したのである。
3 控訴審判決
控訴審判決は、第一審判決の先の判示部分につき、次のように論難する。
「〔原判決は〕当初は『……性交を承諾・認容する以外の行為を期待することが著しく困難な心理状態』としながら、最終的には『逆らうことが全くできない状態』あるいは『人格を完全に支配』さらには『服従・盲従せざるを得ないような強い支配従属関係』といった、当初設定した抗拒不能の成立範囲に比べてより厳しい成立範囲を要求しているが、成立範囲をそのように変えた理由について原判決は何ら言及して」おらず、「抗拒不能概念の法解釈に関し一貫性に欠ける」と。
その上で、原判決の認定を前提にすれば、Aが抗拒不能状態にあったことは優に推認されるとし、さらに、原判決が抗拒不能との評価を阻む事情とした各事実(上記a)b)のほか、被告人との性交を回避した経験、性交を回避するための策のためらい)についても、抗拒不能状態を否定する事情たりえないとした。
さらに控訴審判決は、「原判決は、本件行為が、父親が実の子に対し継続的に行った性的虐待の一環であるという実態を十分に評価していないといわざるを得ない」と強く批判する。本判決は、継続的虐待が行われる環境下で、かつ親の監督下で生活する子供の場合、子供は家から簡単には逃げ出せないため、親から繰り返し性的虐待を受けると無力感を持ち、性的要求に対し抵抗しなくなる傾向があり、また、家庭内において虐待があるからといって、当該家庭の日常生活全てにわたり虐待が行われているわけではなく、普通一般の親子関係が営まれることは何ら不思議ではないという鑑定人の評価に基づき、第一審における無罪の結論は「本件事案の実態を十分に理解しなかった結果」であるとした。
4 継続的虐待という文脈の考慮
第一審に対する控訴審の批判は、継続的虐待であるという本件の特殊性を考慮しなかった点に向けられている。これは、学説から批判が向けられた点でもある。しかし、第一審も、継続的な虐待の存在自体は認めている。したがって、第一審判決が批判されているのは、継続的虐待が背景にあることを認定したにもかかわらず、これを適切に評価に組み込まなかったからだということになる。
では、ここでいう「適切に評価に組み込まなかった」とは何を意味するのであろうか。おそらくそれは、本件の様々な事情は、継続的虐待関係という文脈において理解されるべきであるにもかかわらず、第一審はそこから切り離して評価をした、という意味となろう。
例えば、暴行の頻度が減り、態様も執拗ではなくなっていたという事情を、第一審は、抗拒不能を否定する事情としている。しかし、これを控訴審のように継続的虐待という文脈においてとらえ直すと、虐待により被害者の抵抗意欲が薄くなっており、強度の暴行を用いる必要がなかったと解釈され、抗拒不能を基礎づける事情となる。このように、行為の文脈をどのように設定するかによって、人の態度の意味は変わりうる。
継続的虐待の存在により、犯行当時の様々な態度の意味が変わってしまうことを印象的に示す判例がイギリスにある。CvR事件([2012] EWCA Crim 2034)は、被告人Cが養女であるNに対し、Nが5歳から25歳までの約20年間にわたり継続的に性的虐待を加えていた事案に関するものである。本件では、Cが撮影したNの裸の写真や、口腔性交のシーンを写したビデオが証拠として提出されており、そこに写し出されたNの様子は、Cとの性的行為を望んでいる様に見えるものであった。ここからCは、Nが(イギリスの性的同意可能年齢である)16歳になった後については、Nの同意があるとして争った。
しかし、第一審の有罪判決に対するCの控訴を受けた控訴院は、次のように述べて、控訴を棄却した。被害者の幼少期の虐待「は、被害者が成長した後で与えた見かけ上の同意を検証し評価する文脈を提供する。……〔子ども時代に始まる虐待〕が被告人による被害者への支配と管理に影響、反映した、との心証を陪審が得たならば、被害者〔の〕見かけ上の同意……は、真に見かけ上のものであって、現実のものではな〔い〕と結論づけることは妨げられない」とした(同じような判断は、アメリカ・アイオワ州最高裁判所の判例(State v. Meyers, 799 N.W.2d 132(Iowa 2011)にも見受けられる)。
CvR事件は、写真や映像に写った被害者の態度だけを見れば、被害者は同意していたとの評価に到達しうる事案であった。しかし、被告人が継続的に被害者に性的虐待を行っており、被害者自身も逆らえば何をされるかわからないと考えていた中で撮られた写真であるという文脈は、「被害者は同意していた」との解釈に至ることを許さないであろう。このように、人の態度は、置かれた文脈によってその様相を変えるのである。
以上のように、控訴審と第一審とは、継続的虐待という文脈のもとで事実を評価したかによって結論を異にしたといえる。
5 要件解釈と事実をつなぐ中間的枠組み
しかし、第一審判決が、「継続的虐待」という文脈を考慮しなかったのには、裁判官個人の感覚に帰すことのできない要因があると思われる。これが第一審と控訴審の結論をわけた第2のポイントであり、第一審判決が、「強い支配従属関係」という限定的基準を持ち出した点に関わる。
第一審判決を事実認定の観点から見ると、次のように整理できる。まず抗拒不能を、「性交を承諾・認容する以外の行為を期待することが著しく困難な心理状態にあると認められる場合」と解釈する。次に、継続的虐待の事案においては、「著しく困難な心理状態」が、「強い支配従属関係」の存在をもって認められるとの置き換えを行う。そして本件各事情からは「強い支配従属関係」は認められないと評価し、これをもって抗拒不能には該当しないというのがこれである。
「著しく困難な心理状態」は、「著しい」と「困難」という評価を含んでいることから、裁判所は、「著しく困難である」という評価に向けて間接事実を積み上げていくことになる。しかし、事実から評価に至るためには、前提として、評価にジャンプしうる一定の事実に到達する必要がある。第一審判決が、強い支配従属関係を要求した背景には、「著しく困難」との評価に至りうる事実は何かを検討し、強い支配従属関係をその事実として措定し、これが間接事実から推認できれば、そこから「著しく困難」との評価に到達できると考えたからではないだろうか(もっとも「強い」「支配従属関係」自体が評価を含んでいるのだが)。
控訴審判決は出発点となる抗拒不能の解釈を第一審と共有しつつ、事実認定の筋において第一審判決と発想を異にする。控訴審判決は、1継続的虐待があったという事実と、2親からの継続的な性的虐待の被害者は、無力感を持ち、性的要求に対し抵抗しなくなる傾向があるという実証的な経験則を組み合わせた上で、3他の選択が可能であったことをうかがわせる事情(性交回避の試みなど)によって推認が阻まれるかを検討する形で「著しく困難」であったかの判断を行っていると推測される。この枠組みでは、1と2が「著しく困難」を認める方向に作用し、3はその推認を阻むかという観点から検討されることになる(学費や生活費による被告人への経済的負い目という事情は、抵抗困難性を強める事情と位置づけられる)。
この枠組みの違いは、継続的虐待の位置づけに影響を与える。第一審のように「強い支配従属関係」という中間的事実を措定すると、継続的虐待の存在は、「強い支配従属関係」を推認する間接事実の1つに過ぎなくなり、その推認力が相対化される。継続的虐待を適切に評価していないとの第一審判決への批判は、この枠組みが前提にある限り不可避である。これに対して、控訴審の枠組みは、継続的虐待は、「著しく困難」を第一次的に基礎づける事情として、前者の枠組みよりも大きな重要性が認められることになる。
第一審と控訴審の判断の違いは、法の解釈と、評価的要素への事実のあてはめをつなぐ中間的枠組みの相違に由来するのではないだろうか。そうだとすれば、第一審の「文脈無視」は、第一審の裁判体を構成した裁判官の感覚のみに帰されるべきものではなく、刑法学にもその責任の一端がある。刑法学がこれまで行ってきた作業は、条文の文言についての解釈を示す点に集中していた。しかしその解釈には、「著しい」や「○○な程度の」という評価文言が含まれることが少なくない。その結果、個別の事案について、どのような事実があれば、その評価へとジャンプしてよいのかに関する中間部分の枠組みを欠いている。このような枠組みがない中で第一審の裁判官の判断をただ論難するだけでは、同様の問題が生じかねない。刑法学の側からそのような中間理論を提示していくことの必要性を、本件は示しているのである。
(なかみち・ゆうき 早稲田大学教授)
「判例時評」をすべて見る
「法律時報」の記事をすべて見る
本記事掲載の号を読むには
・雑誌購入ページへ
・TKCローライブラリーへ(PDFを提供しています。次号刊行後掲載)