(第12回)AIに関する著作権法上の留意点(濱野敏彦)
 企業法務、ファイナンス、事業再生、知的財産、危機管理、税務、通商、労働、IT……。さまざまな分野の最前線で活躍する気鋭の弁護士たちが贈る、法律実務家のための研究論文紹介。西村あさひ法律事務所の7名の弁護士が交代で担当します。
企業法務、ファイナンス、事業再生、知的財産、危機管理、税務、通商、労働、IT……。さまざまな分野の最前線で活躍する気鋭の弁護士たちが贈る、法律実務家のための研究論文紹介。西村あさひ法律事務所の7名の弁護士が交代で担当します。(毎月中旬更新予定)
上野達弘「人工知能と機械学習をめぐる著作権法上の課題」
法律時報91巻8号(2019年7月号)33頁~40頁より
AIと著作権に関しては、AI技術を用いてコンピュータにより作成された作品の著作物該当性や、(当該作品が著作物に該当しないのであれば、)立法論として当該作品を著作権法で新たに保護するべきであるかについて盛んに議論がなされており、筆者も、知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会で、AIに関する参考人として、「AIが自律的に生み出した生成物に対する知的財産権の付与の是非」と題する発表をさせていただいた。ちなみに、この議論は、「AI生成物」という言葉を用いて議論されることが多いが、「AI生成物」については、「自律的に」生成されたという点を定義に含めるか否か、また、含める場合における「自律的に」の意味が、論者によって異なり得る点に留意が必要である。
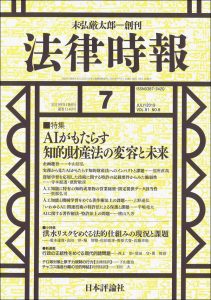
法律時報2019年7月号
定価:税込1,890円(本体価格1,750円)
また、実務的な観点からは、AIによる著作物の利用が、具体的にどこまで可能であるか(当該利用について著作権が制限される範囲)を理解しておくことが重要である。特に、本年1月1日から施行された平成30年の著作権法改正により、AIによる著作物の利用可能な範囲が広がっている点に留意する必要がある。
本稿では、これらの点について、本質を捉えたわかりやすい具体例を用いた説明がなされている。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号)。
このように、著作物は、「思想又は感情」を表現したものであることが要件となっているため、コンピュータによって生成されたものは、著作物には該当しないと解されている。
本稿は、この点に関して、コンピュータと人間の関与の程度には様々な場合があり得るとした上で、具体例として、人間が自動作曲システムに、曲想、曲調、長さ、テンポ等のパラメータを入力することによって作成されたメロディは、「思想又は感情」を表現したといえるかが問題になると指摘している。
人間が作曲をする際に考慮するポイントに類似する複数のパラメータを、人間が、パラメータ相互の関係も考慮しながら設定して生成されたメロディは、「思想又は感情」が表現されているようにも思われる。その一方で、人間が、パラメータ相互の関係を考慮せずに各パラメータを入力したに過ぎない場合には、「思想又は感情」が表現されていないようにも思われる。いずれにせよ、事案によって判断が分かれ得る難しい問題である。
また、著作物は、「創作的に表現した」ものであることが要件となっている。
本稿は、この点に関して、人間による指示や関与が、コンピュータに対して行われる場合と、人間に対して行われる場合とで異なるかが問題になると指摘する。その上で、1万人の人間に詳細な条件等を設定してそれぞれ作曲をさせて、その1万人が作成した1万曲の中から1曲を選択する行為と、自動作曲システムに詳細なパラメータを入力して作成された1万曲の中から1曲を選択する行為という具体例を挙げている。
前者の「選択」行為は、既に人間が創作した1万曲の中から1曲を選ぶ行為に過ぎないため、当該「選択」行為が、選択した当該1曲を「創作的に表現した」ものには該当しないと解される。そのため、人間による指示や関与が、コンピュータに対して行われる場合と、人間に対して行われる場合とで異ならないはずであると考えるならば、後者の「選択」行為も、「創作的に表現した」ものに該当しないことになる。しかし、そのように考えるべきであるかについては、意見が分かれるのではなかろうか。
AI技術を用いてコンピュータにより作成された作品が著作物に該当しないのであれば、立法論として当該作品を著作権法で新たに保護するべきであるかが問題となる。
本稿は、立法論として、当該作品について著作権に基づく保護を与える理由として、当該作品に対する投下資本の回収、及び、当該作品が著作物として保護されないとすると、当該作品がAIによって生成されたのではなく、人間が創作したものと僭称されるようになりかねないこと(僭称コンテンツ問題)が考えられるが、当該作品を著作権法で新たに保護することについては、過剰保護であるとの批判があることを紹介している。
次に、AIによる著作物の利用が可能な範囲(当該利用について著作権が制限される範囲)に関して、本稿では、この点について定める著作権法30条の4第2号の要件、効果について丁寧に解説している。その上で、著作権法30条の4第2号が、イギリス法、ドイツ法、欧州指令と比較して、営利目的の場合を含む点、(複製のみならず、)あらゆる利用行為が許容される点等から非常に広範な権利制限規定であるため、機械学習にとって非常に有用な規定であり、日本は、いわば「機械学習パラダイス」であると指摘している。
さらに、本稿は、既存の著作物の創作的表現が残らない形で著作物を利用する場合には著作権は及ばないとした上で、具体例として、AI技術を用いてジブリ映画などを網羅的に情報解析し、それと同じスタイルで新たな作品を生成しても、もとの著作物の創作的表現が残っていなければ、既存の著作物の著作権は及ばないと指摘している。
この点は、著作権法は「表現」を保護するものであり、いわゆるアイディアを保護するものではないという原則から当然に導かれる結論であるが、見落とされがちな点であり、鋭い指摘であるといえる。
このように本稿では、AIに関する著作権法上の留意点について、本質を捉えたわかりやすい具体例を用いた説明がなされており、示唆に富む論考である。
本論考を読むには
・雑誌購入ページへ
・TKCローライブラリーへ(PDFを提供しています。次号刊行後掲載)
この連載をすべて見る
 濱野敏彦(はまの・としひこ)
濱野敏彦(はまの・としひこ)
2002年東京大学工学部卒業。同年弁理士試験合格。2004年東京大学大学院新領域創成科学研究科修了。2007年早稲田大学法科大学院法務研究科修了。2008年弁護士登録(第二東京弁護士会)。2009年弁理士登録。2011-2013年新日鐵住金株式会社知的財産部知的財産法務室出向。主な著書として、『秘密保持契約の実務』(共編著、中央経済社、2016年)、『知的財産法概説』(共著、弘文堂、2013年)、『クラウド時代の法律実務』(共著、商事法務、2011年)、『解説 改正著作権法』(共著、弘文堂、2010年)等。




