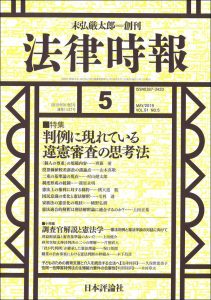性同一性障害特例法の生殖能力要件の合憲性(木村草太)
 一つの判決が、時に大きな社会的関心を呼び、議論の転機をもたらすことがあります。この「判例時評」はそうした注目すべき重要判決を取り上げ、専門家が解説をする「法律時評」の姉妹企画です。
一つの判決が、時に大きな社会的関心を呼び、議論の転機をもたらすことがあります。この「判例時評」はそうした注目すべき重要判決を取り上げ、専門家が解説をする「法律時評」の姉妹企画です。月刊「法律時報」より掲載。
(不定期更新)
◆この記事は「法律時報」91巻5号(2019年5月号)に掲載されているものです。◆
最高裁第二小法廷平成31年1月23日決定 →裁判所ウェブサイト
1 はじめに
日本法は、性的マイノリティへの対応を長らく怠ってきた。しかし、21世紀に入り、ようやく取り組みがなされるようになってきた。2003年には、身体と性自認の一致しない者(性同一性障害者)の法律上の性別取扱いの変更を認める「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下、特例法)が制定された。また、2015年には、東京都渋谷区で同性カップルに対するパートナーシップ制度が導入され、同様の制度が、世田谷区、伊賀市、宝塚市、那覇市、札幌市、福岡市、大阪市でも施行されている。さらに、2019年には、同性婚を認めないことの違憲性を訴える訴訟が提起され、注目を集めている。
このような中、1月23日に、最高裁判所で、性別取扱い変更の要件に関する重要な決定が出された。その内容を検討してみたい。
2 事案と判旨
特例法3条1項は、「家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる」として、①20歳以上(同1号)、②未婚(同2号)、③未成年子不在(同3号)、④生殖能力不在(同4号)、⑤他の性別の性器への近似外観(同5号)の5要件を定め
る。今回の決定では、④生殖能力不在要件が問題となった。
申立人は、男性への性別取扱い変更を求めた女性だが、生殖腺除去手術への恐怖や身体的特徴を基準に性別を判断する考え方への疑問から、生殖腺除去手術を受けていなかった。申立人は、特例法3条1項4号は、身体への侵襲を受けない権利(憲法13条)と平等権(憲法14条1項)を侵害し違憲無効であり、それを前提に審判すべきと主張した。
これに対し、第一審の岡山家裁津山支部審判平成29年2月6日、抗告審広島高裁岡山支部決定平成30年2月9日は、いずれも合憲と判断し、申立人の性別取扱い変更を認めなかった。そこで、特別抗告がなされたが、2019年1月23日に、最高裁第二小法廷は、それを棄却する決定(以下、本件決定)を出した。
最高裁は、問題の規定は「手術を受けること自体を強制するものではないが,性同一性障害者によっては,上記手術まで望まないのに当該審判を受けるためやむなく上記手術を受けることもあり得るところであって,その意思に反して身体への侵襲を受けない自由を制約する面もある」としつつ、「変更前の性別の生殖機能により子が生まれることがあれば,親子関係等に関わる問題が生じ,社会に混乱を生じさせかねないことや,長きにわたって生物学的な性別に基づき男女の区別がされてきた中で急激な形での変化を避ける等の配慮」を理由として、「本件規定の目的,上記の制約の態様,現在の社会的状況等を総合的に較量すると,本件規定は,現時点では,憲法13条,14条1項に違反するものとはいえない」と結論した。
また、鬼丸かおる・三浦守両裁判官は、後述する欧州の動向を紹介し、「憲法13条に違反するとまではいえないものの,その疑いが生じていることは否定でき」ず、「本件規定に関する問題を含め,性同一性障害者を取り巻く様々な問題について,更に広く理解が深まるとともに,一人ひとりの人格と個性の尊重という観点から各所において適切な対応がされることを望む」とする補足意見を付している。
3 問題の所在
法的な性別取扱いと性自認との不一致は、当事者に様々な困難を生じさせる。例えば、同性婚が法制化されていない国では、性自認が男性であっても、女性とは婚姻できない(あるいはその逆)。
同性婚が法制化されている国においても、性自認と異なる扱いを家族法で受け苦しむことがある(性自認が男性であるにもかかわらず、家族法上は母親とされるなど)。家族法分野以外にも、労働法や社会保障法分野でも男女別の取り扱いがある。刑罰で懲役刑などを受ける場合に、男性刑務所・女性刑務所どちらに収監されるかも問題である。戸籍や住民票による性別の公証は、職場や公共施設での男女別の扱いに大きく影響する。
諸外国では、20世紀後半から、この問題に対処する立法が進んだ。1972年のスウェーデン「性の転換に関する法律」を皮切りに、1980年にドイツ「トランスセクシュアル法」、1982年にイタリアで「性別表記の訂正に関する規範」などが制定され1)、現在では、多くの国に性別取扱いの変更を認める法律がある。
もっとも、生来的な生殖能力を残したまま性別取扱いを変更すると、「男性である母」・「女性である父」など、それまでの法体系にはなかった概念を設ける必要が生じる。社会生活上も、トイレ・浴場の利用、女性用DVシェルターでの保護、刑務所への収監など、男性の生殖能力を持つ者を生来的な女性と全く同等に扱ってよいかは、慎重な検討を要する。このため、性別取扱いの変更を認める諸外国では、生殖能力がないことを要件にすることがあり、日本法でも、特例法3条1項4号の生殖能力不在要件が設けられた2)。
しかし、この要件があると、当事者は、性自認と異なる法的取扱いを甘受するか、手術を受けるかの過酷な二択を迫られる。これが人権や憲法上の権利の侵害とならないかは、重大な問題である。
4 欧州の動向
近年、欧州では、この問題について注目すべき決定や判決が出されている。
まず、2011年、ドイツ連邦憲法裁判所は、性別取扱い変更について、生殖能力の不在を要件とすることを違憲だとする決定3)を出した。ドイツのトランスセクシュアル法には、出生登録上の名前だけを変える「小解決(kleine Lösung)」と、名前のみならず性別取扱いも変更する「大解決(große Lösung)」の二つが規定されている。この決定では、大解決について、永続的な生殖能力の不在を要件とした規定が違憲とされた。
また、2017年には、欧州人権裁判所も、同趣旨の判決4)を出した。この判決では、フランス法が、変更後の性別に適合する「外観の不可逆的変更」を要件としていることについて、欧州人権条約違反ではないかが問われた。判決は、この要件は、生殖能力を失う可能性の高い手術を受けることを要件とするに等しく、私生活を尊重される権利(欧州人権条約8条1項)の侵害で、条約違反だと結論した。
近年は、性別取扱い変更に生殖能力の不在を要件としない国も増えてきている。今見た欧州人権裁判所の判決の認定によれば、2017年の段階で、オーストリア、デンマーク、エストニア、ドイツ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、マルタ、モルドバ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、イギリス、フランス、ノルウェーの18か国が、生殖能力喪失手術を性別取扱い変更の要件としていない。こうした欧州の動向を踏まえると、日本の特例法3条1項4号に違憲の疑いがかかるのも、当然だろう。
5 性別変更のベースライン
しかし、本件決定の結論は冷淡だった。4に見た欧州の決定・判決との違いは、ベースラインの理解に起因しているように思われる。
ベースラインとは、憲法や条約が原則として要求している措置や対応を言う。例えば、表現の自由(憲法21条1項)の保障の下では「個人が何でも自由に表現できること」が、生存権(憲法25条1項)の保障を前提にすれば「最低限度を下回る生活をしている国民が、生活保護など国家の援助を受けられること」がベースラインとなる。
憲法上の自由や給付の条件として、「他の憲法上の自由の不行使」を要求することは、憲法上の権利の直接的な制約となる。例えば、「自由にデモ行進をするには、国家監視のためのGPS埋め込み手術を受けなければならない」とか「不妊手術を受けなければ、生活保護は給付しない」という法律は、表現の自由や生存権の侵害であると同時に、身体への侵襲を受けない権利の直接的な侵害と認定できるだろう。
このため、性別変更に関するベースラインをどのように理解するかで、特例法の性質は大きく変わる。憲法が、性自認に応じた性別取扱いの変更を求める請求権(性別変更請求権)を保障しているとすれば、「申立に応じて性別取扱いを変更すること」が憲法上のベースラインとなる。これをベースラインとした場合、生殖能力喪失を性別変更の要件とすることは、身体への侵襲を受けない自由の直接制約と評価されるだろう。身体への侵襲を受けない自由は、内心の自由や拷問されない権利などと同様に絶対保障を受ける権利(あるいは、それに近い手厚い保障を受ける権利)と解すべきだから、生殖能力不在要件の設定を正当化することはかなり難しい。
4に見た決定・判決は、そのようなベースラインの設定に基づくものと読める。ドイツ憲法裁判所2011年決定は、違憲の根拠として、一般人格権(ドイツ連邦共和国基本法2条1項)および身体不可侵の権利(同2項)の二つの権利を挙げる。これは、一般人格権から性別変更請求権が導かれるとしたうえで、それを前提にすると、問題の要件は身体不可侵の権利の侵害になる、との判断を示したものだろう。また、欧州人権裁判所2017年判決は、私生活を尊重される権利(欧州人権条約8条)は、性的アイデンティティーについても適用されるとしたうえで、手術を性別変更の要件にするのはその権利を害するとしている。これは、私生活を尊重される権利には性別変更請求権を含むという趣旨の論証である。
他方、本件決定は、特例法は「手術を受けること自体を強制するものではない」という「制約の態様」を強調する。これは、性別取扱いの変更は憲法上のベースラインではなく、憲法との関係では「国家がしてもしなくてもよいこと」との認識を前提にしている。そうなると、特例法の要件は、必ずしも国家が給付しなくてよいものについて、条件付けをしているだけということになり、自由の直接的な制約とも認定できないし、厳格な審査の対象になることもない。
このように、性別変更請求権をベースラインとするかどうかが、ドイツ憲法裁判所や欧州人権裁判所と、本件決定の分水嶺である。
6 おわりに
本件決定は、申立人の訴えを退けたが、特例法の「憲法適合性については不断の検討を要する」と述べており、当事者に過酷な選択を強いている点に配慮がないわけではない。また、生来の生殖能力を残したまま性別取扱いを変更した場合、親子関係の法的処理に複雑な考慮が必要になるのは確かだが、対応が法論理的に不可能というわけではない5)。今後、この問題をどのように検討して行くべきか。二つの方向があり得る。
第一の方向は、性別変更請求権が憲法上保障されないのか、検討し直すことだ。欧州の裁判例を見ても分かるように、この権利が、憲法上の権利ないし人権だという論理には、相当な説得力がある。
また、第二の方向として、平等権侵害として検討を深めることも考えられる。1993年のドイツ連邦憲法裁判所決定は、性自認に応じた名前の変更(小解決)について、満25歳以上を要件として、年少者と年長者を区別することは平等権(ドイツ連邦共和国基本法3条1項)侵害だとした6)。この決定は、性別変更請求権が憲法上のベースラインとなると断言できなかった時代状況の中で出されたものである。日本法でも、生殖能力を欠いた者は性別変更ができるのに、そうでない者はそれができないのは不平等だという主張はできるだろうし、実際、申立人はそのような主張をしている。
同性婚が法制化されていない日本では、性別変更ができない不利益は諸外国に比してさらに大きい。躊躇のない検討が必要である。
(きむら・そうた 首都大学東京教授)
「判例時評」をすべて見る
「法律時報」の記事をすべて見る
本記事掲載の号を読むには
・雑誌購入ページへ
・TKCローライブラリーへ(PDFを提供しています。次号刊行後掲載)
脚注
| 1. | ↑ | 大島俊之「性同一性障害に関する法的な諸問題」南野千恵子監修『【解説】性同一性障害者性別取扱特例法』(日本加除出版、2004年)39頁。 |
| 2. | ↑ | 南野監修・前掲註1)93頁では、親子関係の混乱に加え、「生殖腺から元の性別のホルモンが分泌されることで、身体的・精神的に何らかの好ましくない影響を生じる可能性を否定できない」ことが、生殖能力不在要件が設定された理由だと解説されている。 |
| 3. | ↑ | BverfGE128,109.邦語での解説として、平松毅「性同一性障害者に戸籍法上の登録要件として外科手術を求める規定の違憲性」ドイツ憲法判例研究会編『ドイツの憲法判例Ⅳ』(信山社、2017年)73頁以下参照。 |
| 4. | ↑ | A. P., Garçon and Nicot v. France, 6 April, 2017.Application no. 79885/12, 52471/13, 52596/13.なお、フランスでは、2016年10月12日に、生殖能力喪失手術を要件としないことを明示する立法が行われた。 |
| 5. | ↑ | これを検討した重要文献として、石嶋舞「性同一性障害者特例法における身体的要件の撤廃についての一考察」早稲田法学93巻1号(2017年)79頁。 |
| 6. | ↑ | BverfGE88,87. |