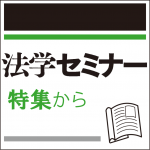民法上の責任に関する原則(野澤正充)(特集:責任はどこから――責任原則とその展開)
◆この記事は「法学セミナー」822号(2023年7月号)に掲載されているものです。◆
特集:責任はどこから――責任原則とその展開
私法上の責任は何を根拠に生じるのか、生じた責任は誰が・どこまで負うべきなのかを、様々なケースに基づいて検討する。
――編集部
1 はじめに――「責任」という語の多義性
民法の講義を聴くと、担当教員が、損害賠償「責任」を負うと言ったり、損害賠償「義務」(または「債務」)を負うと言うのを耳にするであろう。そのようなときに、「責任」と「義務」・「債務」の違いが気にはなるものの、同じ意味かなと考えて、そのままにした経験はないだろうか。しかし、後に債権法の講義では、「責任なき債務」(=自然債務)という概念が説明され、また担保物権法では、「債務なき責任」(=物上保証)という概念が登場する。さらに、会社法では、「有限責任・無限責任」という語が用いられるが、「有限債務・無限債務」とは言わない。そうなると、「責任」という語と「債務」または「義務」という語が、同じなのか違うのか、ということが問題となる。
そこで、法学部に入学した時に購入したであろう法律用語辞典を調べてみると、「責任」という語が「非常に多義的」に使われていることがわかる1)。すなわち、道徳的責任や政治的責任に対して法律的責任という場合には、法律上の不利益または制裁を負わされることを意味する。この法律的責任は、①民事責任と刑事責任とに分けられ、民事責任はさらに、②契約責任と不法行為責任とに分けられる。そして、②についてはそれぞれ、③過失責任と無過失責任とが問題となる。ただし、③については、平成29年の民法(債権関係)の改正(以下、「債権法改正」という。)および判例法の展開により、伝統的な考え方が変容しつつあることを指摘することができる。以下、順に検討する。
なお、民法上の責任と債務(義務)は、ほぼ同義である。ただし、厳密には、債務が債権の目的である給付をしなければならない拘束を意味するのに対し、責任は、債務が履行されない場合に備えて、債務者の財産が引当て(担保)になっていることを意味する。もっとも、債務は責任を伴うことが原則であり、債務者の財産(責任財産)が引当てとなるから、この両者を区別する意義は小さい。上記の「責任なき債務」・「債務なき責任」および有限責任は、その例外であるといえよう。
2 民事責任と刑事責任の区別
一定の加害行為が行われると、加害者は、不法行為による損害賠償義務を負うとともに、処罰されることがある。前者が民事責任であり、後者が刑事責任である。この両責任は、古くは明確に区別されず、不法行為制度も刑罰の一種であると考えられていた。例えば、ローマ法では、私人によって追及される民事責任(不法行為責任)と国家によって追及される刑事責任とは、一応区別されてはいたものの、不法行為制度の目的は、加害者に罰金を科すことにあり、被害者が損害賠償を得ることではなかった。その結果、刑事上の訴追がなされると、私人が不法行為訴権を行使することはできず、また、不法行為による罰金は、損害額のみならず、その倍額を請求することも認められていた。しかし、近代になると、公法と私法が分化され、国家が刑罰権を独占する反面、不法行為は、被害者に生じた損害を塡補することを目的とする制度として純化された。
したがって、今日では、民事責任と刑事責任とは明確に区別され、以下の違いがあるとされている2)。
まず、責任の内容の面では、刑事責任は、加害者に対する応報であり、その社会的責任を問うものである。そのため、加害者の主観的事情を重視し、原則としては故意による加害のみを罰して、過失犯の処罰は例外であるが、未遂でも処罰されることがある。これに対して、民事責任は、被害者に生じた損害を塡補するものである。それゆえ、加害者の主観的事情によっては差異を設けず、故意または過失によって他人に損害を与えた場合には、一様に損害賠償が認められる反面、現実に損害の生じていない未遂の場合には、不法行為責任は生じない。
また、手続の面では、民事責任は、民事訴訟法の適用される民事裁判によって課され、刑事責任は、刑事訴訟法の適用される刑事裁判によって科される。もっとも、フランスでは、不法行為が犯罪を構成する場合には、刑事裁判所に対して損害賠償請求訴訟の提起を可能とする付帯私訴(action civile)が認められている(フ刑訴2条以下)。そして、わが国でも、旧刑事訴訟法においては、公訴に附帯して損害賠償を求める附帯私訴の制度が認められていた(旧刑訴567-613条)。このような制度には、公訴の証拠を私訴にも共通に活用でき、被害者の救済に資するという長所も存するが、わが国では、戦後の改正により、英米法系にならって附帯私訴の制度を廃止した。しかし、平成12年11月1日に施行された「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」は、被害者の損害賠償請求権の行使のために、公判記録の閲覧・謄写を認めた(3・4条)。そして、平成20年の同法の改正では、一定の犯罪に係る刑事被告事件の被害者またはその相続人(一般承継人)が、同事件の係属する裁判所に対し、損害賠償命令の申立てをすることができるとした(17条)。この損害賠償命令の申立ての制度は、附帯私訴に類似するものであり、犯罪被害者による損害賠償請求に関する紛争を「簡易かつ迅速に解決すること」(1条)を可能にする。
以上のように、刑事裁判と民事裁判とが分離した結果、同一の事件について両裁判の結果が異なることがある。ただし、原則としては、刑事責任よりも民事責任の方がより広く認められ、刑事責任が認められる場合には、民事責任を免れることはできないと考えられる。
脚注
| 1. | ↑ | 高橋和之ほか編『法律学小辞典〔第5版〕』(有斐閣、2016年)772-773頁。 |
| 2. | ↑ | 加藤一郎『不法行為〔増補版〕』(有斐閣、1974年)。 |