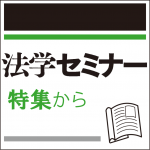主権者としての受刑者 ――在外国民審査権訴訟から受刑者選挙権訴訟への軌跡(吉田京子)(特集:憲法を生かす)
◆この記事は「法学セミナー」820号(2023年5月号)に掲載されているものです。◆
特集:憲法を生かす
憲法訴訟に取り組む弁護士たちの活躍にフォーカスすることで、憲法が実生活に生かせることを示す、実務家たちによる憲法入門。
――編集部
1 大法廷判決の余韻
2022年5月25日、最高裁判所大法廷で、判決の要旨が告げられるのを聴いた。戦後11例目の法令違憲判決である。15名の裁判官全員一致の判断で、宇賀克也判事が補足意見を書いた1)。
2018年4月の提訴から4年越しの判決だった。これによって、海外に暮らす人たちも、国民審査の投票ができるようになる。また、立法不作為の違憲を争う訴訟は、国家賠償請求や実質的当事者訴訟としての地位確認の訴えだけではなく、違法確認の訴えという訴訟類型を用いることができることが明らかになった。今後の憲法訴訟の地平を変える可能性のある重要な判断だ。
私たちは記者会見をし、判決の成果を報告した。新聞は見出しに大きく「最高裁が襟を正した」「国民にバトンが渡された」と私たちの言葉を掲げてくれた。懐かしい、そして心から尊敬する友人から「同窓として誇らしいです。自分ももっと仕事頑張らなければと勇気をもらいました。ありがとう」というメッセージが届いた。大学時代の恩師がわざわざ送ってくださったメールには、あまりにも嬉しくありがたい言葉が書き連ねられていた。裁判官を辞めたあと、研究者へのあこがれを捨てることができずにご相談をし、迷った挙句に弁護士になった。その時、「弁護士として大成することで恩返しができれば」と伝えていた。もちろんまだ道半ばではあるが、一定の成果を挙げることができたことに安堵した。
夜のニュースで私たちの記者会見が放送されると、祝砲はさらに続いた。一緒に喜んでくれる人のいることを改めてありがたく感じた。
脚注
| 1. | ↑ | 最大判2022(令和4)・5・25民集76巻4号711頁、在外国民審査権判決。 |