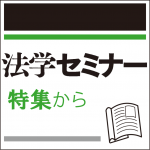時代を踏み越える企て(新田一郎)(特集:法制史のすすめ――歴史から繙く法律学)
特集から(法学セミナー)| 2021.09.16
◆この記事は「法学セミナー」801号(2021年10月号)に掲載されているものです。◆
特集:法制史のすすめ――歴史から繙く法律学
権利と利害関係が複雑に絡み合う現代の法社会にあって、過去に生きた法のすがたを描き出すことは、現行法の歴史的位置やありかたを理解し、その未来に示唆をもたらすことにつながります。
過去と未来の懸け橋となる、“実践的な学問”である法制史の世界にご招待します。
――編集部
1 基礎法学の役割
「法制史」は、日本法制史・西洋法制史・東洋法制史などを含み、法社会学・法哲学・外国法などと併せて「基礎法学」という看板のもとに緩やかに括られている。誤解されることもあるようだが、基礎法学とは、法学の入門的な基礎学習科目、ではない。法という仕組みの成り立ちを、その基礎まで掘り下げて考究するために、仕組みの内側からではなく外側から、様々な角度をつけて観察することが、基礎法学の役割である。基礎法学のうちでも法社会学・法哲学が法の構造的な深部へと直接に踏み込もうと企て、比較法・外国法分野は法の諸相の共時的な差異に着目するのに対して、法の時間的な推移に着目することが法制史の特徴であり、そうした観察を日本について試みるのが日本法制史、ヨーロッパを中心とした西洋世界に材を取るのが西洋法制史、中国をはじめとする東洋諸地域を対象に据えるのが東洋法制史、ということになる1)。これら多角的な観察が相まって法の立体的な像を結び、法学の視野と可能性を拡げる。いずれにせよ、法の成り立ちを基礎まで掘り下げて考究することは、高度に専門的な営みである。
脚注
| 1. | ↑ | 西洋・東洋についてさらに細分化して、「ドイツ法制史」「中国法制史」など国名地域名を冠して唱えられることもしばしばある。一方、日本法制史が地域により細分化されて論じられることはあまりないが、「日本」の同一性を問う余地は無論ある。「日本」の条件を斉一化する仕組みがいかにして形成され推移してきたか、という問題自体が、「日本」法制史の重要な関心対象たりうる。 |