書評:升永英俊『統治論に基づく人口比例選挙訴訟』日本評論社,2020年(評者:中村良隆)
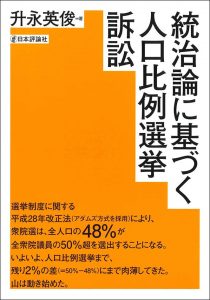 読者諸兄姉は、一人一票の実現を訴える新聞広告を一度は目にしたことがあるのではないかと思われる。
読者諸兄姉は、一人一票の実現を訴える新聞広告を一度は目にしたことがあるのではないかと思われる。
青色発光ダイオード訴訟の原告代理人としても有名な著者は、有志弁護士らとともに、2009年に「一人一票実現国民会議」というNPOを立ち上げ、最高裁判所の裁判官の国民審査のための情報として、判決において、どの裁判官が一人一票に賛成あるいは反対の意見を述べたかの情報を新聞の意見広告で提供するとともに、衆・参全国すべての選挙区で原告を立て、「一票の格差」を争う訴訟を行ってきた。
本書は、『“清き0.6票”は許せない』(現代人文社、2010年)、『一人一票訴訟上告理由書』(日本評論社、2015年)に引き続き、最高裁に提出された上告理由書をもとに、一連の訴訟において2009年から主張している1)「統治論に基づく人口比例選挙」という考えを中心にまとめられたものである。
「統治論に基づく人口比例選挙」とは、憲法56条2項、1条および前文1項第1文から、人口比例選挙(各選挙区に議席を割り当てるときに、人口に比例して行わなければならない)という憲法上の要件が導かれるとするものである。
すなわち、本書によれば「国民は、『両議院の議事』につき、『正当に選挙された国会における代表者を通じて』(同前文第1項第1文冒頭)、『出席議員の過半数(50%超)でこれを決』(同56条2項)するという方法(即ち、多数決)(換言すれば、間接的な多数決の決議方法)で、『主権』を行使する。……一方で、非『人口比例選挙』(即ち、一票の価値の較差のある選挙)では、【全人口の50%が、衆参両院の各院の全議員の50%を選出すること】が保障されない」ので、「【『主権』を有する国民】ではなく、【『主権』を有する国民の代表者に過ぎない国会議員】が、『主権』(即ち、国政のあり方を最終的に決定する権力)を有していることになり得る。」(3~4頁)
そして基準として、「一票の格差が2倍を超えているかどうか」ではなく、「全人口の50%が衆参両院の各院の全議員の50%を選出すること」ができるかどうかという点をメルクマールとして重視するのが特色である(5頁)。このように、従前の訴訟で援用されてきた14条1項や15条1項、44条ただし書(著者の語法では「人権論」)に依拠しておらず、14条1項等に基づく従来の議論を「決め手を欠く、匙加減論」と批判している(1頁)。
こうした著者の主張に対し、工藤達朗教授は「投票価値の平等が、個人の主観的権利(基本権)侵害の問題というよりもむしろ人口比例原則という客観的法原則違反の問題として把握されている……権利侵害から客観法違反へ論点の移行といえる。」と位置づけながらも、①権利侵害をやり過ごして客観的憲法原理の違反を強調することが、違憲無効判決を導き出す戦略として適切なのか、②これらの憲法規定が人口比例原則の根拠として適切であるか、③原告の論理では、直接民主制こそが「本来の」「真の」民主制で、代表民主制はいわば「次善の策」として採用されたものにすぎないことになり、命令委任が認められなければならないと批判している2)。
しかし、14条1項や44条ただし書に頼らずに、56条2項、1条および前文を組み合わせて一人一票原則を導き出したのは、条文相互の関連性の論理的な分析に基づく、非常に独創的かつユニークな見解として高く評価されるべきものである3)。アメリカ合衆国における似たような事例として、連邦議会下院選挙における「一票の格差」が問題となったWesberry v. Sanders, 376 U.S. 1(1964)がある。合衆国憲法第14修正の平等保護条項は、州に対する制約であるため、連邦議会下院の場合に直接適用することはできない。そこでブラック判事の執筆した法廷意見は、第1編2節の連邦下院議員が「人民により……選出される」という規定には、起草者意思に基づいて一人一票原則が含まれると判示したのであった4)。
選挙権は、単なる人権でなく、「国民としての仕事」、公務としての性質があることについては、学会の多数が賛同している(二元説)5)。このように、選挙にはそもそも、人権としての側面と、立法部を構成するための手続(統治機構)としての側面がある。「投票価値の平等(一票の格差)」と「議員定数不均衡問題」、「一人一票原則」と「人口比例選挙」という異なる言い方も人権と統治の2つの視点を示しているように思われる。
したがって、14条1項がなくとも、56条2項+1条+前文1項から一人一票原則が導けるということを示したのは、様々な条文が連なって立憲主義と民主主義を支えている「憲法の重層的構造」を例証したものといえる。現に、議員及び選挙人資格の平等を定める44条ただし書は「第2章 国民の権利及び義務」ではなく「第3章 国会」の中にあり、14条1項と「統治論」とを結びつけている条文であるといえるのではないか。
このように、オリジナリティーあふれる著者の見解を憲法の重層的構造の一例の発見として評価することができるとすると、「14条等に基づく人権論」が悪者であるかのように示唆するのは言い過ぎであろう6)。悪いのはこれまでの最高裁の先例とそれに基づく誤った思考のはずである。投票価値の平等が憲法の「基本的な要求7)」であると口にしながら、違憲・合憲を判断する際には、「以上のような事情を総合すれば……8)」というマジック・ワードで人口要素と非人口要素を一緒くたにし9)、いわゆる「合理的期間論10)」によって、基準の問題と救済の問題を故意に混同させている最高裁の判例理論こそ、真の「匙加減論」の名にふさわしいものというべきである。
もう一つ気になる点としては、「全人口の50%が衆参両院の全国会議員の50%を選出」することがゴールであるかのように書かれていることがある(89頁)。一人一票原則は、全人口の50%が衆参両院の全国会議員の50%を選出することの十分条件であるが、必要条件ではない。したがって、これを当座の目標とすることが訴訟戦略として妥当であるとしても、このマクロの目標が達成された後も個人の投票価値の不平等というミクロの問題は依然として残ることになるのではないか。
基準の問題として、著者は、平成24年最高裁大法廷判決(民集66巻10号3368頁)及び平成26年最高裁大法廷判決(民集68巻9号1374頁)によれば、「参院選の1票の投票価値の平等の要請が、衆院選のそれより「後退してよいと解すべき理由は見いだし難い」と解され(19頁)、憲法は、【各議院の総議員が選出される選挙の1票の投票価値が、それぞれ、同等であること】を「所期」しているので(21頁)、参院選(平成31年)の3.00倍の人口較差は、衆院選(平成29年)の1.98倍の人口較差より後退しているので、違憲であると主張している(22頁)。
この主張は、平成24年判決によって、参議院の独自性に基づいて都道府県を選挙区の単位としてよいという従来の先例法理が修正されたこと11)の論理的帰結であるといえる。もっとも、「衆院選と参院選の1票の投票価値が同等でなければならない」といっても、「どの程度ならば同等といえるのか」という有権者の一票の格差と同じ問題が生じるが、さしあたり、衆議院について選挙区間の人口較差が2倍未満となることを基本とする旨の区割りの基準が国会により定められているのであるから12)、参議院についても同様に2倍未満にしなければならないということは確実にいえるであろう13)。
救済について、著者は、一貫して選挙無効判決を求めてきている14)。まず第1に、違憲状態の選挙は憲法98条1項後段の規範により「その効力を有しない」として「合理的期間論」および「事情判決の法理」を否定する(57頁;前著1-6頁、167-170頁)。そして第2に、たとえ「事情判決の法理」を前提としたとしても、選挙無効判決により選挙区選出議員は失職するが、100人の比例代表選出議員は残り、この議員数は参院の定足数83人を超えるので、選挙無効の判決によって、全議員がいなくなり、違憲規定の改正さえできないという不当な結果、社会的混乱は生じないと主張する(58頁)。
私見では、ある選挙区割法が投票価値の平等に反し憲法に違反するかどうかは法規範すなわち基準の問題であって、「合理的期間論」すなわち国会にモラトリアムを与えるという理由で「違憲状態であるが違憲ではない」というのは日本の法律家にしか通用しえない言い訳と思う。しかし、違憲と判断されたものをどのように是正するかという救済の問題については裁判所に相当の裁量があり、遡及的に無効とせず将来的にのみ無効とすることもできるし(59頁)、必ずしもただちに選挙無効・再選挙とせずとも、適当な救済を編み出すことができるのではないかと考えている15)。
しかし現在のように、国会が投票価値の平等を確保しようとする真摯な努力を一向に行おうとはせず、裁判所も「事情判決の法理」・「合理的期間論」に加えて、国会な事後的な努力(較差是正の措置)を「違憲状態」かどうかの判断要素として潜り込ませる(42-45頁)というように二重、三重に大目に見るというのでは、万年「違憲状態」の現状を変えることは決してできないであろう16)。選挙無効判決は最善の解決策ではないかもしれないが17)、適正な再区割を怠っている国会議員に対する目に見える形での制裁となることは確かであり、著者の言葉を借りれば「核爆発級の破壊力のある」ショック療法であることは間違いない18)。
細かな議論はあるにせよ、一人一票原則の実現のための著者による長年の取り組みは何人も決して軽視できないノブレス・オブリージュ(noblesse oblige)の実践であって、私はそれに対し深く敬服する者の1人であり、本書は、前著とともに、肝心な問題から逃げ、問われていることに答えない19)、最高裁の姿勢に根本的な反省を迫るものといえる。
評者:中村良隆 名古屋大学大学院法学研究科(モンゴル国立大学法学部内日本法教育研究センター)特任講師
脚注
| 1. | ↑ | 『“清き0.6票”は許せない:一票格差訴訟の上告理由を読む』45-46頁、58-60頁、110頁(2010年、現代人文社);朝日新聞意見広告2012年9月8日;朝日新聞意見広告2013年11月12日 |
| 2. | ↑ | 工藤達朗「衆議院選挙と投票価値の平等」判例時報2383号130頁、132頁(2018年)。ただし、著者は本書5頁において、人口比例選挙は自由委任の原則と矛盾しないと反論している。 |
| 3. | ↑ | 笹倉秀夫教授の『法解釈講義』4頁(東京大学出版会、2009年)の図式および同頁以下の分析によれば、法解釈の参照事項として、[A]法文自体の意味、[B]条文同士の体系的連関、[C]立法者の意思、[D]立法の歴史的背景、[E]「法律意思」(=正義・事物の論理・解釈の結果)があり、条文の適用の仕方として、[イ]文字通りの適用(12頁によれば「文理解釈」の語は概念の混同をもたらしてきたとして敢えて避けたとのこと)、[ロ]宣言的解釈、[ハ]拡張解釈、[ニ]縮小解釈、[ホ]反対解釈、[ヘ]もちろん解釈、[ト]類推、[チ]比附、[リ]反制定法的解釈が挙げられている。この分類によれば、14条1項や44条ただし書から一人一票原則が出てくるというのは一般的に[A]法文自体の意味ということになり(深く掘り下げれば[C]立法者の意思、[D]立法の歴史的背景も関係してくるが)、56条2項+前文+1条から一人一票原則を導けるというのは[B]条文同士の体系的連関によるものだと整理できる。 |
| 4. | ↑ | 「ある選挙区における一票が他の選挙区の一票よりも価値があるなどということは、民主的な政府という我々の根本的な概念に真っ向から反するだけでなく、憲法会議で粘り強く争われ確立された、連邦下院が『人民により』選ばれるという原理を無にすることになる。合衆国憲法の歴史、特に第1編2節の採択に関する経緯をみれば、合衆国憲法の起草者は、全州一(=大)選挙区であれ小・中選挙区であれ、選挙制度の如何にかかわらず、人口こそが連邦下院の基盤となるべきであると考えていたことが明らかである。」(376 U.S. 1, 8-9) この解釈は、[C]立法者の意思に依拠するものである。 |
| 5. | ↑ | 芦部信喜・高橋和之『憲法(第7版)』271頁(岩波書店、2019年);野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ⅰ(第4版)』510-511頁(有斐閣、2006年)など。 |
| 6. | ↑ | 升永英俊『一人一票訴訟上告理由書:憲法を規範と捉えた上での判決を求める』35頁(日本評論社、2015年)(以下、「前著」と略す。) |
| 7. | ↑ | 最大判昭和58年11月7日民集37巻9号1243頁「選挙区の人口と配分された議員数との比率の平等が最も重要かつ基本的な基準とされる」;最大判平成11年11月10日民集53巻8号1441頁「選挙区割りを決定するに当たっては、議員一人当たりの選挙人数又は人口ができる限り平等に保たれることが、最も重要かつ基本的な基準である」 |
| 8. | ↑ | 最大判平成25年11月20日67巻8号1503頁「具体的な選挙区を定めるに当たっては、都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位として、地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの諸要素を考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められているところである。したがって、このような選挙制度の合憲性は、これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断される」 |
| 9. | ↑ | Reynolds v. Sims判決によって確立されたといわれる一人一票原則(one person, one vote rule)の意義は、「人口要素の非人口要素に対する優位」、つまり人口の平等をまず第一に確保しなければならず、行政区画との一致等の非人口要素は人口の平等を害さない限度において、二次的に考慮に入れることができるにすぎないことにある。中村良隆「Reynolds v. Sims (1964):議会の議席配分と『一人一票原則』」アメリカ法判例百選12-13頁(有斐閣、2012年)山本庸幸裁判官もその反対意見(最大判平成26年11月26日等)において「投票価値の平等は、他に優先する唯一かつ絶対的な基準として、あらゆる国政選挙において真っ先に守られなければならないものと考える。これが実現されて初めて、我が国の代表民主制が国民全体から等しく支持される正統なものとなるのである。」と述べている。 |
| 10. | ↑ | 最大判昭和51年4月14日民集30巻3号228頁「具体的な比率の偏差が選挙権の平等の要求に反する程度となったとしても、これによって直ちに当該議員定数配分規定を憲法違反とすべきものではなく、人口の変動の状態をも合理的期間内における是正が憲法上要求されていると解されるのにそれが行われない場合に始めて憲法違反と断ぜられるべきものと解するのが相当である。」 |
| 11. | ↑ | 参議院選挙における投票価値の平等について、従前の判例(最大判昭和58年4月27日民集37巻3号345頁)は、「都道府県が歴史的にも政治的、経済的、社会的にも独自の意義と実態を有し一つの政治的まとまりを有する単位としてとらえ得ることに照らし、これを構成する住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味しようとしたものである」と都道府県を選挙区の単位とすることに合理性があるとし、「投票価値の平等の要求は、人口比例原則を基本とする選挙制度の場合と比較して一定の譲歩、後退を免れない」と述べていた。
しかし、平成24年判決は、都道府県を「参議院議員の選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はなく、むしろ、都道府県を選挙区の単位として固定する結果、その間の人口較差に起因して投票価値の大きな不平等状態が長期にわたって継続していると認められる状況の下では,上記の仕組み自体を見直すことが必要になるものといわなければならない。」と述べて、参議院の独自性から都道府県を選挙区の単位としてよいという従来の先例法理を修正した。 |
| 12. | ↑ | 衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条1項 |
| 13. | ↑ | 著者と同じように、私も2倍説では基準として不十分であり、投票価値は「実現可能な限り」平等にしなければならないと考える。Karcher v. Daggett, 462 U.S. 725 (1983) 福田博裁判官も、最大判平成10年9月2日民集52巻6号1373頁の追加反対意見において「国会が最高機関であり続けるためには、平等原則を可能な限り貫徹し、選挙区間の較差を一対一に近づけるため、誠実な努力を尽くすべきである。」と述べている。君塚正臣教授は、学説の状況について「選挙権が憲法の基本である民主主義・立憲主義の根幹であるとすれば、その侵害・不平等はおよそ許されず、本来、一人一票が基本である。これが現在、圧倒的に有力である。」と評価している。判例評論(最大判平27・11・25)判例時報2296号148頁。 |
| 14. | ↑ | 前掲注1)『”清き0.6票”は許せない』92頁。 |
| 15. | ↑ | この点では、工藤教授による「合理的期間論には疑問があり、違憲状態であれば違憲判決を下すべきだと考えるが、違憲と無効とを切り離した違憲宣言(違憲確認)判決は、平等や社会権に関する判決手法として有用だ」(前掲注3・135頁)との指摘に賛同する。アメリカでも「合理的期間論」に相当する法理はないが、「事情判決の法理」に相当する「de facto officer doctrine」というものがある。暫定的な救済として、裁判所は①選出された議会の任期および職務を再区割に限定することができるであろうし(Holt v. Richardson, 238 F. Supp. 468 (D. Haw. 1965); Buckley v. Hoff, 234 F. Supp. 191 (D. Vt. 1964))、②選出された議員が議会で投票する場合に、1人1票でなく選挙区の人口数に応じた票数を与えることができるであろう(Thipgen v. Meyers, 231 F.Supp. 938 (Wash. 1964);Jurij Toplak, Equal Voting Weight of All: Finally “One Person, One Vote” from Hawaii to Maine? , 81 Temple L. Rev. 123 (2008); 高野克則「(私の視点)一票の格差:議員ごとの持ち票制で解消」朝日新聞2013年5月9日17面)。
しかしこれらの方策も、再選挙と同様、国会が必ず適正な再区割を行うことを担保するものではない。したがって、裁判所が再区割を行うことが終局的な救済方法であると考える。三権分立の静態的・硬直的な理解には反するかもしれないが、権力分立の目的は自由を守ることにあるというモンテスキューの真意(『法の精神』第11編第1章-6章(野田良之・稲本洋之助・上原行雄・田中治男・三辺博之・横田地弘(訳)、岩波文庫版(上)287-304頁)参照)に鑑みれば、立法部が選挙権の侵害を長年にわたって放置し、これを改善する意思も能力もない場合には、司法部が再区割を立法部の代わりに行うということ救済も容認されるものと解する。Baker v. Carr (Douglas, J., concurring), 369 U.S. 186, 241 (1962);中村良隆「一人一票原則の歴史的再検証」(PDFはこちら)比較法学36巻1号17頁(2002年)参照。 |
| 16. | ↑ | 最大判平成16年1月14日民集58巻1号56頁(深澤武久裁判官の反対意見)「投票価値の不平等が、かくも広く長期にわたって改善されない現状は、事情判決を契機として、国会によって較差の解消のための作業が行われるであろうという期待は、百年河清を待つに等しいといえる。」 |
| 17. | ↑ | 中村良隆「(私の視点)選挙区の人口格差:違憲なら裁判所が区割りも」朝日新聞2013年5月25日 |
| 18. | ↑ | 広島高裁平成25年3月25日(筏津順子裁判長)、広島高裁岡山支部平成25年3月26日(片野悟好裁判長)、同平成25年11月28日(同)の3つの高裁判決は、最高裁の判例理論によったとしても、選挙無効が決してありえない選択肢ではないことを例証している。特に、広島高裁岡山支部平成25年11月28日判決は、「仮に本件選挙における47選挙区の全ての選挙が無効になったとしても、平成22年選挙によって選出された議員と本件選挙における比例代表選挙による選出議員は影響を受けず、これらの議員によって、本件定数配分規定を憲法に適合するように改正することを含めた参議院としての活動が可能であることなどを考慮すれば、長期にわたって投票価値の平等という憲法上の要請に著しく反する状態を容認することの弊害に比べ、本件選挙を無効と判断することによる弊害が大きいということはできない。」と述べ、著者の主張を直截に認めている。
また、最高裁においても山本庸幸裁判官(最大判平成26年11月26日、最大判平成29年9月27日、および平成30年12月19日)ならびに木内道祥裁判官(最大判平成27年11月25日)が一定の格差を超えた選挙区に限定して選挙無効判決を下すべきという反対意見を執筆している。 なお、最大判平成29年9月27日において鬼丸かおる裁判官も、「仮に本件選挙は無効という結論を採っても、本件選挙によって選出された議員だけが議席を失うのであって参議院の機能は失われることがないから公の利益に著しい障害を直ちに生じさせないこと等を考えると、本件選挙を全部無効とする結論も採り得ると考える。」と述べているが、結論としては「本件選挙は違法というべきであるが、司法が直ちに選挙無効の結論を出すのではなく、まず国会自らが平成31年には必ず結論を得る旨を確約した是正の結果について司法が検証するということが、憲法の予定する立法権と司法権の関係に沿うものと考えるものである。」として選挙無効判決に踏み切るまでには至っていない。 |
| 19. | ↑ | 前著45頁、52-53頁 |




